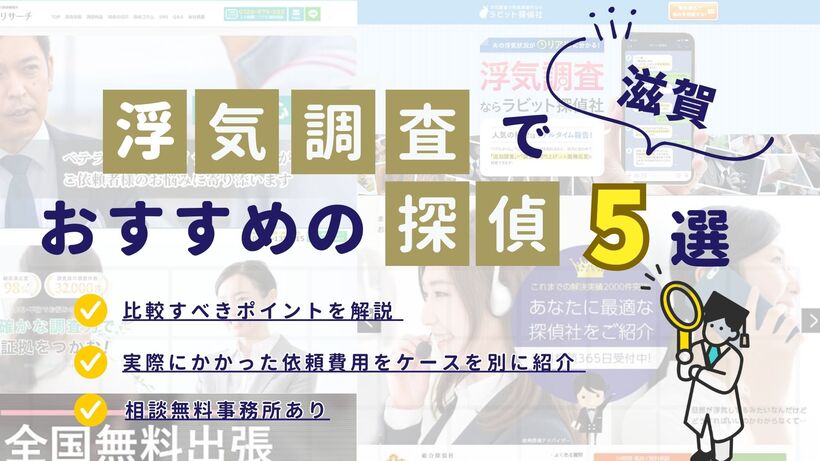離婚時に父親が親権を取るには?親権を獲得する方法・親権獲得できた事例を解説


子どもがいる夫婦が離婚する場合、「子どもの親権はどうするのか」が大きな争点となります。
司法統計によると、2023年におこなわれた離婚調停・審判離婚のうち母親が親権を獲得したケースは9割以上を占めています(令和5年司法統計年報 3家事編|最高裁判所)。
つまり、父親が親権を持つことは少ないということがうかがえます。
しかし、適切な対応を取ることで父親でも親権を獲得できる可能性があり、実際に親権が認められたケースもあります。
本記事では、父親が親権を取りにくい理由や親権者の判断基準、父親が親権を獲得するためにできることや、実際に父親が親権を獲得できた事例などを解説します。
親権とは?
親権とは、未成年の子どもへの監護・教育や、財産管理などをおこなう権利・義務のことを指します。
主に親権には「身上監護権」や「財産管理権」などの権利が含まれており、それぞれ民法で定められています。
| 権利 | 概要 | |
| ①身上監護権 | 監護教育権 | 子どもの教育や身の回りの世話をする権利・義務(民法第820条) |
| 居所指定権 | 子どもの住所・居所を親が決める権限(民法第822条) | |
| 職業許可権 | 子どもが職業を営むにあたって親が許可する権限(民法第823条) | |
| ②財産管理権 | 未成年の子どもの財産を親が代わりに管理する権利・義務(民法第824条) | |
なお、婚姻中の夫婦であれば共同で親権を持っていますが、離婚する場合はどちらかを親権者に設定しなければいけません(民法第819条1項)。
親権者の決め方としては、協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの方法があり、具体的な手続きの流れは「離婚時に父親が親権を獲得する方法」で後述します。
離婚時に父親が親権を獲得するのは難しい
2023年の司法統計年報によると、離婚調停・審判離婚での離婚件数1万6,103件のうち、父親が親権を獲得したのは1,290件で全体の約8%であるのに対し、母親は1万5,128件で全体の約94%を占めています(令和5年司法統計年報 3家事編|最高裁判所)。
現在の日本では、離婚時の親権者争いにおいて母親のほうが有利な状態にあり、父親が親権を持つことは決して多いとはいえないのが実情です。
ここでは、父親が親権を取りにくい理由や、法改正による変更点などを解説します。
父親が親権を取りにくい理由
父親が親権を取りにくい理由としては、主に以下のようなものがあります。
- 子どもが小さいほど母親のほうが有利になるため
- フルタイムで仕事をしていて育児との両立が困難なため
- 子どもが父親よりも母親に懐いていることも多いため
以下では、それぞれの理由について解説します。
子どもが小さいほど母親のほうが有利になるため
親権に関しては「母性優先の原則」という考え方があり、特に乳幼児期の子どもの親権に関しては父親よりも母親のほうが優先されやすい傾向にあります。
まだ子どもが幼ければ、親権争いで不利になることを考えて、子どもが大きくなるまで離婚を待ったほうが良い場合もあります。
ただし、あくまでも母性優先の原則は判断基準のひとつに過ぎないため、母親側にDVなどの何らかの事情がある場合は父親に親権が認められることもあります。
フルタイムで仕事をしていて育児との両立が困難なため
現在では夫婦共働きの家庭も増えているものの、「父親はフルタイムで仕事をして、母親が主に子どもの面倒をみている」という家庭も多くあります。
親権に関しては「これまでの養育実績」なども判断材料となるため、より多くの時間を育児に費やしている母親のほうが親権獲得で有利になりやすい傾向にあります。
なお、親権の判断基準については「裁判所が親権者を決める際の判断基準」で後述します。
子どもが父親よりも母親に懐いていることも多いため
親権に関しては「子どもが父親と母親のどちらと一緒に生活したいと考えているか」も判断材料となります。
特に、普段は仕事で忙しくて子どもと遊んだりする機会が少ない場合には、子どもが母親のほうに懐いてしまって母親との生活を選ぶ可能性があります。
改正民法の施行後は共同親権を選択できるようになる
2024年5月17日、離婚時に共同親権の選択を可能にする改正民法が可決・成立しました。
共同親権とは、離婚する際にどちらか一方が単独で子どもの親権を持つのではなく、共同で親権を持って子どもを育てるという制度のことです。
改正民法は2026年5月までに施行予定であり、施行後は離婚する際に単独親権と共同親権のどちらかを選択できるようになります。
また、共同親権の導入前に離婚している夫婦に関しても、裁判所にて親権変更の申立てが認められれば、単独親権から共同親権へ移行することが可能です。
裁判所が親権者を決める際の判断基準
基本的に、夫婦どちらが親権を持つかは話し合いによって決定します。
しかし、話し合いによる決着がつかない場合は、家庭裁判所にて調停委員を介して話し合う「離婚調停」に移行し、離婚調停も不成立となった場合は「裁判」で親権者を決定します。
裁判所が親権者を決める際は、次に挙げる7点が重視されるため把握しておきましょう。
1.母性優先の原則
乳幼児期の子どもの親権者を決める際には、母性を有する者が望ましいという考えがあります。
具体的には、子どもを受け入れて包みこむ愛情を持ち、きめ細やかな配慮ができる者を優先するという考え方です。
この考え方は母性優先の原則と呼ばれ、一般的には親権争いにおいて母親側が有利になる要因とされていますが、父親が母性に類する愛情やケアを提供できる場合にも考慮されます。
2.監護の継続性の原則
監護の継続性の原則とは、>子どもの現状を尊重し、できるだけこれまでの生活環境は変えないようにするべきという考え方のことです。
たとえば「夫婦がすでに別居しており、子どもが一定期間にわたって父親と安定した生活を送っている」という場合、その現状維持が推奨されるため父親が親権者としてふさわしいと判断されることがあります。
つまり、すでに生活をしていた一方の親と引き離すことで、引っ越しや転校などの子どもの生活にかえって大きな支障が生じるのであれば、今の環境を継続させたほうがよいと判断されるのです。
3.兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹不分離の原則とは、兄弟姉妹がいる場合は一緒に育てるほうが子どもにとって良いという考え方のことです。
一緒に暮らして育ってきた兄弟姉妹は情緒面や精神面の繋がりが強く、お互いに得るものがあって人格的に成長するという面から、分離によって悪影響が生じると考えられています。
そのため、兄弟姉妹が離れ離れにならずに済んで一緒に引き取れる環境のほうが有利になるのです。
4.面会交流の寛容性の原則
面会交流の寛容性の原則とは、離婚後の子どもとの面会交流に対するものであり、面会交流に協力的な親のほうが親権者に適しているという考え方です。
面会交流などを通じて、離婚後も他方の親とも交流をして良好な関係を保つことが子どもの人格形成に重要であるため、より子どもの面会交流を肯定的・積極的に考えている親かどうかが判断されます。
5.子どもの意思の尊重
ある程度の年齢に達した子どもの選択は尊重されるべきという考え方も強まっている傾向にあり、子どもの年齢によって判断の重みは異なります。
たとえば、子どもが乳幼児から10歳前後の場合は意思能力が比較的乏しいとされ、意思以外の判断基準に重きが置かれやすい傾向にあります。
一方、10歳前後から14歳の場合は意思能力が比較的認められ、子ども側の意思が考慮されるのが一般的です。
なお、15歳以上の場合は審判や訴訟時に必ず子どもへの意思聴取がおこなわれ、子どもの意思が重要視されます。
子どもがはっきりと自分の意思を伝えており、その親と暮らすことが客観的にみても特に問題なければ、基本的には子どもの意思が尊重されます。
6.監護態勢の優劣
子どもを育てるためには膨大な時間とお金が必要であることから、監護態勢の優劣も重要な判断要素となります。
これは、子どもがより良い環境で生活できるほうを選ぶべきという考え方に基づくものです。
親権争いにおいて、子どもの利益の観点からみて今後の養育環境を考慮する際は「子どもに寄り添った生活ができるか」「経済的に子どもを養える状況にあるか」という点が問われます。
もし親が子どもと一緒に過ごす時間を十分に確保できなければ、子どもの心の育成はできません。
また、経済的に厳しい状況であれば、十分に監護をおこなうことは難しいでしょう。
たとえば「自分は仕事中心の生活をしているため、基本的に子どもは自分の親に預かってもらって面倒をみてもらう」というような状況では、たとえ経済的には潤っていても子どもと一緒に過ごす時間が短く、心の育成には適切でないと判断される可能性があります。
7.親の年齢・健康
心身ともに健康な親が養育したほうがよいと考えられるため、親の年齢や健康状態も重要な判断基準のひとつです。
心身の不調は生活を破綻させる可能性が懸念され、健康状態が悪い場合や高齢な場合などは、子どもの養育や監護が十分におこなわれるかが不安点となります。
したがって、子育て自体にも体力が必要ですし、かつ経済的な安定のために就労するにあたっても健康でいることが重要になります。
父親が親権争いで有利になる4つのケース
現在の日本では母親側に親権が認められやすいものの、なかには父親が親権者として選ばれるケースもあります。
ここからは、父親に親権が認められやすい4つのケースを紹介します。
1.父親が日常的に育児をしている場合
子どもの親権者として相応しいか判断する際、父親が日常的に育児をしているかどうかが極めて重要です。
これまで日常的に育児に関わってきた場合、将来的にも安定して養育できる可能性が高いと判断され、親権者として認められることがあります。
なお、これまでの育児状況を立証する手段としては、保育園や幼稚園の連絡帳、自身の日記やスケジュール、保育施設や友人の陳述書などが挙げられます。
2.母親が育児放棄や虐待をしている場合
母親が育児放棄や虐待をしている場合、父親側に親権が認められやすくなります。
育児放棄の一例としては、母親が子どもに対して食事を与えない・何日も同じ服を着させる・お風呂に入れない・学校に行かせないなどの行為が該当します。
なお、育児放棄や虐待の事実があったことを示す証拠が必要となるため、子どもにけがやアザがある場合は写真に残し、医師に診断書を作成してもらいましょう。
ほかにも、日記・音声・動画データなども有力な証拠になり得るため、率先して証拠集めをおこなってください。
3.母親が子どもよりも不倫相手を優先するおそれがある場合
母親が浮気をしていて不倫相手と遊んでいるような場合、母親が子どもよりも不倫相手を優先するおそれがあるという理由から、父親の親権が認められることもあります。
なお、親権はあくまでも子どものための権利であるため、母親側の不倫が理由で離婚することになったからといって、ただちに子どもの養育に不適格であると判断されるわけではありません。
「子どもの養育が十分におこなわれず、幼い子どもを家に置いて不倫相手と出かけている」などの事実がある場合には、親権争いに影響します。
4.子どもが父親との生活を望んでいる場合
子どもが父親との暮らしを強く望んでいる場合、父親に親権が認められる可能性が高く、特に10歳以上の子どもの主張は立派な判断材料になります。
ただし、子どもの年齢や性格によっては親に気を遣ったり、自分の本当の気持ちを発言できなかったりする可能性もあります。
実際の離婚手続では、家庭裁判所の調査官によって慎重に意思確認がおこなわれます。
離婚後に父親が親権を勝ち取ることが出来た事例
父親として親権争いを有利に進めたい場合は、弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士なら、法律知識やノウハウを活かして親権の獲得のために尽力してくれて、実際に弁護士のサポートによって親権を勝ち取ることができたケースもあります。
ここでは、当社が運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ離婚」に掲載している解決事例の中から、父親が親権を獲得できたケースを3つ解説します。
母親のモラハラを主張して父親の親権が認められたケース
夫は妻の暴言や生活の乱れで悩んでおり、子どもを連れて別居を始めて離婚手続を進めていたところ、妻と親権について争いになったという事例です。
夫は「親権を獲得するために徹底的に争いたい」という強い希望があったため、依頼を受けた弁護士は裁判も視野に入れて対応を進めました。
面会交流調停では、子どもの生活状況にも配慮しながら何度も話し合いの機会を設けて、結果的に夫側が納得のいく形で取り決めることができました。
離婚に関しては離婚調停が不成立となったため離婚裁判に移行し、裁判では夫の育児状況や妻のモラハラなどを証拠を用いて主張したことで、最終的に妻は親権の取得を諦めて離婚慰謝料の獲得にも成功しました。
母親の不倫が発覚して父親の親権が認められたケース
妻が不倫をしていて不倫相手と同居するようになり、夫婦ともに離婚の意思はあったものの、親権・養育費・財産分与・慰謝料などについて争いになったという事例です。
離婚自体に争いはなかったものの取り決めるべき事項が多く、夫は自力での対応に不安を感じて弁護士にサポートを依頼しました。
依頼を受けた弁護士が妻との話し合いを持ちかけたところ、妻側も弁護士を立ててきたため、弁護士間で離婚に向けた手続きを進めることになりました。
離婚手続では、これまで夫が子育てに尽くしてきたことや、離婚後の養育環境も整っていることなどを主張したことで親権の獲得に成功し、財産分与などの離婚条件についても夫側が納得のいく形で取り決めることができました。
離婚協議によって父親の親権が認められたケース
妻が子どもとともに別居を始める準備を進めていたため、それを察した夫が先に子どもを連れて別居を始めたところ、妻によって子の監護者指定・引渡しの審判・各保全処分の申立てなどがおこなわれたという事例です。
依頼を受けた弁護士は各手続きに対応し、別居の経緯などの夫側の主張を整理した書面を裁判所に提出したほか、夫に対しては家庭裁判所調査官による調査対応のアドバイスなどのサポートもおこないました。
第二審まで争われたものの、結果的には夫が監護者として指定され、妻の申立ては却下となりました。
審判後は妻との協議離婚を進めて、最終的には夫が親権を獲得する形で離婚成立することができました。
父親が親権を取るには?親権獲得のためにできること
ここからは、子どもの親権を父親が獲得するためにできることを解説します。
1.養育環境を整えておく
まずは、養育環境を整えることが重要です。
子どもと過ごす時間を長く取れるように仕事時間を調整できるかどうか、仕事の都合で子どもと一緒にいられない場合は両親などの周囲の協力を得られるかなどがカギとなります。
子どもを養育する環境が十分に整っていることを主張できれば、親権を獲得できる可能性が高まります。
2.これまでの養育実績を証明する資料を準備する
子どもをどの程度養育してきたのか、これまでの養育実績を証明できるものも準備しておきましょう。
たとえば、お弁当を含む食事の支度・洗濯・掃除・学校行事への参加・病気になった際の看病状況・休日の過ごし方など、具体的な養育実績がわかるメモ・日記・写真を準備しておきましょう。
3.母親の育児放棄や虐待の証拠を揃えておく
母親が育児放棄や虐待をしている場合、その事実を証明できる詳細な証拠も揃えておきましょう。
虐待は、暴行を加える身体的虐待だけでなく、暴言や罵声を浴びせるなどの心理的虐待も含まれます。
たとえば、日々育児放棄している状況を記載した日記・けがの写真・動画などが有効な証拠となります。
4.家庭裁判所の調査には丁寧かつ明確に対応する
離婚調停などで争っている場合、なかには家庭裁判所の調査官が子どもの現状を調査するために家庭訪問をおこなうことがあります。
調査官の判断は親権者の決定に大きく影響するため、常識のある態度で真摯に対応するように心がけましょう。
調査官は、日常生活の事柄について質問する形で調査をおこない、子どもの養育に適しているかどうかを確認します。
尋ねられたことには具体的かつ明確に回答し、くれぐれも嘘をつくことや、自身に有利に働くような過剰な主張などは控えましょう。
5.別居時から子どもと生活する
裁判所による親権者の判断基準のひとつとして「監護の継続性の原則」があり、子どもの生活の現状維持が優先されます。
子どもと一緒に生活している親のほうが親権争いでは有利になりやすいため、別居する際は子どもと生活することが大切です。
もし別居するにあたって子どもを相手に渡さなければならないような場合は、親権争いで不利な状況に陥ることを避けるためにも、離婚するまでは別居せずに過ごすことも検討しましょう。
6.乳幼児期を過ぎてから離婚する
父親が乳幼児期の子どもの親権を得るのは不可能ではないものの、非常に難しいというのが実情です。
裁判所は母性優先の原則も判断基準のひとつとしているため、基本的に乳幼児期の子どもであれば余程のことがない限り、母親に親権がわたってしまいます。
そのため、少なくとも乳幼児期を過ぎるまでは、離婚は待ったほうが賢明だといえます。
離婚時に父親が親権を獲得する方法
相手と親権争いをする場合、以下のような流れで手続きを進めるのが通常です。
1.夫婦同士で離婚協議をおこなう
親権者を決定する際、まずは夫婦同士で直接話し合って解決を図ります。
話し合いの中で親権などについてお互いが合意すれば、離婚届に親権者を記載して役所に提出することで離婚が成立し、親権問題も解決となります。
なお、子どもが複数いる場合には、両親のどちらが親権者になるのかを一人ずつ決めなければなりません。
2.離婚調停を申し立てる(離婚協議が不成立の場合)
夫婦で話し合いをしても解決せず、親権者について合意できない場合は、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。
離婚調停にあたって必要となる書類は次のとおりです。
- 離婚調停申立書
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 夫婦の戸籍謄本
- 連絡先等の届出書 など
離婚調停では、お互いに顔を合わせることなく自身の主張ができ、調停委員がそれぞれの主張をまとめて状況を把握し、必要に応じて調査をおこないます。
調停委員によって双方の主張を踏まえた解決方法が提案され、双方が納得すれば調停成立となり、親権問題も解決となります。
3.離婚裁判で争う(離婚調停が不成立の場合)
離婚調停でも親権が決まらなかった場合は、離婚裁判で争います。
親権争いの場合は調査官調査がおこなわれることもあり、子どもや親との面接調査・学校や幼稚園での聞き取り調査など、さまざまな方法で親の的確性が調査されます。
その際、父親が主体となって育児をしていた実績や、母親が育児放棄をしていた証拠などがあれば非常に役に立つでしょう。
離婚裁判では双方が主張立証をおこない、最終的にはこれまでの養育実績・子どもの年齢・現状などのさまざまな事情をもとに、裁判官が親権者を決定します。
父親が親権を獲得できなかった場合の対処法
もし親権争いで母親が親権者となった場合、父親が検討すべき方法としては以下があります。
子どもとの面会交流を求める
親権を獲得できなかった場合、子どもとの面会交流を求めましょう。
面会交流とは、子どもと暮らしていない側の親が定期的に子どもと会うことを指し、子どもの健やかな成長のために必要とされているものです。
もし親権を獲得することができなかったとしても、子どもと会って直接交流する権利はあります。
なお、面会交流は継続性をもって確実に実施できるよう、現実的な方法を相談のうえで決定しなければなりません。
気持ちを切り替えて面会交流の回数を増やす交渉ができれば、子どもと接する機会が多くなり、子どもの成長を見守って支えていることが実感できるでしょう。
親権者変更調停を申し立てる
一度決定した親権は、親の勝手な都合や気持ちで変更することはできません。
しかし、「子どもが親権者である母親から育児放棄や虐待を受けている」「父親に親権者を変更してほしいと望んでいる」などの正当な理由がある場合は、家庭裁判所にて親権者変更調停を申し立てて親権の変更を求めることが可能です。
ただし、親権者を変更することで子どもの生活環境が大きく変わって混乱を生じさせる可能性もあるため、慎重に検討しなければなりません。
監護権者の変更を申し入れる
親権者でなくても子どもと一緒に暮らしたい場合、監護権者の変更を申し入れるという方法もあります。
監護権とは、子どもとともに生活を送り、日々の世話や教育をする権利を指します。
基本的には親権者が子どもの監護権も有していますが、親権と監護権を分離することも可能です。
監護権者を変更する際は、父親と母親で協議をおこなって合意できれば変更となり、協議不成立の場合は調停や審判などに移行することになります。
父親の親権に関するよくある質問
最後に、父親の親権に関するよくある質問について解説します。
親権争いでは母親のほうが有利?父親が不利なのはなぜ?
多くの場合、親権争いでは母親のほうが有利になります。
一般論では、父親よりも母親のほうが育児に手が回るため、養育上において子どもの成長過程を考慮すると母親と一緒に暮らすことが望ましいと考えられています。
父親の場合、子どもに突然の事故や病気などがあった際の対応も比較的困難と考えられ、このような生活環境は子どもにとって好ましくないといえます。
ほかにも、父親のほうが養育実績が乏しいケースが多かったり、特に乳幼児期の子どもについては母性優先の原則が考慮されたりするなど、さまざまな事情で父親のほうが不利になりやすい傾向にあります。
父親が親権を獲得した場合、母親に養育費を請求できる?
父親が親権を獲得した場合は、母親に対して養育費を請求することが可能です。
ただし、養育費の金額は、夫婦それぞれの収入を考慮したうえで決定する必要があります。
そのため、親権者である父親のほうが収入が高い場合や、母親に十分な支払い能力がないような場合には、養育費が免除・減額されることもあります。
離婚原因は親権の獲得に影響する?
もし母親側の不貞行為が原因で離婚する場合でも、子どもの養育を十分におこなっていれば、基本的に不貞行為自体が親権争いに影響することはありません。
しかし、子どもの養育が十分におこなわれず、幼い子どもを家に置いて不倫相手と出かけているなどの事実があれば親権争いに影響します。
また、DVが原因で離婚する場合には、たとえ子どもに直接暴力をふるっていなくても監護者・親権者としての適格性が問題視され、親権争いに影響を及ぼす場合もあります。
母親が無断で子どもを連れ去ったときはどうする?
離婚成立前に母親が無断で子どもを連れ去った場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
実際に罪に問われる可能性は低いものの、これまでの監護状況によっては連れ去った母親が親権者として不適格であると判断される可能性があります。
なお、連れ去られた子どもを取り戻すには、家庭裁判所に対して「監護者指定・子の引渡し審判」と「審判前の保全処分」を申し立てる必要があります。
さいごに|父親が親権を獲得するためにも、まずはベンナビ離婚で相談を
離婚時に父親が親権を獲得するためには、どれだけ子どもの幸せを考えて健康に成長できる環境を整えられるかが重要です。
少しでも親権獲得の可能性を高めたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら「親権獲得が見込めるかどうか」「今後どのように動くべきか」などのアドバイスが望めるほか、配偶者との交渉・調停・裁判などの対応を一任することも可能です。
弁護士にサポートしてもらいながら、養育実績を積み上げて養育環境を整えることで、父親でも親権を獲得できる可能性は大いにあります。
当社が運営する「ベンナビ離婚」では、親権請求などの離婚問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
お住まいの地域から対応可能な弁護士を一括検索でき、初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、親権問題で悩んでいる方は一度ご利用ください。