相続放棄申述申し立ての必要書類完全ガイド!続柄別・取得場所についても解説

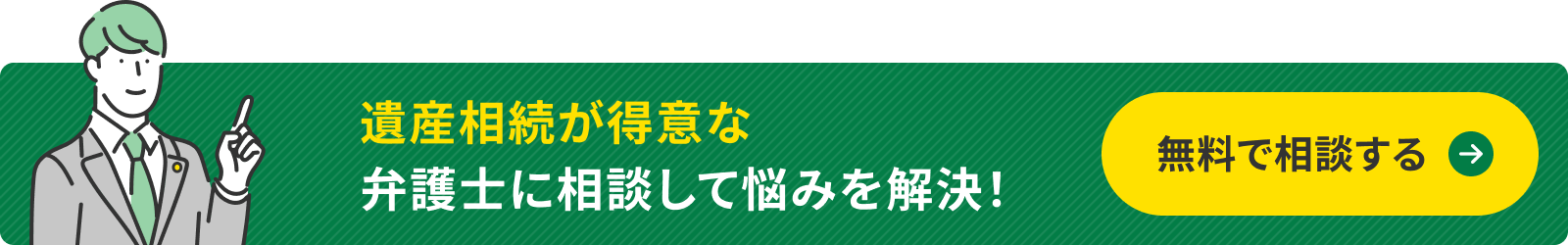

- 「亡くなった兄弟の借金が発覚したので、相続放棄をしたい」
- 「相続放棄を自分でおこなうので、必要書類を知りたい」
相続発生時に今まで知らなかった借金や負の遺産の存在がわかり、相続放棄を検討している方もいるでしょう。
相続放棄には、戸籍や申述書などさまざまな書類が必要です。
また、亡くなった方との関係性によっても、必要書類は異なります。
本記事では、相続放棄に必要な書類や入手場所などについて解説します。
自分で相続放棄の手続きをおこないたいと考えている方は、この記事を参考にして必要書類を把握しましょう。
相続放棄の申述に必要な書類と入手場所
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなう必要があります。
相続放棄の申述に必要な書類は、被相続人との関係性によって異なります。
まずは全ての関係者に共通して必要な書類について見ていきましょう。
| 必要書類 | 入手場所 |
|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所のホームページ 成人が相続放棄をおこなう場合 未成年が相続放棄をおこなう場合 |
| 被相続人の住民票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地(戸籍附票の場合は本籍地)を管轄する役所 (郵送等での申請も可能) |
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地を管轄する役所 (郵送等での申請も可能) |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地を管轄する役所 (郵送等での申請も可能) |
| 相続人であることがわかる戸籍謄本類 | 被相続人、申述人の本籍地を管轄する役所 |
1.相続放棄の申述書|裁判所ホームページよりダウンロード可能
相続放棄に必要な1つ目の書類は、相続放棄の申述書です。
相続放棄の申述書とは、相続放棄の意思表示をする書面のことです。
当事者の氏名や本籍地、住所地、相続放棄の理由などを記載します。
書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
成人が申述人になる場合と、未成年が申述人になる場合では書式が異なるので気をつけましょう。
2.被相続人の住民票または戸籍附票|住所地または本籍地の市町村役場で取得
相続放棄に必要な2つ目の書類は、被相続人の住民票または戸籍の附票です。
相続放棄の申述書には、被相続人の住所地を記載する欄があるため、被相続人の住所地がわかる書類が必要になります。
住民票は、被相続人の最後の住所地を管轄する役所で取得可能です。
戸籍の附票は、被相続人の本籍地を管轄する役所で取得できるので、どちらかを用意するようにしましょう。
3.被相続人の戸籍謄本|誰が申述するかで必要な範囲が異なる
相続放棄に必要な3つ目の書類は、被相続人の戸籍謄本です。
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する役所で取得できます。
ただし、誰が申述人になるかによって必要な戸籍謄本の範囲は異なるので注意しましょう。
たとえば、申述人が被相続人の配偶者や子どもであれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本のみで問題ありません。
第1順位の相続人が相続放棄をする場合、必要な戸籍謄本は少なく済むでしょう。
ただし、第2順位以下の相続人が相続放棄をする場合は事情が異なります。
たとえば、申述人が被相続人の父母である場合、被相続人と第1順位の子どもおよび、孫の出生から死亡までがわかる戸籍謄本が必要です。
詳しくは家庭裁判所のホームページに記載があるので、確認しておきましょう。
4.申述人の戸籍謄本|本籍地の市町村役場で取得
相続放棄に必要な4つ目の書類は、申述人の戸籍謄本です。
申述人の戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で取得できます。
なお、相続放棄の申述には、発行から3ヵ月以内の現在戸籍が必要です。
古い戸籍は使用できないので、気をつけましょう。
5.相続人であることがわかる戸籍謄本類
相続放棄に必要な5つ目の書類は、相続人であることがわかる戸籍謄本類です。
申述人が本当に被相続人の相続人なのかを証明するためには、戸籍謄本が必要です。
申述人が配偶者や子であれば、被相続人死亡の記載がある戸籍謄本と申述人の戸籍謄本が必要になります。
ただし、第2順位以下の相続人が相続放棄をする場合は、被相続人の出生~死亡の戸籍謄本一式、申述人と被相続人のつながりがわかる戸籍謄本を用意しなければなりません。
集める戸籍が多く、相続関係が複雑であれば、専門家への依頼を検討しましょう。
被相続人との続柄別・相続放棄の申し立てに必要な書類一覧
ここからは、被相続人との続柄別に、相続放棄の申し立てに必要な書類を一覧で紹介します。
| 被相続人との関係 | 必要書類 |
|---|---|
| 配偶者 | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎被相続人の戸籍謄本 |
| 子ども | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎被相続人の戸籍謄本 ✔︎ご自身の戸籍謄本 |
| 孫 | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎被相続人の戸籍謄本 ✔︎ご自身の戸籍謄本 ✔︎本来の相続人(被相続人の子)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 親 | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎被相続人の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎ご自身の戸籍謄本 ✔︎第1順位の相続人(及び代襲者)の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 祖父母 | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎ご自身の戸籍謄本 ✔︎被相続人の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎第1順位の相続人(及び代襲者)の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹 | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎ご自身の戸籍謄本 ✔︎被相続人の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎第1順位の相続人(及び代襲者)の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本(年代的に明らかに亡くなっていると推測される場合は不要) |
| おい・めい | ✔︎相続放棄の申述書 ✔︎被相続人の住民票または戸籍附票 ✔︎ご自身の戸籍謄本 ✔︎被相続人の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎第1順位の相続人(及び代襲者)の出生~死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本 ✔︎被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本(年代的に明らかに亡くなっていると推測される場合は不要) ✔︎被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本 |
代襲相続が起こった場合は本来の相続人の戸籍謄本が必要
代襲相続が起こった場合は、本来の相続人の戸籍謄本が必要です。
代襲相続とは、法定相続人の死亡などが理由で相続できないときに、その下の代へと相続権が移ることを指します。
たとえば親が死亡し、その子どもも死亡しているなら、孫への代襲相続が発生します。
この場合、孫に相続権が移ったという証明をしなければならないので、本来の相続人(子ども)が死亡していることがわかる戸籍謄本が必要です。
同じ書類は1通でOK
相続放棄の必要書類において、同じ書類は1通のみ用意すれば問題ありません。
ひとつの戸籍に必要な情報が複数載っていることも考えられます。
たとえば、被相続人の死亡の記載がある戸籍が、配偶者の現在戸籍を兼ねている場合などです。
相続放棄にあたって複数の戸籍を集めることになりますが、情報が被っているものは1通のみ提出するようにしましょう。
相続放棄の申述に必要な費用
相続放棄の申述の際、申述人1人につき収入印紙800円と、各地の家庭裁判所が定めた所定の郵便切手が必要です。
東京家庭裁判所の場合、110円分の郵便切手を4組(計440円)用意しましょう。
相続放棄の申述の必要書類についてよくある質問
最後に、相続放棄の申述の必要書類についてよくある質問を7つ解説します。
1.被相続人の戸籍謄本は亡くなる前に取得したものでもよいでしょうか?
被相続人の戸籍謄本は、亡くなったあとに取得しましょう。
相続放棄をするにあたって必要なのは、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本です。
死亡の記載がない戸籍謄本では手続きができないため、必ず亡くなったあとに取得してください。
2.申述人の戸籍謄本はいつ取得したものでもよいでしょうか?
申述人の戸籍謄本は、発行から3ヵ月以内のものを用意しましょう。
また、被相続人の死亡がわかる戸籍も、発行から3ヵ月以内のものが必要です。
ただし、被相続人やその他の相続人の過去の戸籍謄本に関しては、過去のものと現在のもので情報が変わるわけではないので、使用期限はありません。
3.被相続人の兄弟姉妹です。戸籍謄本は取得できるでしょうか?
相続放棄の意思表示をすれば、兄弟姉妹でも戸籍謄本の取得が可能です。
ただし、戸籍謄本を取得するには、相続人であるという証明が必要な場合があります。
取得のルールは自治体によっても異なるため、管轄の役所に確認しましょう。
また、弁護士などの専門家であれば、職権によって代理で戸籍を取得できます。
自身での戸籍収集が難しいのであれば、専門家への依頼がおすすめです。
4.被相続人の子ども2人で一緒に申し立てをします。共通する書類は省略できますか?
複数人で同時に相続放棄を申立てる場合、共通書類は省略が可能です。
基本的に同じ書類は、1通の提出で問題ありません。
また、既に他の相続人が相続放棄の申述をしており、その際に提出された書類と重複する書類も省略できます。
5.期限内に必要書類をそろえられません。どうすればよいでしょうか?
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月という期限があります。
3ヵ月の期限内に書類が間に合わない場合は、取り急ぎ相続放棄の申述書を提出し、後日必要書類を追加で提出しましょう。
申述の際、足りない書類はあとで提出する旨のメモを同封しておけば、裁判所も事情を理解してくれるはずです。
期限内に全ての書類を揃えて申し出をしたいなら、弁護士への依頼を検討しましょう。
なお、すでに相続放棄の期限が過ぎている場合は速やかに弁護士へ相談してください。
6.相続放棄の必要書類の収集は専門家に依頼できますか?
相続放棄に関する書類収集は、弁護士に依頼可能です。
相続関係はケースによっては非常に複雑で、個人で戸籍を集める作業が困難なことも考えられます。
弁護士であれば手続きにも慣れていますし、職権で戸籍を集めることができるので、迅速かつ漏れなく収集できるでしょう。
7.相続放棄申述書の記入例はありますか?
相続放棄申述書のひな形と記載例は、裁判所のホームページに掲載されています。
ダウンロードもできるので、参考にして記入を進めましょう。
さいごに|相続放棄の必要書類の収集で困ったら弁護士に相談を
相続放棄をするには、さまざまな書類が必要です。
さらに、相続関係が複雑になればなるほど、必要書類も増えます。
書類集めに困ったら弁護士へ相談しましょう。
弁護士は職権で戸籍を請求できるうえ、複雑な相続でも抜け漏れなく戸籍を集めてくれるはずです。
相続放棄の必要書類や、相続放棄申述の手続きをご自身でおこなうのが困難であれば、早めに弁護士へ相談しましょう。







