交通事故(人身事故)で科される罰金の相場!罰金刑を避けるための3つのポイントも

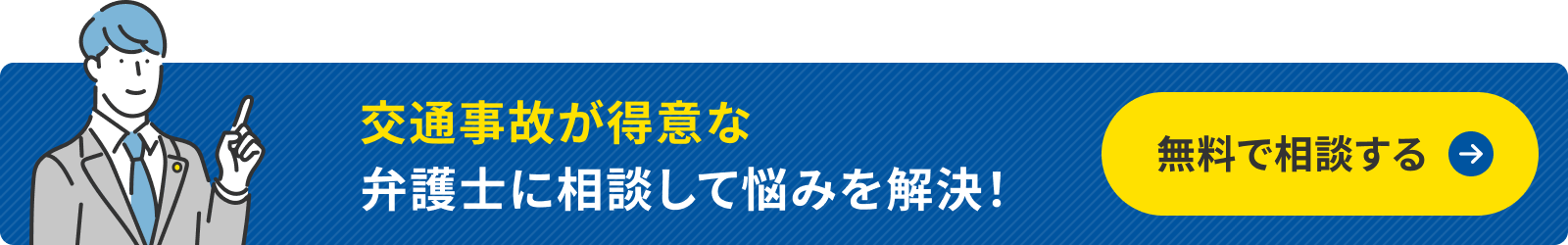

交通事故を起こして人を轢いてしまったときには、人身事故を起こしたことに対して民事責任・刑事責任・行政責任の3種類の法的責任が課されます。
また、人身事故について刑事責任を追及されるときは、逮捕・勾留という身柄拘束処分だけではなく、有罪判決が下されるリスクも生じます。
人身事故という重大な交通事故を起こした以上、法的責任を果たすのは当然のことですが、今後の社会生活のことを考えると、できるだけ軽い刑事処分を目指すために適切に対応すべきでしょう。
本記事では、人身事故を起こしたときに加害者に適用される可能性がある犯罪類型や、罰金刑が確定したときの相場、弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
交通事故(人身事故)で科される可能性がある主な刑事罰
まずは、人身事故を起こした加害者に適用される可能性がある犯罪類型や刑事罰を解説します。
過失運転致死傷罪|100万円以下の罰金または7年以下の懲役・禁錮
自動車を運転する際に、運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させたときには、「過失運転致死傷罪」で処罰されます。
過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑」です。
ただし、被害者が負った傷害の程度が軽いときには、情状によって刑が免除されます。
過失運転致死傷罪が適用される具体例として以下のものが挙げられます。
- 赤信号を無視して交差点に進入して走行中の車両に衝突した
- 停止線を無視して交差点に進入して横断歩道を歩行中の人を轢いた
- 運転中のスマートフォン操作などにより前方不注意に陥り、停車していた車両に後方から追突した
- 運転中のハンドル操作を誤り対向車線を走行中の原動機付自転車に接触した
- 駐車時にアクセルとブレーキを踏み間違えてコンビニエンスストアの店舗内に進入してお客さんを轢いた など
危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第2条)|15年以下の懲役(負傷)、1年以上の有期懲役(死亡)
以下の1号~8号のいずれかに該当する行為を故意におこなった結果、人を死傷したときには、「危険運転致死傷罪」で処罰されます。
危険運転致死傷
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者に生じた結果次第で異なります。
具体的には、被害者が負傷したときには「15年以下の懲役刑」、被害者が死亡したときには「1年以上の有期懲役刑」です。
危険運転致死傷罪が適用される事案では、罰金刑は適用されません。
危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第3条)|12年以下の懲役(負傷)、15年以下の懲役(死亡)
アルコールや薬物、一定の病気の影響によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合には、「危険運転致死傷罪」が適用されます。
本条に規定される危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が負傷したときには「12年以下の懲役刑」、被害者が死亡したときには「15年以下の懲役刑」です。
本条で処罰されるときには罰金刑は適用されません。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪|12年以下の懲役
アルコールや薬物は、体内に取り込んでから一定期間が経過すれば、検査をしても反応が消滅・軽減する性質があります。
つまり、アルコールや薬物の影響によって交通事故を引き起こした場合でも、これらの影響がなくなってから出頭すれば、比較的軽微な過失運転致死傷罪での摘発を狙うことができてしまうということです。
これでは、飲酒運転による交通事故などの悪質な行為に及んだ加害者に対して重い刑事罰を科すことができません。
そこで、自動車運転死傷処罰法では、以下3つの行為に対して「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」として処罰する規定を設けています。
- 運転時のアルコールや薬物の影響を隠す目的で、さらにアルコールや薬物を摂取すること
- 現場を離れてアルコールや薬物の濃度を減少させること
- その他、アルコールや薬物の影響や程度が発覚することを免れること
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役刑」です。
罰金刑は適用されません。
無免許運転による加重
自動車運転死傷処罰法に規定される犯罪・交通事故を無免許の状態で起こしたときには、以下のように法定刑が加重されます。
とくに、過失運転致死傷罪が適用される事案では、無免許運転による加重によって、罰金刑がなくなる点に注意が必要です。
- 危険運転致傷罪(第2条):6ヵ月以上の有期懲役刑
- 危険運転致傷罪(第3条):15年以下の懲役刑
- 危険運転致死罪(第3条):6ヵ月以上の有期懲役刑
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条):15年以下の懲役刑
- 過失運転致死傷罪(第5条):10年以下の懲役刑
無免許の状態で自動車を走行させること自体に悪質性が認められるため、免許があるときに交通事故を起こしたケースよりも法定刑が引き上げられています。
救護義務違反|100万円以下の罰金または10年以下の懲役
人身事故を起こした場合、加害者を含む車両の運転者などは、速やかに車両を停止して、負傷者を救護する義務(救護義務)が課されています。
たとえば、交通事故現場で人を轢いたのにそのまま現場を離れた場合には、救護義務違反(ひき逃げ)を理由に刑事責任を追及されます。
救護義務違反の法定刑(人の死傷が自分の運転が原因であるとき)は、「10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」です。
なお、信号を無視して人を轢いたにもかかわらず、そのまま現場を立ち去ったときには、救護義務違反と同時に過失運転致死傷罪も成立します。
両者の関係は併合罪に立ち、懲役・禁錮については「その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたもの」、罰金については「それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下」で処断されます。
報告義務違反|5万円以下の罰金または3ヵ月以下の懲役
交通事故を起こした運転手には、事故を起こした日時等について報告をする義務(報告義務)が課されています。
たとえば、人身事故を起こして車両を停車して被害者のところに立ち寄ったところ、被害者が「たいした怪我もないし、私も不注意だったので大丈夫です」と声をかけられて、それならばとその場を立ち去ってしまうと、報告義務違反に該当します。
報告義務違反の刑事罰は「3ヵ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」です。
なお、警察に通報をしておかなければ、交通事故証明書を取得できない点にも注意が必要です。
交通事故証明書がなければ、任意保険関係の手続きを進めることができず、被害者に対して自動車保険から保険金を支払うことができなくなってしまいます。
人身事故が過失運転致死傷罪になったときの罰金の相場
人身事故の加害者として過失運転致死傷罪の容疑で有罪になったときには、「7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑」の範囲で刑事罰が科されます。
過失運転致死傷罪の罰金刑の相場は以下のとおりです。
| 被害者のけがの程度 | 罰金の相場 |
|---|---|
| ・重傷事故(全治3ヵ月以上) ・後遺障害あり |
・加害者に全責任がある場合:30万円〜50万円程度 ・被害者にも責任がある場合:30万円〜50万円程度 |
| ・重傷事故(全治30日以上、3ヵ月未満) | ・加害者に全責任がある場合:30万円〜50万円程度 ・被害者にも責任がある場合:20万円〜50万円程度 |
| ・軽症事故(全治15日以上、30日未満) | ・加害者に全責任がある場合:15万円〜30万円程度 ・被害者にも責任がある場合:15万円〜30万円程度 |
| ・軽症事故(全治15日未満) | ・加害者に全責任がある場合:10万円〜20万円程度 ・被害者にも責任がある場合:10万円〜20万円程度 |
なお、刑事罰の重さは、人身事故で生じた被害の規模や加害者の過失の程度、反省の有無、示談が成立しているか、被害者側の処罰感情の強さなど、諸般の事情を総合的に考慮したうえで決定されます。
できるだけ罰金刑の金額を引き下げたい場合は、捜査段階から刑事弁護を得意とする専門家に依頼し、対応方法などについてアドバイスをもらうべきでしょう。
【事例付き】人身事故を理由に罰金刑が科されたケース
人身事故を起こして罰金刑が科された実際の事例を紹介します。
自動車で女児をはねて全治90日のけがを負わせた事例|罰金70万円
本件は、2022年9月1日の午後3時頃、横断歩道を渡っていた小学1年生の女児を乗用車がはねた事例です。
被害にあった女児は、すねの骨折など、全治約90日の重傷を負っています。
被害者が負った怪我が重いこと、横断歩道を通行中の歩行者には一切過失がなく、加害者側に全過失があるケースであることから、70万円の罰金刑が略式裁判で確定しました。
【参考】茨城県職員に罰金70万円 車で女児はね骨折させる - 産経ニュース
捜査車両を運転中に女児をはねて軽傷を負わせた事例|罰金10万円
本件は、2024年5月27日の午後3時40分頃、男性警察官が公務中、見通しの良い道路上の横断歩道付近を渡ろうとしていた5歳女児を捜査車両ではねた事例です。
女児は頭部に軽傷を負いました。
公務中の警察官には車両運転中に高度の注意義務が課されているために罰金刑が下されましたが、被害者が負った怪我が比較的軽傷であったため、10万円の罰金刑が確定しました。
【参考】捜査車両で女児はねた警察官に罰金10万円 松江簡裁 | 中国新聞
人身事故が有罪になり罰金を支払うまでの流れ|略式裁判になることが多い
人身事故を起こして刑事訴追されたときの手続きの流れは、以下のとおりです。
【人身事故が罰金刑の場合の大まかな流れ】
- 交通事故発生、警察に110番通報する
- 人身事故であることを把握して警察が実況見分を実施する
- 警察段階の取り調べが実施される(任意捜査になることが多いが、状況次第では逮捕・勾留される可能性もゼロではない)
- 検察段階の取り調べが実施される(在宅事件として刑事手続きが進むことが多いが、逮捕・勾留が継続する可能性もゼロではない)
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
- 罰金刑の場合、検察官が略式起訴を下す(通常の起訴処分が下された場合、公開の刑事裁判を経て罰金刑などの刑罰が確定する)
- 検察庁から罰金の納付書を受け取る
- 罰金を納付する
なお、罰金刑が下される刑事事件では、「略式手続き」という流れがとられることが多いです。
略式手続きとは、簡易裁判所の管轄事件について、公開の刑事裁判を省略して、検察官の請求による書面審理だけで罰金刑を確定させる刑事手続きのことです。
100万円以下の罰金刑または科料を科す事件であり、被疑者が略式手続きに同意をしているときに限り、公判手続きを遂行する負担を回避できます。
もちろん、公開の刑事裁判で反論したいと考えるのなら、略式手続きに同意をする必要はありません。
一方、実際の刑事裁判で無罪を獲得するのが難しい状況なら、略式手続きに同意をしたうえで、早期に刑事手続きを終了させるのも選択肢のひとつでしょう。
いずれにせよ、早期の問題解決を望む場合は、刑事事件につよい弁護士へ早めに相談するのがおすすめです。
人身事故が原因の罰金刑や懲役刑を避けるための3つのポイント
人身事故を起こしたあと、罰金刑・懲役刑を避けるためのポイントを3つ紹介します。
1.被害者に対して謝罪し被害回復に向けた支援をする
日本の刑事裁判の有罪率は90%以上なので、罰金刑や懲役刑を避けるには、「刑事裁判にかけられないこと=起訴処分を下されないこと」が重要です。
検察官が担当事件に対して起訴処分を下すかどうかを決定するときには、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況などが総合的に考慮されます。
そのため、刑事訴追されたときにはできるだけ早いタイミングで被害者に対して謝罪をして、示談交渉の成立を目指すのが重要です。
たとえば、示談が成立して被害者の処罰感情が希薄になったことが明らかになれば、不起訴処分獲得の可能性が高まります。
また、被害に対する弁償が済んでいれば、仮に起訴されたとしても、当事者間で民事的解決が成立したことを理由に軽い刑事処分を期待できるでしょう。
2.捜査機関に対する取り調べなどには誠実に対応する
人身事故について警察・検察から取り調べを受けるときには、できるだけ誠実に対応することを強くおすすめします。
なぜなら、黙秘をしたり虚偽の供述をしたりすると、交通事故を起こしたことについて反省の態度がないと判断されて刑事処分が重くなる危険性が高まるからです。
また、黙秘や虚偽の供述をしたり、反省の態度を示さなかったりすると、「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と判断されて、逮捕・勾留されるリスクにも晒されます。
ただし、警察や検察から実施される取り調べにおいて、自分にとって不利な事実をわざわざ伝える必要はありません。
事情聴取には誠実に対応しつつも、軽い刑事処分を獲得できるような供述は意識するべきでしょう。
3.できる限り早い段階で弁護士に相談する
人身事故を起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
なぜなら、交通事故トラブルを得意とする弁護士の力を借りることで以下のメリットを得られるからです。
- 逮捕・勾留という身柄拘束処分を避けるための弁護活動を展開してくれる
- 起訴処分が避けられないケースでも、懲役刑を避けて、罰金刑・執行猶予付き判決獲得を目指した弁護活動を期待できる
- 捜査段階で実施される取り調べに向けたアドバイス(供述姿勢・供述内容など)をもらえる
- 人身事故の被害者との間で示談交渉をスタートして民事紛争の早期解決を目指してくれる
- 被害者側にも一定の過失割合が認められる事案では、加害者側に有利な過失割合条件での示談契約締結を目指してくれる
人身事故を起こしたときには、刑事責任だけではなく、民事責任や行政責任も負担しなければいけません。
民事責任については、相手方との示談交渉・民事訴訟によって解決を目指す必要があります。
加害者本人だけでは刑事責任・民事責任が重くなるリスクがある以上、交通事故事案を得意とする弁護士のノウハウを頼るべきでしょう。
さいごに|人身事故のことならベンナビ交通事故で弁護士を探そう
人身事故を起こしたときに問われる刑事責任については、以下2つのポイントを意識する必要があります。
- 不起訴処分を獲得して前科がつかないようにする
- 起訴処分を避けられないとしても、罰金刑や執行猶予付き判決獲得を目指して、懲役刑を避ける
これらの目標を達成するためには、交通事故を起こしたあとは、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。
ベンナビ交通事故では、人身事故を起こした加害者の弁護活動などを得意とする弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、この機会にぜひ信用できそうな弁護士までお問い合わせください。







