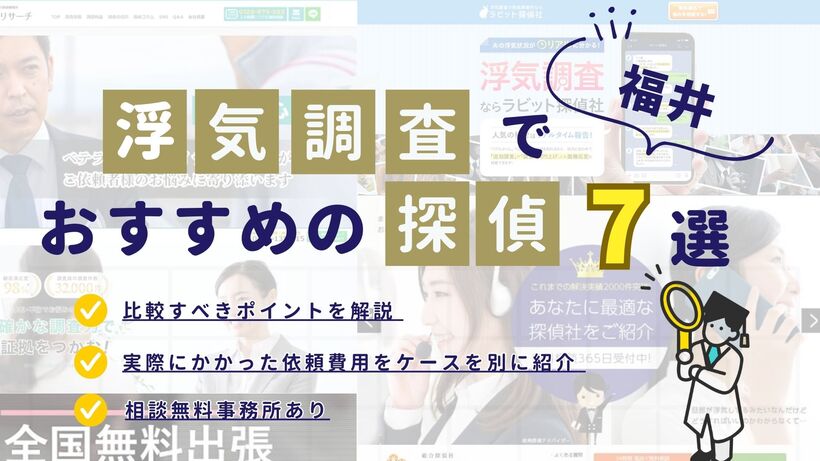子供に対する扶養義務は何歳まで続く?養育費の終期の決め方と4つの判断ポイント


離婚後に養育費などを支払っている方の中には、「いったい、子供への扶養義務は何歳まで続くのか?」といった疑問を抱える方は少なくありません。
特に、子供がすでに18歳や20歳を迎えている場合、「もう支払わなくていいのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、子供に対する扶養義務が発生する期間について、法律上の考え方や家庭裁判所の判断基準をもとにわかりやすく解説します。
さらに、離婚時に扶養義務の終期を決める方法や、現在も支払う必要があるかを見極める4つのポイントも紹介します。
養育費に関する正しい知識を身につけ、無用なトラブルを回避するための参考にしてください。
子供の扶養義務は何歳まで続く?一般的には「20歳」が目安となる
まずは子供の扶養義務が何歳まで続くのかについて、詳しく解説します。
1.年齢に関する一律の決まりは存在しない
民法では、親子間の扶養義務について定められていますが、「扶養義務は何歳まで続くか」という点について、明確に年齢上限を規定する条文は存在しません。
扶養の必要性は、形式的な年齢ではなく、子供が経済的・社会的に自立できる状態かどうかによって判断されます。
つまり、「18歳を超えたから」「成年に達したから」といった年齢的な区切りのみで、扶養義務の終了を一律に判断することはできません。
実際には、子供の生活状況や収入の有無、就学状況などを総合的に見て、親が引き続き扶養すべきかどうかが判断されます。
2.一般的には「20歳」を目安にすることが多い
実務上、離婚時に取り交わされる養育費の合意書や、公正証書、調停調書では、「子供が20歳に達したあとの最初の3月まで」といった文言で扶養の終期を設定するケースが多く見られます。
この「20歳」という区切りは、2022年の法改正前まで成年年齢とされていたことから、現在でも慣習的に使用されています。
また、家庭裁判所での判断においても、20歳を目安に扶養義務の終期が決定されることが一般的です。
ただし、大学や専門学校への進学が広く一般化している現代では、20歳を迎えても社会的・経済的に自立できていない子供は多く、実質的には「未成熟子」と評価されるケースも少なくありません。
3.実際は子供が未成熟子である間は扶養義務が生じる
扶養義務が続くかどうかの最終的な判断は、子供が自力で生計を立てられるかどうかにかかっています。
たとえば、高校卒業後すぐに就職し、安定した収入を得て自立している場合には、未成熟子とは見なされません。
一方で、大学や専門学校に通っており、学業が中心で十分な収入がない、あるいはアルバイトで生計を立てているといった場合は、引き続き未成熟子とされ、扶養義務が残ることになります。
とくに、就職活動中で無収入である、または進学中にやむを得ない事情で親の援助が必要な状況にある場合には、扶養の必要性が認められやすくなります。
このように、形式的な年齢だけでなく、進路や収入状況、生活実態をふまえて、扶養義務の有無は柔軟に判断されるのが実務の特徴です。
離婚時の子供に対する扶養義務を何歳までにするか決める3つの方法
離婚する際、子供への養育費を「いつまで支払うのか」は重要な取り決め事項のひとつです。
しかし、法律で明確な終期が定められているわけではないため、後々トラブルにならないよう、離婚時に終期を明確にしておくことが望ましいといえます。
養育費の終期は、以下の3つの方法で取り決めることが可能です。
- 協議
- 調停
- 訴訟
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
1.協議|両親で話し合って決める
養育費の終期を決める最も一般的な方法は、父母が協議によって終期を取り決めることです。
協議離婚の場合、養育費の金額や支払い期間について自由に話し合って合意することができます。
ただし、「成人するまで」や「自立するまで」などの曖昧な表現は、のちに解釈の違いによってトラブルになるおそれがあるので注意しましょう。
「子供が20歳に達した後の最初の3月まで」や「22歳に達する年度の3月末まで」など、終期を明確に記載しておくことが重要です。
合意内容を確実に履行させたい場合は、公正証書にしておくと、将来の強制執行も可能になります。
2.調停|裁判所の調停委員が仲介役となり決める
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用して終期を定めることが可能です。
調停では、裁判所が選任する調停委員が間に入り、父母双方の主張を調整したうえで合意を目指します。
調停調書には終期が明記されるため、合意内容に法的拘束力が生まれ、のちのトラブル回避にもつながるのがメリットです。
近年の調停実務では、子供の進学希望や家庭環境に応じて、22歳(大学卒業相当)までの支払いが妥当とされるケースも見られます。
3.訴訟|離婚裁判の中で養育費について取り決める
調停でも合意に至らなかった場合は、離婚訴訟のなかで裁判所が養育費の支払い終期を判断することになります。
訴訟では、子供の進学意向、家庭の経済状況、監護親の負担など、具体的な事情を総合的に考慮して判断が下されます。
たとえば、子供が大学に進学する蓋然性が高く、進学後も親の支援が必要であると認められれば、20歳を超えても扶養義務が続くとの判決が出ることも少なくありません。
このように、裁判所の判断は単なる年齢基準ではなく、子供の将来設計や両親の資力を踏まえて、扶養の必要性があるかどうかを見極めたうえで下されます。
現在も子供に対しての扶養義務を負うのか判断する際の4つのポイント
子供が18歳や20歳を超えたとしても、扶養義務がすぐに終了するとは限りません。
家庭裁判所や実務では、形式的な年齢よりも「未成熟子かどうか」が判断基準とされており、子供の生活状況によって扶養義務が継続する可能性があります。
ここでは、現在も扶養義務があるかどうかを見極めるための4つのチェックポイントを紹介します。
1.子供が働いているかどうか
扶養義務があるかどうかを判断する際、基本的な材料となるのが、子供が現在働いているかどうかです。
たとえば、高校を卒業して就職してフルタイムで働いている場合は、すでに自分の収入で生活を成り立たせていると見なされる事が多いです。
そのような状況であれば、経済的に自立していると評価され、親の扶養義務は終了すると判断される可能性が高いでしょう。
一方で、子供が大学や専門学校に通っており、学業が中心となっているケースでは、まだ十分な収入を得ることが難しく、経済的な自立は果たせていないとされるのが一般的です。
また、就職をしていない場合や、就職活動中で無収入の期間が続いている場合も、親の援助が必要であると考えられ、扶養義務が継続する根拠となります。
2.働いている場合は正社員かどうか
子供が就労している場合であっても、雇用形態によって、扶養義務の有無は変わってきます。
たとえば、正社員として継続的に雇用され、安定した収入を得ている場合には、社会的・経済的に自立したと見なされやすく、養育費の支払い義務は終了するとされることが多くあります。
しかし、アルバイトやパートタイム、または契約社員など、雇用の継続性や収入の安定性が乏しい働き方をしている場合は、まだ自立したとはいえないと判断されるケースも少なくありません。
とくに、収入が生活費をまかなうには不十分である場合や、親からの経済的支援がなければ学業や生活を維持できない状況であれば、引き続き未成熟子として扶養の対象になる可能性があります。
3.子供に持病や障害があるかどうか
子供が持病や障害を抱えているかどうかも、扶養義務を判断するうえで非常に重要な要素のひとつです。
たとえば、身体的または精神的な事情により就労が難しい、あるいは生活能力が十分でないと判断される場合には、年齢にかかわらず扶養が継続することになります。
医師の診断や就労支援の状況などを踏まえ、経済的な自立が困難とされる場合には、扶養義務が長期間続くことも珍しくありません。
ただし、病気や障害があったとしても、実際に働いて収入を得ており、生活が成り立っていると判断できる場合は、扶養義務が終了する可能性もあります。
あくまで「支援がどの程度必要か」に応じて、個別具体的に判断されるのが実務の基本です。
4.子供が結婚しているかどうか
子供が結婚しているかどうかも、扶養義務の有無を左右する重要なポイントになります。
結婚すると、法律上は配偶者と互いに扶養義務を負う関係になるため、原則として親の扶養義務は終了するものと考えられています。
これは、子供が経済的・社会的にひとり立ちしたと見なされるからです。
たとえ未成年であっても、結婚した場合には成人と同じように扱われ、家庭を築く主体として法的に認められるため、親がこれ以上養育費を支払う必要はないというのが一般的な考え方です。
さいごに|子供の扶養義務を何歳まで負うのかは個別に判断する必要がある
子供に対する扶養義務が何歳まで続くかは、年齢だけでは一概に判断できません。
たとえ18歳や20歳を迎えていたとしても、子供が「未成熟子」に該当する場合には、引き続き扶養義務を負うことになります。
進学や就職、結婚、健康状態など、さまざまな事情をふまえて個別に検討する必要があるため、実務でも柔軟な判断が求められます。
また、離婚時に養育費の終期を明確に決めていなかった場合は、あとになって「支払いを継続すべきか」「終了できるのか」といった悩みが生じることもあります。
こうしたケースでは、家庭裁判所で調停を申し立てたり、弁護士に相談して適切な対応を検討することが重要です。
親としての責任と生活の現実とのバランスをとるためにも、法的な視点をもとに冷静に状況を整理し、必要に応じて専門家の力を借りながら判断していくことをおすすめします。