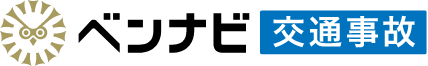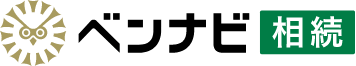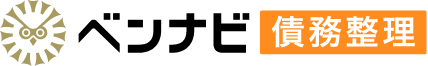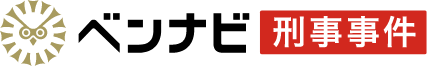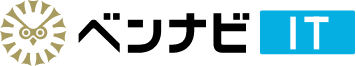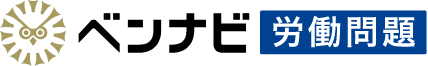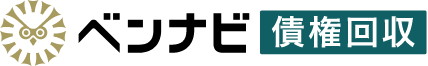【分野別】弁護士費用の相場はいくら?安く抑える方法・払えない場合の対処法を解説


- 「配偶者と離婚条件でもめている…」
- 「交通事故に遭ってけがをしたので、賠償金を請求したい」
- 「突然訴えられた!」
など、法律トラブルに巻き込まれて不安な思いをしている方もいるでしょう。
そのようなときに頼りになるのが弁護士です。
しかし、以下のように弁護士費用が不安で踏み出せないという方も多いでしょう。
- 「今すぐにでも弁護士に依頼したいけれど、費用はいくらかかるのだろう?」
- 「弁護士費用は高いって聞くし、自分では頼めないかも…」
現在では弁護士費用は自由化されており、見積もりを比較することで安い事務所が見つかることもありますし、事務所によっては分割払いや後払いに対応しているところもあります。
本記事では、分野別・依頼内容別の弁護士費用の相場や、弁護士費用を安く抑える方法、弁護士費用を払えない場合の対処法などを解説します。
弁護士費用の内訳
法律トラブルで弁護士に相談・依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
- 日当
- 実費
- その他費用 など
ここでは、各項目について解説します。
相談料|30分あたり5,000円程度
相談料とは、弁護士に法律相談する際にかかる費用です。
基本的にはタイムチャージ制となっており、相場は30分あたり5,000円程度ですが、相談内容や法律事務所によっては「初回相談無料」「何度でも相談無料」という場合もあります。
また、その場で弁護士に依頼して委任契約を締結した場合にも、無料としているところがほとんどです。
着手金|経済的利益の額などによって変動する
着手金とは、弁護士に問題解決を依頼する際に支払う費用です。
これは弁護士が業務にあたることに対して支払う「ファイトマネー」のようなものであり、依頼結果がどうであれ返金はされません。
着手金の金額は相手への請求金額などに応じて決められますが、法律事務所によっては着手金0円の完全成功報酬制を採用しているところもあります。
また、一般的に着手金は業務の段階が変わるごとに発生するものです。
たとえば、交渉段階から依頼したものの解決せずに訴訟へ移行する場合、基本的には交渉依頼時だけでなく訴訟移行時にも着手金がかかります。
報酬金(成功報酬)|経済的利益の額によって変動する
報酬金とは、弁護士に依頼して問題解決できた場合に支払う費用です。
報酬金の金額は、依頼者が得た経済的利益の額に応じて決まります。
弁護士に依頼して依頼者が望んだ結果を得られた場合はもちろん、一部勝訴や和解などで依頼者の請求する全額の獲得はできなかったものの、いくらかの利益を得られた場合でも請求されます。
一方、全面敗訴したり交渉が決裂したりするなど、まったく利益を得られなかった場合は請求されません。
日当|半日3万円~5万円程度、1日5万円~10万円程度
日当とは、弁護士が事務所以外で業務にあたった際に支払う費用です。
たとえば、弁護士が案件対応のために裁判所に出向いた場合や、交渉先に赴いた場合などに発生します。
日当の相場は拘束時間によって異なり、一般的には半日で3万円~5万円程度、1日で5万円~10万円程度で、事件終了後にまとめて請求されることが多いです。
なお、法律事務所によっては、遠方に出張するようなケースでない限り日当が発生しないことなどもあり、詳しくは依頼する際に確認しておくとよいでしょう。
実費|依頼内容によって変動する
実費とは、弁護士が依頼を遂行する際に実際にかかった費用のことです。
たとえば、交通費・通信費・鑑定料などがあり、基本的には一定の金額を最初に「預り金」という形で預かり、事件終了時に成功報酬とまとめて精算します。
その他費用|手数料など
事件の種類によっては、着手金や報酬金ではなく「手数料」として請求されることもあります。
契約書作成・遺言書作成・遺言執行などのような、トラブル対応ではなく単なる事務手続きだけを依頼するようなケースでは、手数料が請求される可能性があります。
【分野別】弁護士費用の相場
弁護士費用の相場を分野ごとにまとめると、以下のとおりです。
ただし、「どの手続きを依頼するのか」「弁護士の介入によっていくら獲得できたのか」などによっても金額は大きく変動するため、あくまでも参考程度にご覧ください。
| 分野 | 相場 |
|---|---|
| 離婚問題 | 100万円~170万円程度 |
| 遺産相続 | 10万円~100万円程度 |
| 債務整理 | 20万円~100万円程度 |
| 交通事故 | 102万円程度 |
| 刑事事件 | 60万円~100万円程度 |
| 労働問題 | 5万円~130万円程度 |
| インターネットトラブル | 10万円~100万円程度 |
| 債権回収 | 50万円~130万円程度 |
| 企業法務 | 3万円~2,000万円程度 |
| 不動産トラブル | 60万円~120万円程度 |
| 医療過誤 | 120万円~200万円程度 |
| 消費者トラブル | 60万円~110万円程度 |
※経済的利益を500万円と仮定して計算
なお、かつて弁護士費用には、日本弁護士連合会が定める「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という基準がありましたが、2004年4月に廃止されています。
現在では弁護士費用は自由化されており、事務所によっても金額にはバラつきがあります。
以下では分野別・依頼内容別の費用の目安を紹介しますが、正確な金額を知りたい方は直接事務所にご確認ください。
離婚問題の弁護士費用の相場
離婚問題の場合、協議離婚・離婚調停・離婚裁判などの解決方法があります。
これらのうちどれを依頼するのかによって、以下のように金額が異なります。
協議離婚
- 着手金:20万円~30万円程度
- 報酬金:30~40万円程度+経済的利益の10%~20%程度
協議離婚とは、裁判所を利用せずに夫婦同士で直接話し合って離婚する手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として相手との話し合いを進めてくれます。
たとえば「弁護士に協議離婚を依頼して慰謝料200万円を獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は70万円~100万円程度になるでしょう。
離婚調停
- 着手金:30万円~40万円程度
- 報酬金:30万円~40万円程度+経済的利益の10%~20%
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員が仲介して離婚に向けた話し合いを行う手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として調停に出席し、調停委員による聞き取りなどに対応してくれます。
離婚調停を依頼した場合、弁護士費用の総額は60万円~80万円程度(+経済的利益の10~20%)になるでしょう。
離婚裁判
- 着手金:30万円~50万円程度
- 報酬金:30万円~60万円程度+経済的利益の10%~20%
離婚裁判とは、家庭裁判所で主張立証を行って、最終的には裁判官の判決によって離婚成立を目指す手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として裁判所での主張立証などに対応してくれます。
離婚裁判を依頼した場合、弁護士費用の総額は60万円~110万円程度(+経済的利益の10%~20%)になるでしょう。
遺産相続の弁護士費用の相場
遺産相続の場合、どの相続手続きを依頼するのかによって弁護士費用が異なります。
主な相続手続きとしては、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・遺言書作成・遺言執行・相続放棄などがあり、それぞれの費用相場は以下のとおりです。
遺産分割協議にかかる弁護士費用
| 獲得金額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 獲得金額の8% | 獲得金額の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 獲得金額の5%+9万円 | 獲得金額の10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 獲得金額の3%+69万円 | 獲得金額の6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 獲得金額の2%+369万円 | 獲得金額の4%+738万円 |
遺産分割協議でかかる弁護士費用は、上記のとおり相続での獲得金額(着手金の場合は、取得を希望する金額)によって異なります。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人としてほかの相続人とのやり取りを進めてくれます。
たとえば「弁護士に遺産分割協議を依頼して500万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は102万円程度になるでしょう。
遺留分侵害額請求
| 獲得金額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 獲得金額の8% | 獲得金額の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 獲得金額の5%+9万円 | 獲得金額の10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 獲得金額の3%+69万円 | 獲得金額の6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 獲得金額の2%+369万円 | 獲得金額の4%+738万円 |
遺留分侵害額請求でかかる弁護士費用は、上記のとおり獲得金額(着手金の場合は、取得を希望する金額)によって異なります。また、ご依頼される手続の内容によっても費用は異なります。
遺留分とは、相続の際に法定相続人(兄弟姉妹、甥・姪は除く)が最低限受け取れる取り分のことです。
実際の取り分が遺留分よりも少ない場合は、遺産を多く受け取っている相続人に対して不足分を請求できます。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人としてほかの相続人とのやり取りを進めてくれます。
遺言書作成
- 手数料:10万円~20万円程度
弁護士なら遺言書作成を依頼でき、代理人として必要な手続きを一任できます。
ただし、遺言内容が複雑なケースや相続財産の種類が多いケースなどでは、上記の範囲内に収まらないこともあります。
遺言執行
- 手数料:30万円~
遺言執行とは、被相続人の遺言内容を実現するために必要な手続きを行うことを指します。
遺言執行者には、親族や相続人だけでなく弁護士を指定することも可能です。
相続放棄
- 手数料:10万円程度
相続放棄は相続方法のひとつで、ほかには単純承認や限定承認などがあります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない方法
限定承認や相続放棄を行うには期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に必要書類を準備して家庭裁判所に提出しなければいけません。
弁護士なら、相続放棄のために必要な手続きを一任することができます。
債務整理の弁護士費用の相場
債務整理の場合、どの手続きを依頼するのかによって弁護士費用が異なります。
主な手続きとしては、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求などがあり、それぞれの費用相場は以下のとおりです。
任意整理
- 着手金:1社あたり2万円~3万円程度
- 報酬金:1社あたり2万円~3万円程度+減額報酬10%~15%
任意整理とは、債権者と直接交渉して、将来利息のカットや返済スケジュールの変更などをしてもらう手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として債権者との交渉を進めてくれます。
たとえば「弁護士に任意整理を依頼して債権者1社からの借金を100万円減額できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は14万円~21万円程度になるでしょう。
個人再生
- 着手金:30万円~50万円程度
- 報酬金:10万円~20万円程度
個人再生とは、裁判所を介して借金の元本をその金額に応じて最大90%減額してもらい、残りの元本を分割して3~5年で返済する手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として申立書や再生計画案などの必要書類を作成してくれて、書類提出後の裁判官との面談などにも対応してくれます。
個人再生を依頼した場合、弁護士費用の総額は40万円~70万円程度になるでしょう。
自己破産
- 着手金:20万円~50万円程度
- 報酬金:0円~30万円程度
自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務(一部の対象外の債務を除く)を免除してもらう手続きのことです。
財産の有無や借金の理由等により、同時廃止事件、少額管財事件、管財事件にわかれており、手続の種類により費用は異なります。
弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として必要書類を作成してくれて、書類提出後の裁判官や管財人との面談などにも対応してくれます。
自己破産を依頼した場合、弁護士費用の総額は20万円~80万円程度になるでしょう。
過払い金請求
- 着手金:1社あたり2万円程度
- 報酬金:獲得金額の20%~25%程度
過払い金請求とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対して、利息制限法の上限を超えて支払っていた利息を返還するように求める手続きのことです。
弁護士に依頼すれば、取引履歴を取得して正確な過払い金を算出して、貸金業者に対して交渉や裁判などの手段で請求してくれます。
たとえば「弁護士に過払い金請求を依頼して貸金業者2社から総額200万円取り戻せた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は44万円~54万円程度になるでしょう。
交通事故の弁護士費用の相場
| 獲得金額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 獲得金額の8% | 獲得金額の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 獲得金額の5%+9万円 | 獲得金額の10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 獲得金額の3%+69万円 | 獲得金額の6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 獲得金額の2%+369万円 | 獲得金額の4%+738万円 |
交通事故の損害賠償請求でかかる弁護士費用は、上記のとおり獲得金額(着手金の場合は、取得を希望する金額)によって異なります。
弁護士に依頼すれば、加害者や加害者側の任意保険会社との示談交渉や裁判などの手続きを一任することができます。
たとえば「弁護士に損害賠償請求を依頼して500万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は102万円程度になるでしょう。
詳しくは「弁護士費用が払えない場合の対処法」で後述しますが、交通事故トラブルでは自動車保険の弁護士費用特約を利用することで自己負担が0円で済むケースもあります。
刑事事件の弁護士費用の相場
- 着手金:30万円~50万円程度
- 報酬金:30万円~50万円程度
- 接見費用:1回あたり2万円~5万円程度
- 身柄解放手続の着手金:10~20万円程度
- 身柄解放手続の報酬金:10~20万円程度
- 示談交渉の報酬金:10万円程度
弁護士に依頼すれば、自首の同行・被害者との示談交渉・捜査機関に対する働きかけなどのサポートをしてくれて、早期釈放や不起訴処分の獲得などが望めます。
たとえば、「逮捕段階で依頼をして不起訴で終わることができた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は60万円~150万円程度になるでしょう。
なお、刑事事件を起こした際に呼べる弁護士は以下の3種類おり、当番弁護士や国選弁護人に関して基本的に弁護士費用は無料です。
| 当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 | |
|---|---|---|---|
| 弁護士費用 | 無料 | 原則無料 | 有料 |
| 呼べるタイミング | 逮捕後 | 勾留後・起訴後 | いつでも可 |
| 依頼できる人 | 被疑者本人・家族・友人など | 被疑者本人・被告人本人 | 被疑者本人・家族・友人など |
| メリット | ・弁護士費用が無料 | ・資力が一定以下であれば無料で利用できる ・費用負担が発生した場合も低額で済む |
・自分で弁護士を自由に選択できる ・逮捕前でもサポートが受けられる |
| デメリット | ・自分で弁護士を選べない ・1度の接見しか利用できない |
・自分で弁護士を選べない ・選任できるタイミングが遅い |
・弁護士費用が高額になりやすい |
労働問題の弁護士費用の相場
労働問題の場合、どのようなトラブルで悩んでいるのかによって弁護士費用が異なります。
主なトラブルとしては、給料未払い・残業代請求・不当解雇・労働災害・ハラスメント・退職代行などがあり、それぞれの費用相場は以下のとおりです。
給料未払い・残業代請求
- 着手金:20万円~30万円程度
- 報酬金:獲得金額の20%程度
弁護士に給料未払い・残業代請求を依頼すれば、いくら未払いになっているのか正確な金額を計算してくれて、会社に対して書面送付や直接交渉などの手段で請求してくれます。
もし書面送付や直接交渉でも解決が難しい場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行して請求してもらうことも可能です。
たとえば「弁護士に未払い給料の請求を依頼して労働審判などに移行せずに300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は80万円~90万円程度になるでしょう。
不当解雇
- 着手金:30万円程度
- 報酬金:獲得金額の10~15%程度(固定料金の場合は20万円~30万円程度)
弁護士に不当解雇トラブルの対応を依頼する場合、復職を望んでいるのであれば解雇無効請求、そのまま退職するのであれば損害賠償請求などを進めてくれます。
たとえば「弁護士に不当解雇のトラブル対応を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は60万円~75万円程度、報酬金が固定の場合は50万円~60万円程度になるでしょう。
労働災害
- 着手金:10万円~30万円程度
- 報酬金:獲得金額の10%~15%程度(固定料金の場合は20万円~30万円程度)
労働災害の被害に遭った場合、弁護士に依頼することで労災の申請手続きをサポートしてくれたり、被害状況によっては会社に対して損害賠償請求してもらうことも可能です。
たとえば「弁護士に労働災害の対応を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は40万円~75万円程度、報酬金が固定の場合は30万円~60万円程度になるでしょう。
ハラスメント
- 着手金:10万円~20万円程度
- 報酬金:獲得金額の10%~15%程度
パワハラやセクハラなどのハラスメント被害に遭った場合、弁護士に依頼すればハラスメント差止要求書の提出や損害賠償請求などの対応を代行してくれます。
また、ハラスメントの被害状況によっては刑事告訴が可能な場合もあります。
たとえば「弁護士にセクハラ被害の対応を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は40万円~65万円程度になるでしょう。
退職代行
- 着手金:5万円~6万円程度
- 成功報酬:なし ※別途依頼内容に応じて発生
弁護士に退職代行を依頼すれば、退職したいという旨を代わりに勤務先に伝えてくれるだけでなく、退職金請求や有給消化などの退職条件について交渉してもらうことも可能です。
インターネットトラブルの弁護士費用の相場
インターネットトラブルの場合、どの手続きを依頼するのかによって弁護士費用が異なります。
主な手続きとしては、インターネット上の投稿の削除請求・加害者の身元特定・損害賠償請求などがあり、それぞれの費用相場は以下のとおりです。
投稿の削除請求
- 着手金:5万円~20万円程度
- 報酬金:5万円~15万円程度
インターネット掲示板やSNSなどで権利侵害するような投稿がされた場合、弁護士に依頼すれば管理者・運営者に対して任意で削除を求めたり、裁判上の手続きで削除を求めたりしてくれます。
インターネット上の投稿削除を依頼した場合、弁護士費用の総額は10万円~35万円程度になるでしょう。
加害者の身元特定(発信者情報開示請求)
- 着手金:20万円~30万円程度
- 報酬金:15万円~20万円程度
インターネット上で権利を侵害した投稿者の身元を特定したい場合、弁護士に依頼すれば管理者やプロバイダに対して任意で情報開示を求めたり、裁判上の手続きで情報開示を求めたりしてくれます。
加害者の身元特定を依頼した場合、弁護士費用の総額は35万円~50万円程度になるでしょう。
損害賠償請求(交渉・民事訴訟)
- 着手金:10万円~20万円程度
- 報酬金:獲得金額の16%程度
権利を侵害した投稿者の身元を特定できた場合、弁護士に依頼すれば交渉や裁判などの手段で投稿者に対して損害賠償請求してくれます。
たとえば「弁護士に損害賠償請求を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は58万円~68万円程度になるでしょう。
債権回収の弁護士費用の相場
- 着手金:10万円~30万円程度 ※回収方法や債権額によって変動する
- 成功報酬:獲得金額の10%~20%程度
債権回収の場合、着手金に関しては「回収方法ごとに料金設定している法律事務所」もあれば「債権額ごとに料金設定している法律事務所」もあります。
まず、回収方法ごとに料金設定している場合の相場は以下のとおりです。
| 回収方法 | 着手金相場 |
|---|---|
| 内容証明郵便 | 1万円~5万円程度 |
| 支払督促 | 3万円~20万円程度 |
| 民事調停・交渉 | 10万円~20万円程度 |
| 訴訟 | 10万円~30万円程度 |
| 強制執行 | 5万円~20万円程度 |
この場合、たとえば「弁護士に交渉を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は40万円~80万円程度になるでしょう。
次に、債権額ごとに料金設定している場合の相場は以下のとおりです。
| 債権額 | 着手金相場 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10万円程度、または請求額の10%程度 |
| 100万円を超え500万円以下 | 15万円~30万円程度、または請求額の8%程度 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 30万円~50万円程度、または請求額の6%程度 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 50万円~100万円程度、または請求額の4%程度 |
| 3,000万円を超える場合 | 100万円以上、または請求額の2%~3%程度 |
この場合、たとえば「弁護士に債権回収を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は45万円~90万円程度になるでしょう。
企業法務の弁護士費用の相場
企業法務の場合、どの手続きを依頼するのかによって弁護士費用が異なります。
主な依頼内容としては、顧問契約・会社設立・事業承継・M&A・破産手続き(法人破産)・事業再生などがあり、それぞれまとめると以下のとおりです。
| 依頼内容 | 相場 |
|---|---|
| 顧問契約 | タイムチャージ制:1時間あたり3万円~5万円程度 月額制:1ヵ月あたり3万円~30万円程度 |
| 会社設立 | 手数料:10万円程度 |
| 事業承継 | 着手金:15万円以上 報酬金:獲得金額の10%程度 |
| M&A | 契約書の作成・確認:50万円以上 デューデリジェンス:50万円以上 |
| 破産手続(法人破産) | 着手金:54万円以上 報酬金:50万円程度 |
| 事業再生 | 着手金:240万円以上 報酬金:着手金の2倍程度 |
不動産トラブルの弁護士費用の相場
- 着手金:10万円~20万円程度
- 報酬金:獲得金額の10%~20%程度
不動産トラブルの場合、弁護士に依頼すれば代理人として契約内容を確認してくれたり、オーナー・入居者との交渉などを進めてくれます。
たとえば「弁護士に不動産トラブルの対応を依頼して300万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は40万円~80万円程度になるでしょう。
医療過誤の弁護士費用の相場
- 着手金:70万円~100万円程度 ※医療調査、証拠保全、示談交渉等依頼内容により異なる
- 報酬金:獲得金額の10%~20%程度
医療過誤の場合、弁護士に依頼すれば代理人として証拠収集や過失の有無などを調べてくれて、医療過誤が認められる場合は交渉や裁判などの手段で損害賠償請求してくれます。
たとえば「弁護士に医療調査や証拠保全を含めた損害賠償請求を依頼して500万円獲得できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は120万円~200万円程度になるでしょう。
消費者トラブルの弁護士費用の相場
- 着手金:10万円以上
- 報酬金:回収金額の10~20%程度
消費者トラブルの場合、弁護士に依頼すれば内容証明郵便・交渉・裁判などの手段で、クーリングオフ・契約解除・返金などを求めてくれます。
たとえば「弁護士に返金請求を依頼して100万円回収できた」というようなケースでは、弁護士費用の総額は20万円~30万円程度になるでしょう。
弁護士費用を安く抑える方法
できるだけ弁護士費用を安く抑えたい場合は、以下のような対応を検討しましょう。
できるだけ早期に弁護士に依頼する
できるだけ早い段階で弁護士に依頼することで、弁護士費用の負担軽減につながります。
依頼するタイミングが遅れると、すでに争いが複雑化してしまっていて交渉では解決できず、裁判手続きに移行せざるを得ない場合もあります。
段階が変われば再度着手金が必要になることもありますし、事件の難易度が上がって弁護士の要する手間が増えれば報酬金も高くなります。
弁護士費用を安く抑えたいなら、早期に弁護士へ依頼するのが賢明です。
無料相談を活用して費用の安い事務所を探す
弁護士費用は法律事務所によっても異なるため、できるだけ安い金額で応じてくれるところを探すのも有効です。
初回相談無料の法律事務所に絞ってそれぞれ見積もりを出してもらい、どの事務所が安いのか比較検討するとよいでしょう。
ただし、費用の安さだけを見て依頼先を選んでしまうと、弁護士との相性が合わなかったりして思うように動いてもらえずに不満の残る結果になるおそれがあります。
弁護士を探す際は、「信頼できる弁護士かどうか」「自分と相性が合うかどうか」なども確認しておくことが大切です。
弁護士保険に加入しておく
まだ法律トラブルに巻き込まれていない場合は、弁護士保険に加入しておけば、いざという時に弁護士費用を補償してもらえるのでおすすめです。
法人や個人事業主だけでなく一般の方でも利用できますし、自分が被害者の場合だけでなく加害者になってしまった場合も利用できるなど、幅広くサポートしてくれます。
弁護士費用が払えない場合の対処法
なかには「弁護士に依頼したいけど、弁護士費用を支払う余裕がない」という方もいるでしょう。
弁護士費用の支払いが困難な場合、以下のような対処法があります。
相談料無料の法律事務所を活用する
現在では初回相談無料の法律事務所も多く、うまく活用すれば簡単なトラブルなら費用をかけずに解決できる可能性があります。
ただし、無料法律相談では相談時間が30分程度に限られているため、事前に相談内容に関する資料を用意して質問事項をメモにまとめるなどの準備を整えておくことが大切です。
また、弁護士なら「内容証明郵便の送付のみ」「文書作成のみ」など、断片的な依頼も可能です。
断片的な依頼であれば事件解決を丸ごと依頼するよりも費用を安く抑えられるため、できるだけ費用を抑えたい場合は検討してみるのもよいでしょう。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
法テラスとは、法律問題の解決をサポートする公的機関のことです。
法テラスでは、経済的事情で弁護士に依頼できない方を対象に「民事法律扶助制度」を実施しています。
法テラスが定める利用条件を満たしていれば、弁護士との無料法律相談や弁護士費用の立替制度などが利用できます。
なお、弁護士費用の立替制度を利用する場合、あとから分割で法テラスに返還する必要がありますが、その返還額は月5,000円程度と無理のない範囲に調整してもらうことが可能です。
民事法律扶助制度の利用条件や利用の流れなどは「無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス」をご確認ください。
分割払い・後払い可能な法律事務所に依頼する
弁護士費用は原則一括払いですが、法律事務所によっては分割払いや後払いに対応しているところもあります。
法律事務所が対応しているかどうかは事務所ホームページで確認できますが、特に記載がない場合でも直接相談すれば対応してくれるケースも多くあるため、気になる弁護士が見つかった際は一度相談してみましょう。
弁護士費用特約が利用できないか確認する(交通事故の場合)
弁護士費用特約は自動車保険のオプションのひとつで、交通事故でかかる弁護士費用を保険会社が一定額まで負担してくれるというものです。
保険会社によっても補償内容は異なりますが、法律相談料は最大10万円、弁護士費用は最大300万円まで補償してくれるのが一般的です。
なお、自分が加入していなくても配偶者や同居親族が加入していれば利用できるケースもあるため、交通事故に遭った際は周囲の契約状況もあわせて確認しておくことをおすすめします。
弁護士費用に関するよくある質問
ここでは、弁護士費用に関するよくある質問について解説します。
弁護士費用は誰が払う?相手方に請求できますか?
基本的に弁護士費用は依頼者本人が支払うものであり、相手方へ請求することはできません。
ただし例外として、交通事故などの相手方の不法行為によって損害賠償請求をおこなう場合には弁護士費用の一部だけ相手方に請求することが可能です。
しかし、その相場は「認められる賠償金の1割程度」であるため、全額の請求は困難です。
追加で弁護士費用を請求されることはありますか?
事件の段階が変われば、追加で着手金を請求される可能性があります。
たとえば「交渉段階から依頼したものの解決せず、訴訟に発展してしまった」という場合は、交渉依頼時だけでなく、訴訟に移行する際も着手金が発生します。
それ以外にも「当初の想定よりも事件の難易度が高く、弁護士側の負担が大きい」というようなケースでは、見積もり時よりも報酬金が高くなる可能性があります。
弁護士費用はなぜこんなに高いのですか?
弁護士費用が決して安くない理由は、弁護士業務の性質にあります。
ひとつは、事件を請け負ってから解決までには、どうしてもある程度の時間がかかることです。
どんなに短くても数ヵ月、長い場合では数年かかることもあり、解決までに時間がかかるぶん報酬を低くすることは難しいのです。
また、弁護士業務は二つとして同じ内容のものはありません。
たとえ同種の事件でも、人間同士のトラブルである限り「全てが同じ」ということがないためにマニュアル化できず、必然的に労力を要します。
さらに、依頼者の人生を左右する問題であることも多いため、いい加減な対処はできません。
そのため、弁護士がひとつひとつの案件に取り組む労力は相当なものであり、そのぶん費用がどうしても高くなる傾向があります。
「経済的利益」とは何のことですか?
経済的利益とは、トラブル解決時に依頼者が得られる利益のことです。
自分が請求側の場合は、相手方から支払われた金額が経済的利益となります。
一方、自分が請求を受ける側の場合は、当初相手方から請求されていた金額から減額できた分が経済的利益に相当します。
さいごに|法律トラブルで悩んでいるなら、まずはベンナビで無料相談を
弁護士に法律問題の解決を依頼する場合、相談料・着手金・報酬金・実費・日当などの費用がかかります。
弁護士費用は事務所によっても差があるため、あくまでも本記事で紹介した費用相場は参考程度に留めて、正確な金額を知りたい方は事務所に直接確認してください。
当社が運営する「ベンナビ」では、各分野に強い全国の法律事務所を掲載しています。
初回相談無料・着手金0円・後払い可能・分割払い可能などの事務所も掲載しており、お住まいの地域を選ぶだけで対応可能な法律事務所を一括検索できます。
依頼せずに法律相談だけの利用も可能ですので、まずは一度利用してみることをおすすめします。