バック事故の過失割合は?ぶつけられたときの過失割合の考え方を解説

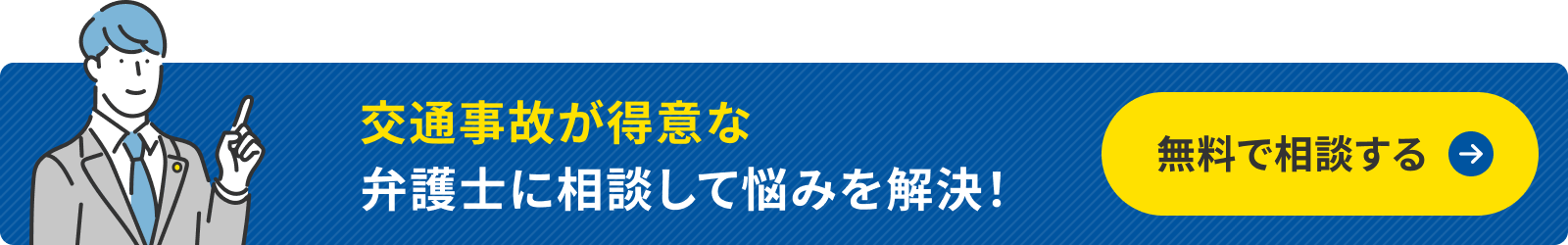

「バック事故」の被害に遭った場合、完全に相手の過失にできるか、はたまた自分にも責任を問われるかは気になるところです。
本記事では、バック事故の過失割合や加害者に請求できる金額などについて解説します。
原則として、後方不注意としてぶつかった側の過失が大きい傾向にありますが、ぶつけられた側に責任が問われる可能性もゼロではありません。
ぶつけられた側の責任が問われる、揉めてしまう場合についても紹介するため、自分は該当しないかを確認してみてください。
なお、当事者同士で解決できない場合は交通事故問題を得意とする弁護士への相談をおすすめします。
バックしてきた車にぶつけられた!過失割合はどれくらい?
そもそもバック事故とは、車両が後退中の後方不注意によって車両や人、物に衝突する事故のことをいい、「逆突事故」と呼ばれることもあります。
バックしてきた車にぶつけられるパターンは、大きくわけて3つあります。
それぞれの状況における割合は次のとおりです。
|
自分の車 |
相手の車 |
過失割合 |
|
停車中 |
バックしてきた |
自分0:相手100 |
|
徐行中 |
バックしてきた |
自分0~30:相手70~100 |
|
公道を進行中 |
わき道からバックしてきた |
自分20:相手80 |
停車中に相手の車がバックしてきたケース
原則として、停車中の車にぶつかった場合は、ぶつけた側が過失100となります。
交通事故では、バック事故に限らず、停車中の車両に対する過失割合は0と考えられています。
徐行中に相手の車がバックしてきたケース
いわゆる逆突事故の場合、自分は0~30程度、相手が70~100の過失となる可能性があります。
特に、相手の車がバックしてくると予測できたのにかかわらず直進してきた場合は、自分の過失が大きくなる傾向にあります。
公道を直進中に相手が脇道からバックで出てきたケース
公道を直進中に相手が脇道から出てきてバックでぶつかった場合、過失は自分20、相手80程度となります。
駐車場内での事故とは異なり、スピードを出して直進していることから、事故の被害も大きくなります。
加えて、けがの程度が大きくなるにつれ、相手に対して請求できる慰謝料なども高額になりやすいと考えられます。
バック事故では基本的にバックした車の過失割合が大きくなる
基本的に、バック事故は追突事故と同様にぶつけてきた側の責任が大きくなります。
過失割合はパターンによって異なりますが、特にぶつけられた側が避けられないときにはぶつけた側の過失は大きくなるでしょう。
このとき、バックしてきた車の後方確認不足が事故の原因と認められるかどうかがポイントとなります。
バック事故でぶつけられた側の過失割合が増えるケース
基本的にバック事故はぶつかってきた車の過失となりますが、ぶつけられた側の対応・状況によって過失割合は変わります。
ここでは、ぶつけられた側の過失割合が増える2つのケースについて解説します。
クラクションを鳴らさなかった場合
バックで近づいてくる車に気付いたとき、クラクションを鳴らして警告しているかどうかは過失割合で争うポイントです。
相手の車が近づいてきてクラクションを鳴らす余裕があったにもかかわらず警告しなかった場合は、ぶつけられた側の責任も大きくなります。
何も対処する間もなくぶつかられた場合は自分に責任はないとみなされますが、ぶつかった側はクラクションを鳴らす余裕があったと主張してくるかもしれません。
万が一、口論に発展して収拾がつかない場合はドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などをチェックする、もしくは弁護士への相談をおすすめします。
不適切な位置に駐車・停車していた場合
いきなりバックでぶつけられたといっても、ぶつけられた車が駐車禁止エリアや、わき道から出てくる車を妨害する場所に停車していた場合は、ぶつけられた側にも過失があるとみなされます。
不適切な位置に駐車・停車していた場合は、ぶつけられた側にも10~20程度の過失割合が加算されることがあります。
バック事故の過失割合で揉めるケース4つ
バック事故の過失割合は事故のパターンによっておおよそ決められていますが、自分と相手の主張によってはスムーズに過失割合が決まらないケースもあります。
ここでは、バック事故の過失割合で揉める4つのケースを解説します。
事故の状況について嘘をつかれる
ぶつかってきた側は少しでも有利になるよう、事故の状況について嘘をつく可能性があります。
たとえば、自分は停車していたにもかかわらずスピードを出していたと主張されたり、クラクションを鳴らすタイミングが遅いなど必要以上の過失を主張されたりした場合は、正しいかどうかを確かめるまでに時間を要します。
加害者・被害者それぞれの説明が異なるのは、バック事故では珍しいことではありません。
お互いが主張を曲げず話が進まない場合は、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など客観的なデータで事実を確認してください。
なお、証拠がない、何が証拠になるかわからない場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
クラクションが聞こえなかった、車が見えなかったと言い訳をされる
自分の過失を下げるため、バック事故に対して言い訳をすることは珍しくありません。
代表的な言い訳としては、「クラクションが聞こえなかった」「相手の車が見えなかった」などが挙げられます。
しかし、「クラクションが聞こえない」「相手の車が見えない」という言い訳がそもそも嘘である可能性がある、かつ本当でも判断基準が左右されることはありません。
相手が言い訳をして話し合いが進まない場合は、弁護士に相談して対処することをおすすめします。
よけないほうが悪いと言われる
ぶつけられた側に対して前方不注意を指摘し、自身の責任を逃れようとするケースもあります。
加害者側がぶつけられた側の前方不注意を主張してきた場合、反論する際は次に挙げる点を意識してください。
- 前方車がバックしてくる可能性を考慮して徐行運転をしていた
- 前方車がバックしてくることに気付き、ブレーキ・クラクションなど事故回避のアクションをとった
- 前方車が死角にあり、注意しても気付けない状況だった
- バックしてくる車を回避できない状況だった
ご自身の反論に相手が納得しない場合は、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など客観的なデータを用意しましょう。
具体的にどのようなものが証拠になり得るかわからない場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
保険会社の過失割合に納得できない
バック事故の過失割合を加害者側の保険会社が決めた場合、その結果に納得できないケースも大いに考えられます。
加害者側の保険会社の中には、「被害者も前方不注意だった」などといった、事実とは異なる主張をして過失割合を下げてこようとする可能性も否定できません。
仮に保険会社が提示した金額で安易に示談すると、本来受け取れる金額よりも安く済まされ、ぶつけられた側が損をしてしまいかねません。
自分で保険会社を相手に過失割合の交渉をするのは容易ではないうえ、時間も労力もかかってしまいます。
そのため、自分で対応せず交通事故問題を得意とする弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば、被害者にとって有利になる証拠を集めてくれたり、過去の裁判例や専門知識などをもとに正式な割合を算出してくれたりします。
バック事故で加害者に請求できるお金
バック事故で加害者に請求できるものには、主に次の4種類が挙げられます。
本来受け取れるお金をもれなく請求できるよう、あらかじめ把握しておきましょう。
慰謝料|事故のせいでけがをした場合
交通事故における慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
なお、交通事故の慰謝料には3種類あり、それぞれの相場は次のとおりです。
- 入通院慰謝料:28万円~116万円(重症の場合で通院1ヶ月~6ヶ月の場合)
- 後遺傷害慰謝料:110万円~2,800万円
- 死亡慰謝料:2,000~2,800万円
慰謝料の算出は被害者の世帯状況・収入・被害の度合など、さまざまな要素を組み合わせるため計算は複雑になります。
また、慰謝料について相場は自賠責基準と弁護士基準で異なり、弁護士基準のほうが高い傾向にあります。
弁護士は個々のケースに応じて適切な慰謝料額を算出してくれるため、自賠責基準での金額に納得できない場合は相談しましょう。
積極損害|事故のせいで発生した出費
積極損害とは事故による出費全般を指します。
たとえば、次に挙げるものが該当します。
- 入院費・通院費・病院までの交通費
- 事故によって介護状態になった場合の介護費用
- ぶつかられて壊れた車の修理代や買い替え費用
- 付添人に対する人件費
- 事故のせいで歩けなくなった場合の代替費用(タクシー代など)
- 被害者が亡くなった場合の葬儀費用
積極損害を請求する際は、請求書や領収書などが必要となる点に注意してください。
また、原則として治療費は保険範囲内が請求対象となり、特別室料や差額ベッド料などは普通病室が空いていない、あるいは医師からの指示があった場合に限り認められます。
一方、事故によって減った収入の補填や休業補填など、本来得るはずだった将来の利益の損失を埋め合わせるお金を消極損害といいます。
休業損害|事故が原因で仕事を休んだ場合
休業損害とは、事故の治療や入院などによって仕事ができずに失った収入のことです。
休業損害は被害者の収入や休んだ日数によって計算されるため、一概に決まった金額を算出することはできません。
なお、休業損害の計算方法は休業日数×基礎収入(1日分の収入)が基本です。
基礎収入の日額は、原則として国が最低限の基準を6,100円と定めています。
ただ、弁護士基準(相場である過去の判例に基づく基準)に沿って「事故前の収入から算出した日額」を用いることもできます。
ただし、加害者側は任意保険基準(保険会社独自の基準)に沿った、自賠責基準に近い金額を提示してくる可能性も否定できません。
また、実際の収入を基準とした計算では、被害者の職業によって計算方法や証明に必要となる書類がそれぞれ異なります。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
逸失利益|後遺症が残る場合や被害者が亡くなった場合
逸失利益とは、後遺症が残って事故前のように働けなくなった場合や被害者が亡くなった場合など、「事故のせいで失われた、将来の収入」のことをいいます。
後遺障害(治らないけが)を負った場合や、被害者が亡くなった場合に支払われます。
金額は、年齢や年収などにもよりますが、ケースによっては数百万円~数千万円など高額になる傾向があります。
後遺症の程度や被害者の職業・収入などによって賠償額が異なります。
また、後遺障害が認められるようなケースであったとしても、基礎収入や労働能力喪失期間をどう捉えるのかによっても金額が大きく変わります。
詳細については、以下の記事を参考にしてください。
バック事故の過失割合で損害金はどう変わる?
バック事故の過失割合に応じて受け取れるお金も変わるため、適切な過失割合を提示して納得できる示談を目指しましょう。
なお、原則として自分の過失が大きくなるほどに受け取れるお金は少なくなってしまうため、できる限り相手の過失にすることがポイントです。
過失割合が「10:0」の場合
過失割合が10対0は完全に相手に責任があるため、損害賠償金が100万円の場合は全額が相手から支払われます。
10対0になるケースとして、次の場合が挙げられます。
- 相手が信号無視によってぶつかってきた
- 相手のセンターオーバーによってぶつかってきた
- 停止中に相手がぶつかってきた
10対0を主張するためには、自分に非がなく完全に相手の責任によって事故が起こったことを証明しましょう。
過失割合が「80:20」の場合
過失割合が80対20の場合、損害賠償金が100万円のケースで受け取れる金額は80万円に留まります。
自分が受け取る金額よりも相手に支払うほうが高額な場合、マイナスになる可能性があるため注意してください。
過失割合が「70:30」の場合
過失割合が70対30の場合、損害賠償金が100万円の場合に受け取れる金額は70万円に留まります。
このように、過失が大きくなればなるほど、もらえるお金は自ずと少なくなってしまいます。
さいごに|バック事故の過失割合で揉めたら弁護士に相談を
本記事では、バック事故の過失割合や加害者に請求できるお金の種類などを解説しました。
原則、加害者の後方不注意として過失割合は10対0となりますが、ご自身の運転している車が徐行中あるいは公道を進行中の場合などは割合が異なる可能性もあります。
ケースによっては、加害者が少しでも過失割合を減らそうと事故の状況について嘘をついたり、被害者側の責任を洗い出そうとしたりする可能性も否定できません。
過失割合が多くなると、相手から受け取れる額が減るだけでなく、相手の損失額を補填するためのお金を支払わなければなりません。
仮に過失割合について話し合いで決まらない場合は当事者間で解決を試みず、速やかに弁護士に相談してください。
交通事故問題を得意とする弁護士に相談すれば、被害者に有利な証拠を集めてくれたり、適切な過失割合・損害金を算出してくれたりするでしょう。
有利に進めるためにも、バック事故をはじめ交通事故を得意とする弁護士を探してみてください。







