相続放棄の失敗例7つを徹底解説!知らないと怖い相続放棄の落とし穴とは?

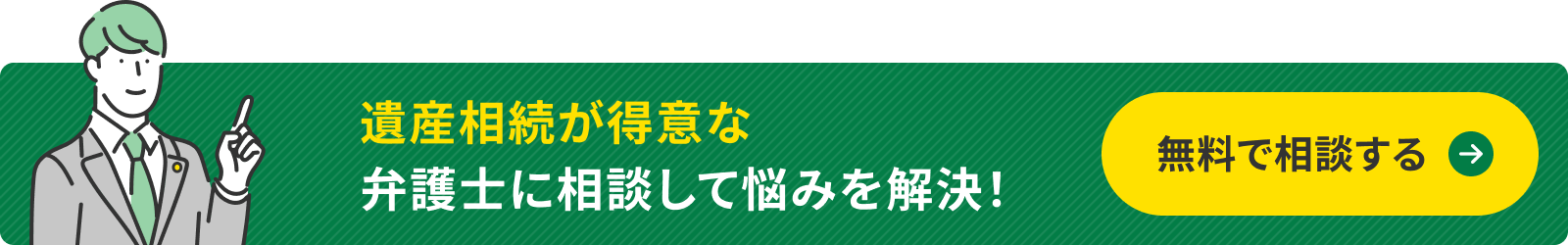

- 「相続放棄の失敗例を知りたい」
- 「相続放棄の申述が却下されることはあるの?」
被相続人が膨大な金額の借金をしていた場合など、相続放棄を検討すべきケースは少なくありません。
ただし無条件で相続放棄が認められるわけではないので、却下されないか不安になり失敗例を知りたいと考えるのも当然です。
本記事では相続放棄の失敗例7つと、相続放棄で失敗しないための対策、万が一相続放棄に失敗してしまった場合の対処法、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するとよい理由や弁護士費用の目安を解説します。
本記事を読むことで、相続放棄を確実にすすめるためのポイントを理解し、安心して手続きをすすめられるようになるでしょう。
相続放棄でよくある失敗例7つ | 知らないと怖い落とし穴とは?
まず、相続放棄でよくある失敗例を7つ紹介します。
相続財産を処分するなどして単純承認が成立してしまった
相続財産を処分するなどした場合、法律上は「相続することを認めた」とみなされ単純承認が成立してしまう可能性があります。
単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなるので注意しなくてはなりません。
たとえば相続放棄をする前に、被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費として使えば単純承認が成立します。
その結果、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるのです。
相続放棄の期限(3ヵ月)が過ぎてしまった
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内におこなわなくてはなりません(民法915条第1項)。
この期間を「熟慮期間」と呼び、熟慮期間経過後の相続放棄は原則として認められません。
期限が過ぎても相続放棄ができる場合もある
ただし、熟慮期間を過ぎた場合でも、「やむを得ない理由」があると認められれば、相続放棄が認められることもあります。
やむを得ない理由に該当するケースの具体例として、相続財産に借金があるのを把握するのが困難だった場合や、相続人が知的障害で意思能力がなく、相続放棄ができなかった場合などが挙げられます。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなかった
相続放棄は、ほかの相続人や債権者に「相続放棄をする」と伝えるものではありません。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄する旨を申述する必要があります(民法第938条)。
申述を失念して熟慮期間が経過してしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまいます(民法第921条第2号)。
必要書類の不備があったり照会書に回答しなかったりした
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ相続放棄申述書と被相続人の住民票除票や戸籍附票などの必要書類を提出します。
提出された必要書類が足りなければ、家庭裁判所から連絡が来るので指示にしたがい再提出をすれば問題ありません。
また相続放棄申述書を提出したあと、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が送られてくることがあります。
この書類は、家庭裁判所が相続放棄の意思や事情を確認するためのものです。
照会書に回答せず、放置したままにすると相続放棄の申述が却下されてしまう可能性があるので注意してください。
相続放棄の照会書が届いたら、できるだけ速やかに回答を返送するようにしましょう。
借金も遺産分割ができると勘違いしていた
借金も遺産分割ができると誤解して、後悔する例もあります。
たとえば被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業運営で作った膨大な借金も相続することになるといったことはあり得るでしょう。
遺産分割協議で、事業を引き継ぐ別の相続人が借金も全て相続することを決めたとします。
しかし借金については相続開始と同時に、法定相続分※に従い相続人に承継され、遺産分割の対象でないと考えられているのです。
| ※法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合です。 遺言書がない場合、一般的に遺産分割をする際の相続割合は法定相続分が基準とされます。 法定相続分の詳細については、以下記事で確認ください。 【関連記事】法定相続分とは?計算方法は?遺産分割したときの割合を図解で解説 | ベンナビ相続 |
相続人同士での合意があっても、債権者から法定相続分に基づく借金の返済を迫られたら拒否できません。
その結果として、はからずも被相続人が事業でつくった莫大な借金の一部を引き継いでしまうことが考えられるのです。
遺産分割協議をすると単純承認をしたとみなされるので、相続放棄をすることもできなくなります。
相続財産のなかに大きな負債があるときは、意図せずその借金を引き継いでしまわないためにも特に注意しましょう。
子ども全員が相続放棄をしたことで、想定外の相続人が登場することになった
相続放棄の使い方を誤り、後悔する例も少なくありません。
たとえば父親が亡くなり、配偶者(母親)と3人の子どもが父親の遺産を相続することになったという例を想定してみましょう。
この例では母親に全ての遺産を相続させたいと考え、3人の子どもが全員相続放棄をしたとします。
しかしこの例では、子どもが相続放棄をしたからといって母親が全ての遺産を相続する権利をもつとは限らないのです。
たとえば父親の兄弟姉妹が存命であれば、相続順位に従い子ども達の代わりにその兄弟姉妹へ相続権が移る可能性があります。
子どもが相続放棄をしてしまうことによって、想定外の相続人が登場することになるわけです。
これにより、本来は必要なかった相続争いがおこってしまう可能性も考えられます。
この例では、母親に遺産を相続させるため子どもたちが相続放棄をする必要はありませんでした。
父親の遺産を母親が全て相続することを、子ども3人が合意するだけでよかったのです。
このように相続放棄の使い方を誤ると、取り返しがつかなくなることもあるので注意しましょう。
相続順位の詳細については、以下記事が詳しいです。
【関連記事】遺産相続の相続順位と相続割合|52パターンで図解解説 | ベンナビ相続
親族に借金を背負わせる可能性があることを想定していなかった
被相続人が借金を抱えていた場合、相続放棄をするとほかの親族へ相続権が移り、その親族が借金も含め相続することになります。
相続放棄をすることについて事前に話しておかなければ、その親族は突然借金を背負うことになってしまうのです。
相続放棄をする際は、あらかじめ相続権を取得することになる親族にも事前に話しておくべきでしょう。
その親族もまた借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄などを検討する必要があります。
相続放棄で失敗しないための対策5つ
相続放棄をスムーズに進めるためには、事前にしっかり準備をすることが大切です。
以下では、失敗を防ぐための具体的な対策を5つ紹介します。
相続財産調査はしっかりおこなう
借金があるため相続放棄を検討するつもりでも、財産調査をおこなった結果、財産が見つかり、相続放棄を選ばずにすむ場合もあります。
相続が発生した場合は、被相続人の借金の有無や不動産の所在地、預貯金をくまなく確認するなどして、相続財産調査をしっかりおこないましょう。
期限切れにならないように、速やかに手続きをはじめる
相続放棄は、3ヵ月間の熟慮期間中におこなう必要があります。
できれば、相続が発生する前から準備をしておき、相続が発生した場合はスピーディーに手続きを始めておくことができるようにしておきましょう。
どうしても期限に間に合いそうにないなら期間伸長手続きを検討する
やむを得ない事情で相続放棄の手続きが間に合わない場合、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てましょう。
期間伸長の申述が認められると、相続放棄の期限が1~3ヵ月延長されます。
なお、どんな事情でも相続放棄の期間伸長が認められるわけではありません。
たとえば被相続人と疎遠で相続財産の調査に時間がかかっているなど、やむを得ないと考えられるケースに限られます。
反対に、ただ期限を知らなかった・忘れていただけなどであれば、期間伸長の申述は認められないので注意ください。
相続人の財産や借金を安易に処分しない
財産を処分すると単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
被相続人の預金を自分の支出として使うのはもちろん、被相続人の借金を返済しても単純承認とみなされる可能性があるのです。
相続放棄を検討している場合、被相続人の財産や借金に安易に手をつけることは控えましょう。
相続放棄をすると、ほかの親族などに負債を背負わせる可能性があることを把握する
上記のとおり、相続放棄をすることで、相続権が次順位の相続人に移ります。
被相続人に借金などの負債があれば、相続権を取得する親族がそれら負債を背負うことになり得るのです。
相続放棄を検討する際は、そのことを把握し適宜対応する必要があります。
たとえば慎重に相続財産の調査をしたり、相続権を取得する親族と話し合ったりなどを検討しましょう。
自分のケースでどうすればよいかわからない場合は、弁護士に相談してアドバイスを求めることも推奨されます。
相続放棄に失敗した場合の対処法2つ
万が一、相続放棄に失敗してしまった場合でも、以下のような方法で対処できる可能性があります。
手続きが間に合わなかったやむを得ない理由を裁判所に説明する
熟慮期間を経過しまった場合でも、裁判所に「やむを得ない理由」があった旨を説明することで、相続放棄ができる可能性があります。
この場合、単に「期限を知らなかった」という説明だけでは不十分で、期限を過ぎてしまったことについて正当な理由を示して、家庭裁判所に理解してもらうことが必要です。
2週間以内に即時抗告をおこなう
家庭裁判所に相続放棄の申述を却下され、その判断に納得できないのであれば、2週間の期限内に高等裁判所へ即時抗告ができます。
家庭裁判所が相続放棄の申述を却下する可能性があるのは、単純承認をしている場合や3ヵ月の熟慮期間が過ぎてしまっていた場合などです。
やむを得ない事情があれば、家庭裁判所への異議が認められる可能性がありますが簡単ではありません。
あらかじめ弁護士に相談して、アドバイスを求めることも推奨されます。
相続放棄に失敗しないため、弁護士に相談・依頼するとよい理由
これまでに見てきたとおり、相続放棄には失敗のリスクが伴います。
もっとも、弁護士に依頼することで、リスクを大幅に軽減することができます。
以下、具体的な理由を解説します。
相続放棄をすべきかも含めて適切なアドバイスがもらえる
被相続人の借金額が大きいから、という理由だけで相続放棄を決めるべきではありません。
たとえば被相続人が有する資産が負債より多いときは、相続放棄することでかえって損をしてしまいます。
相続放棄をすることで、実家の不動産などほかの遺産も相続できなくなる可能性がある点も注意しなくてはなりません。
弁護士に事情を説明することで、相続放棄が適切かほかの手段を選ぶべきかアドバイスをもらうことが可能です。
限定承認のほうがよいかのアドバイスもしてくれる
相続放棄の代わりに「限定承認」をとるという選択もあります。
限定承認は、預金などプラスの財産を相続し、その範囲内でのみマイナスの財産も引き継ぐ相続の方法です。
限定承認であれば、万が一マイナスの財産がプラスの財産より多くても、自分の財産で負債を返済するといった事態を避けられます。
逆にプラスの財産が多いなら、その分は手元に残るのです。
このようにメリットもある限定承認ですが、一方で相続人全員が限定承認の手続きをしなくてはならないなど高いハードルもあります。
弁護士に相談して事情を説明すれば、限定承認が適切かもアドバイスしてもらうことが可能です。
スムーズに手続きを進めてくれるので期限切れの不安がない
仕事などで忙しい方であれば、熟慮期間の3ヵ月中に相続財産の調査や手続きを滞りなくすませるのは難しいかもしれません。
相続放棄を得意とする弁護士に依頼すれば、相続財産の調査や手続きをスムーズに進めてくれるでしょう。
熟慮期間の期限切れで、相続放棄ができなくなってしまうような不安はほぼありません。
必要に応じて相続財産調査を任せることもできる
相続放棄をするにあたっては、まず相続財産がどれだけあるのか、借金がどれくらいあるのかを正確に把握する必要があります。
具体的には、相続人は被相続人の預貯金、土地・建物などの不動産、株式などの有価証券、さらには負債について詳細に調べなければなりません。
個人が相続財産調査をする場合、調査漏れが生じてしまうかもしれません。
弁護士に依頼することで、漏れを生じることはほぼないでしょう。
また、弁護士は「弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)」の権限を有しています。
弁護士会照会により、預金や株式などの財産についての情報を効率的に調査することができます。
相続トラブルを回避できる
相続放棄をすると次順位の相続人に権利が移る点など、相続放棄が原因で相続人間でのトラブルに発展してしまうおそれがあります。
その点弁護士に依頼すれば、弁護士から他相続人に相続放棄の理由を説明するなどしてくれるので、トラブルの回避が可能です。
債権者の対応も任せることができる
相続放棄をすれば被相続人の負債を相続する必要がないので、仮に債権者から請求を受けても対応をする必要はありません。
しかし相続放棄の手続きをすすめている際に、債権者から借金の返済を迫られる可能性があります。
相手の請求を無視し続けると訴訟を起こされるなどの不安もあり、対応に困るでしょう。
もし相手の請求に従い相続財産から借金を返済するなどすれば、単純承認したことになり相続放棄ができなくなります。
そういった際も弁護士に依頼すれば、債権者の対応を任せることが可能です。
相続人自身で対応する必要がなくなるのでトラブルを回避できるうえ、身体的・精神的な負担も軽減されるでしょう。
万が一期限が切れたときの対応も依頼できる
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所にやむを得ない理由があったことを主張すれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、その事情を上申書などで裁判所が納得するよう説明するのは難しいことがあるのは否めません。
実績が豊富な弁護士に依頼すれば、自分でするよりずっと適切に裁判所へ事情を説明してくれます。
相続放棄が認められる可能性を高めるためにも、弁護士に依頼することを検討するとよいでしょう。
相続放棄を弁護士に任せる場合の費用はどのくらい?
相続放棄を弁護士に依頼した場合の費用は法律事務所によって異なるものの、おおよその相場は以下のとおりです。
- 相談料:0円~1万円
- 申述書作成代理費用:5,000円~1万円程度(戸籍謄本取得・実費含む)
- 代理手数料:5万円~10万円程度
- 成功報酬:なし
- 合計:5万円~
相続財産調査も弁護士に依頼する場合、追加で10万円~30万円程度の費用がかかります。
遺産相続については、無料で相談に応じてくれる弁護士も少なくありません。
弁護士費用がいくらになるか不安であれば、無料相談の際に詳しい見積もりをもらうことも推奨されます。
複数の弁護士に無料相談を申し込み、弁護士費用を比較するのも手です。
相続放棄の失敗に関してよくある質問
以下、相続放棄の失敗に関してよくある質問をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してみてください。
相続放棄の申述をしたら裁判所にどこまで調べられる?
家庭裁判所で相続放棄の申述をした場合、単純承認が成立する行為がおこなわれたか詳細に調べられることは実際のところ少ないです。
相続放棄を受理するか判断するにあたり、立ち入りの調査がおこなわれることも基本的にはありません。
明らかに却下しなくてはならない理由※がない限り、相続放棄の申し立ては受理されるのが通常です。
相続放棄の申述が却下されることは滅多にありません。
「司法統計(家事 令和5年度)」によれば、令和5年における相続放棄の却下率は0.14%と非常に低いことがわかります。
ただし、申述が受理されたからといって、相続放棄が確定するわけではなく、これを争う被相続人の債権者から訴えられる可能性がある点は注意が必要です。
仮に債権者から訴えられ、相続財産の処分・隠匿が発覚すると、相続放棄ができなくなってしまいます。
※被相続人の銀行口座を解約したり不動産の名義を変更したりすれば、すぐに発覚して却下される可能性が高くなります。
被相続人が残した非常に高価な美術品・ブランド品などを引き取ったようなケースでも、発覚する可能性が高いです。
反対に売っても価値がないような被相続人の衣服や所持品を引き取っても、発覚する可能性は低いでしょう。
相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼するとよい?
相続放棄の手続きは弁護士だけでなく、司法書士に依頼することも可能です。
依頼にかかる費用を比べると、弁護士の場合は5万円~かかる一方で、司法書士なら3万円~が相場となります。
費用で比べれば、司法書士の方が若干安いでしょう。
一方で弁護士に依頼すれば、相続放棄の手続きを全て任せられます。
たとえば弁護士なら照会書への回答や裁判所への出廷代理などの対応も可能です。
司法書士は相続放棄に必要な書類の収集や作成はしてくれますが、その他は自分でおこなう必要があります。
相続放棄の手続きについて書類の収集・作成以外は自分でするということなら、費用が安価な司法書士に依頼してもよいでしょう。
一方で相続放棄の手続きを一任して、スムーズにすすめたいなら弁護士に依頼するとよいです。
相続放棄の期限後に借金がみつかったら相続放棄はできる?
相続放棄には相続開始から3ヵ月という期限がありますが、実務上は柔軟に運用されており、期限経過後でも家庭裁判所の裁量的判断で認められるケースは少なくありません。
相続放棄の期限後に借金が見つかった場合についても、以下の条件を満たせば相続放棄が認められる可能性が高いです。
- 相続放棄を検討するきっかけとなるような、借金の存在を知らなかった
- 借金の存在を知らなかったことに関し、やむを得ない理由がある
- 借金の存在を知ってから、3ヵ月以内に相続放棄の申述をした
「2」の「やむを得ない理由」とは、被相続人とほとんど交流がなかったり借金の存在を示す資料が破棄されていたりなどがあげられます。
また弁護士に財産調査を依頼したものの借金が発覚しなかったという場合も、やむを得ない理由として認められる可能性が高いでしょう。
相続放棄をしたら、死亡保険金や遺族年金も受け取れない?
死亡保険の受取人として相続人が指定されていれば、仮に相続放棄をしたとしても相続人が受け取ることができます。
また遺族年金は遺族に取得する権利があり、相続とは関係がありません。
遺族である相続人が相続放棄をしていたとしても、遺族年金は受け取ることが可能です。
一方で死亡保険金について、被相続人自身が受取人に指定されていた場合、相続放棄をした相続人は受け取れません。
このケースでは、死亡保険金は被相続人が保有する財産の一部と考えられるためです。
このように生命保険の受取人が誰に設定されているかで結論が異なるので、不安であればあらかじめ確認しておきましょう。
さいごに | 相続放棄の手続きに不安があれば弁護士へ相談を!
相続放棄の手続きは、法律の専門知識が求められる場面も多く、やり方を間違えると大きなトラブルにつながる可能性があります。
また、熟慮期間が設定されているので、手続きをスピーディーにおこなう必要があります。
弁護士に依頼することで、相続放棄の失敗を防ぐことができます。
相続放棄の手続きに不安があれば、弁護士に相談することを強くおすすめします。







