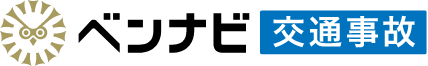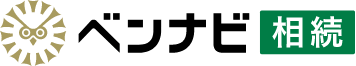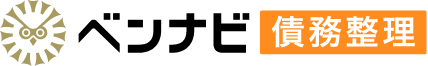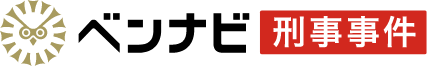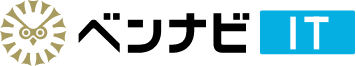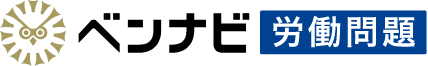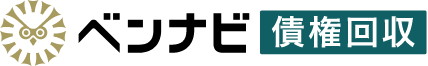弁護士の選び方のコツとは?信頼できる弁護士の探し方・見分け方のポイントを解説


法律トラブルに巻き込まれた際、信頼できる弁護士を知っているという方は少ないでしょう。
なかには「弁護士は優秀だから、誰に頼んでも同じ結果が得られる」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、実際のところは、どの弁護士を選ぶのかによって結果が大きく変わる可能性があります。
本記事では、これから弁護士を探す方に向けて、弁護士を選ぶ際に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
弁護士の探し方や、弁護士に依頼するまでの具体的な流れ、弁護士費用の相場なども解説するので、実際に弁護士を探す際に参考にしてみてください。
弁護士を選ぶ前には相談状況を整理しておくことが大切
まず、弁護士を選ぶ前に以下のような情報を整理しておきましょう。
- どのような問題で困っているのか
- どのような形での解決を希望するのか
- 予算はどれぐらいか など
相談状況や希望内容などをまとめておけば、法律相談の際に弁護士がスムーズに状況を把握できて的確なアドバイスが望めます。
口頭では伝え漏れが発生する可能性があるためメモに残しておき、相談内容に関する資料があればあわせて準備しておきましょう。
自分に合った弁護士の探し方
弁護士の探し方としては、主に以下の5つの方法があります。
- 友人・知人に紹介してもらう
- インターネットで検索する
- 弁護士ポータルサイトを利用する
- 弁護士会で紹介してもらう
- 法テラスを利用する
ここでは、それぞれの探し方について解説します。
1.友人・知人に紹介してもらう
弁護士に依頼したことがある友人・知人がいれば、紹介してもらうという方法があります。
信頼できる友人・知人からの紹介であれば、安心して問題解決を依頼することができます。
ただし、詳しくは「【相談前】信頼できる弁護士の選び方のポイント」で後述しますが、弁護士にはそれぞれ得意分野・不得意分野があります。
「友人の依頼内容は遺産相続で、自分は離婚問題で悩んでいる」というようにトラブル内容が異なる場合、離婚問題には注力しておらず的確なサポートが受けられないおそれがあります。
友人・知人から紹介してもらう際は、どのようなトラブルで悩んでいたのか確認し、もし自分と異なる場合は法律事務所ホームページにて注力分野や解決実績を確認する必要があります。
2.インターネットで検索する
弁護士を紹介してくれる友人・知人がいない場合、インターネットで検索するのも有効です。
GoogleやYahoo!にて「地域 相談分野 弁護士」などでキーワード検索すれば、キーワードに合ったさまざまな法律事務所ホームページがヒットします。
たとえば、新宿で遺産相続について相談したい場合は「新宿区 遺産相続 弁護士」「新宿駅 遺産相続 弁護士」などのキーワードで検索しましょう。
ただし、インターネット検索では数多く法律事務所ホームページがヒットして情報過多になり、弁護士選びに手間や時間がかかるおそれがあります。
3.弁護士ポータルサイトを利用する
弁護士ポータルサイトとは、さまざまな地域の弁護士・法律事務所の情報が掲載されているサイトのことです。
「自分で弁護士を選びたい」「トラブル内容に合った弁護士に相談したい」という方は、弁護士ポータルサイトを利用することをおすすめします。
当社が運営する「ベンナビ」では、法律分野ごとにサイトを設置しています。
お住まいの地域や相談内容を選ぶだけで対応可能な弁護士を一括検索でき、弁護士選びが初めての方でも自分に合った弁護士をスムーズに探すことができます。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、弁護士費用が不安な方もまずは一度利用してみましょう。
4.弁護士会で紹介してもらう
ほかの探し方としては、弁護士会に紹介してもらうという方法もあります。
弁護士会とは、弁護士や弁護士法人が加入している団体のことです。
弁護士会は各都道府県に設置されており、東京弁護士会や大阪弁護士会では法律トラブルで悩む方に向けて「弁護士紹介制度」を実施しています。
弁護士紹介制度を利用する際は、インターネットや電話などで申し込みが必要で、詳しい流れは各弁護士会のホームページをご確認ください。
注意点として、必ずしも自分に合った弁護士を紹介してくれるわけではなく、相談内容によっては紹介を断られることもあります。
5.法テラスを利用する
弁護士費用を支払う余裕がない方は、法テラスの利用も有効です。
法テラスとは、法律トラブルで悩む全ての国民に司法サービスや必要な情報を提供することを目的に設立された公的機関です。
法テラスでは、法律トラブルの解決に役立つ法制度や相談先を紹介してくれる「法テラス・サポートダイヤル」を設置しているほか、経済的事情で弁護士に依頼できない方に向けて「民事法律扶助制度」なども提供しています。
民事法律扶助制度では、弁護士や司法書士との無料法律相談や、弁護士費用や司法書士費用の一時立替えなどのサポートをおこなっています。
ただし、利用するためには収入基準や資産基準などの条件を満たしている必要があり、詳しくは「民事法律扶助業務|法テラス」をご確認ください。
【相談前】信頼できる弁護士の選び方のポイント
これから弁護士を探す際は、以下のような点をチェックしましょう。
- 自分の相談内容と弁護士の得意分野は一致しているか
- 弁護士との連絡や返信はスムーズか
- 弁護士の人柄や相性が合っているか
- 弁護士費用は適切か・料金体系は明確か
- 過去に懲戒処分を受けているか
- 法律事務所のアクセスは良いか
ここでは、弁護士選びで失敗しないためのポイントについて解説します。
自分の相談内容と弁護士の得意分野は一致しているか
弁護士を選ぶ際は、自分の相談内容と弁護士の得意分野が一致しているか確認しましょう。
弁護士が対応する法律分野は多岐にわたり、たとえば交通事故・遺産相続・離婚問題・債権回収・債務整理・インターネットトラブル・企業法務などがあります。
一口に弁護士といっても、これまで解決してきた案件や力を入れている分野は弁護士ごとに異なります。
対応経験の浅い弁護士などを選んでしまうと、思うように動いてくれずに不満を感じてしまうおそれがあるため、自分が相談したい内容を得意としている弁護士を選びましょう。
弁護士の得意分野や解決実績は、各法律事務所ホームページやベンナビで確認できます。
弁護士との連絡や返信はスムーズか
弁護士のレスポンスの早さも判断基準のひとつです。
弁護士によっては、以下のような理由で連絡や返信が遅れることもあります。
- 弁護士が多くの案件を抱えていて忙しい
- 弁護士一人、事務員一人で全ての業務を回している
- 弁護士の出張が多く、事務所にいる時間が少ない など
弁護士の対応が遅いと、そのぶん問題解決も長引いてしまうため、なるべくスピーディな対応を心がけている弁護士を選びましょう。
弁護士の人柄や相性が合っているか
弁護士の人柄・相性もチェックすべきポイントのひとつです。
配偶者との離婚や親族との相続トラブルなど、法律トラブルでは相談内容がセンシティブで他人には相談しにくいというケースも多くあります。
しかし、問題解決のためには、話しにくいことも全て弁護士に伝える必要があります。
たとえ解決実績が豊富な弁護士でも、態度が冷たくて話しにくい雰囲気の場合はストレスを感じてしまいますし、相性が合わない場合は相談内容がうまく伝わらないこともあります。
できるだけストレスなく的確なサポートを受けるためにも、「この人なら何でも話せる」と思えるような弁護士を選びましょう。
弁護士費用は適切か・料金体系は明確か
弁護士を選ぶ際は、弁護士費用についても確認が必要です。
弁護士費用は法律事務所ごとに自由に設定できるため、それぞれ金額にはバラつきがあります。
法律事務所によっては弁護士費用が比較的高額なところもありますし、なかには料金体系が不明瞭で依頼後に予想以上の金額を請求されたりすることもあります。
余計なトラブルを避けるためにも、費用体系について法律事務所ホームページなどで詳しく説明しているところを選びましょう。
過去に懲戒処分を受けているか
弁護士の中には、法律違反や不正行為などで懲戒処分を受けている弁護士もいます。
懲戒処分に至るまでの経緯はさまざまですので、必ずしも「懲戒処分を受けている弁護士は危険」というわけではありません。
ただし、過去に何度も懲戒処分を受けているような弁護士に関しては、トラブルのリスクがあるため避けたほうが安心です。
弁護士の懲戒処分の情報は「弁護士懲戒処分検索センター」から確認できます。
法律事務所のアクセスは良いか
「自宅や職場から法律事務所が近いかどうか」も確認すべきポイントのひとつです。
法律事務所が遠くにある場合、法律相談の際には多くの時間や交通費がかかってしまいますし、問題解決を依頼する際は弁護士の交通費などもかさんでしまいます。
状況によっては、依頼後も打ち合わせのために何度か法律事務所に行くこともあるため、なるべく通いやすいところにある法律事務所を選びましょう。
【相談後】弁護士に依頼すべきかどうかのチェックポイント
法律相談だけでなく問題解決も依頼したい場合は、以下のような点をチェックしましょう。
- 弁護士から提示された解決策や対応方針に納得できたか
- 実際に相談してみて信頼できると感じたか
- デメリットやリスクなども伝えてくれたか
ここでは、問題解決を依頼する弁護士の選び方について解説します。
弁護士から提示された解決策や対応方針に納得できたか
弁護士に依頼する際は、納得のいく解決策や対応方針を提案してくれる弁護士を選びましょう。
弁護士が提示する解決策や対応方針に納得いかない場合、そのまま依頼してしまうと最終的に不満の残る結果になってしまうおそれがあります。
同じトラブルでも、弁護士によってはアプローチの仕方が異なることもあるため、もし弁護士の提案内容に納得いかない場合は別の弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
実際に相談してみて信頼できると感じたか
弁護士に相談してみて「信頼できると感じたかどうか」も重要な判断基準のひとつです。
法律トラブルの解決を依頼する場合、なかには弁護士との関係が数年以上続くこともあります。
依頼後は弁護士と二人三脚で問題解決に向けて取り組むことになり、問題解決のためには積極的にコミュニケーションを取って情報共有することが大切です。
ストレスなく情報共有をおこなうためにも、「人柄は良いか」「話しやすい雰囲気か」「説明はわかりやすく丁寧か」なども確認したうえで依頼しましょう。
デメリットやリスクなども伝えてくれたか
弁護士の中には、相談者に都合のよいことばかり伝えてくる弁護士もいます。
しかし、法律トラブルに「絶対」はなく、解決策ごとにメリットとデメリットがあります。
都合のよいことばかり伝えてくる弁護士の場合、依頼後に予期せぬトラブルが発生したりして不利益を被る可能性があります。
法律トラブルの解決を依頼する際は、今後のリスクやデメリットなども全て正直に説明してくれる弁護士を選んだほうが安心です。
弁護士選びで失敗しないための注意点
法律トラブルで弁護士を選ぶ際は、以下のような点に注意しましょう。
事務所の規模や知名度の高さで決めるのは避ける
「大手法律事務所」や「有名弁護士」など、事務所の規模や知名度の高さだけをみて選ぶのは避けましょう。
大手法律事務所だからといって、必ずしも自分にとって最適なサポートが受けられるわけではなく、なかには弁護士との相性が合わないこともあります。
「【相談前】信頼できる弁護士の選び方のポイント」や「【相談後】弁護士に依頼すべきかどうかのチェックポイント」でも解説したとおり、弁護士を選ぶ際は得意分野・解決実績・相性の良さ・弁護士費用などを総合的に考慮したうえで決めることが大切です。
実際に法律事務所に足を運び、自分の目で見て信頼できると感じた弁護士に依頼しましょう。
弁護士費用が極端に安い法律事務所には注意する
ほかの法律事務所に比べて、金額設定が極端に安いところも注意が必要です。
弁護士費用は自由化されているため、法律事務所によって多少のバラつきはありますが、あまりにも安い場合は依頼後に高額な追加料金を請求されたりするおそれがあります。
また、ほかの法律事務所に比べてサポートが手薄だったり、弁護士からの連絡が遅かったりする可能性もあります。
安いからといって安易に依頼しようとせず、見積もりを出してもらって費用総額を確認したり、インターネット上の評判などを確認したりすることをおすすめします。
依頼後も同じ弁護士が対応してくれるか確認する
法律相談後に問題解決を依頼する場合、相談に乗ってくれた弁護士とは違う弁護士が対応にあたることもあります。
当然、弁護士間で引き継ぎをしたうえでしっかり対応してくれるため、担当が変わったからといって依頼結果が大きく変わるわけではありません。
それでも同じ弁護士にそのまま対応してもらいたい方は、相談時に「誰が事件終了まで担当してくれるのか」を確認しておきましょう。
弁護士を探して依頼するまでの流れ
実際に弁護士を探して依頼するまでは、基本的に以下のような流れで進みます。
- 弁護士を探して相談予約をする
- 弁護士との法律相談をおこなう
- 問題解決を依頼する場合は見積もりを取る
- 弁護士と委任契約を締結する
- 着手金を支払って問題解決してもらう
ここでは、それぞれの流れについて解説します。
1.弁護士を探して相談予約をする
まずは、インターネット検索や弁護士ポータルサイトなどで弁護士を探しましょう。
基本的に弁護士との法律相談では事前予約が必要ですので、条件に合った法律事務所が見つかったら、電話やインターネットなどで相談予約をしてください。
相談予約が済んだら、質問事項をまとめて相談内容に関する資料も整理しておき、法律相談の準備を整えておきましょう。
2.弁護士との法律相談をおこなう
相談日当日になったら、弁護士と法律相談をおこなってアドバイスを受けます。
法律相談は面談形式が一般的ですが、なかには電話・メール・LINE・オンラインなどに対応しているところもあります。
「どうしても忙しくて法律事務所に行く余裕がない」というような場合は電話相談やオンライン相談などが有効ですが、弁護士の人柄や雰囲気などを確認するためにも、基本的には面談形式で相談することをおすすめします。
なお、法律相談で納得のいく回答が得られなかった場合は、別の弁護士にも相談してみることをおすすめします。
弁護士によっても法律問題に対するアプローチの仕方は異なるため、別の弁護士なら異なる視点から良いアドバイスをしてくれる可能性があります。
3.問題解決を依頼する場合は見積もりを取る
法律問題のアドバイスだけでなく問題解決を依頼したい場合は、相談時に弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう。
法律トラブルの解決にかかる主な費用としては、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。
法律事務所によって料金体系や支払うタイミングは異なるため、依頼前には必ず確認しておきましょう。
なお、法律相談後すぐに依頼する必要はなく、一旦持ち帰って検討することも可能です。
依頼はせずに法律相談だけの利用も可能ですので、依頼するかどうか迷っている方も遠慮なくご相談ください。
4.弁護士と委任契約を締結する
弁護士に問題解決を依頼する場合は、委任契約を結びます。
弁護士と契約する際には、委任契約書の作成が必要です(弁護士職務基本規程30条)。
委任契約書には、受任の範囲・弁護士費用・中途終了時の取り扱い・トラブル時の解決方法などの条項が記載されているので、必ず全ての内容に目を通したうえで合意しましょう。
なお、法律相談後に一旦持ち帰ってから弁護士への依頼を決めた場合は、再度法律事務所を訪れるか、郵送やインターネットなどで契約書を交わすことになります。
5.着手金を支払って問題解決してもらう
弁護士に問題解決を依頼する際は、着手金の支払いも必要です。
着手金は依頼結果に関わらず発生する費用であるため、たとえ失敗に終わったとしても原則返金されません。
契約手続きや着手金の支払いが済んだら、弁護士が依頼者の代理人として対応にあたり、適宜進捗報告を受けることになります。
弁護士の尽力によって問題が解決すれば、報酬金・実費・日当などの費用を支払ったのち、委任契約は終了となります。
【分野別】法律トラブルでかかる弁護士費用の相場一覧
現在では弁護士費用は自由化されていますが、かつては「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という報酬基準が定められていました。
法律事務所によっては、現在でも旧報酬基準を参考に弁護士費用を定めているところもあります。
法律トラブルごとの弁護士費用の相場をまとめると以下のとおりです。
なお、経済的利益の額は500万円と仮定して計算しています。
| トラブル分野 | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 離婚問題 | 約100万円~約170万円 |
| 遺産相続 | 約10万円~約100万円 |
| 債務整理 | 約20万円~約100万円 |
| 交通事故 | 約102万円 |
| 刑事事件 | 約60万円~約100万円 |
| 労働問題 | 約5万円~約130万円 |
| インターネットトラブル | 約10万円~約100万円 |
| 債権回収 | 約50万円~約130万円 |
| 企業法務 | 約3万円~約2,000万円 |
| 不動産トラブル | 約60万円~約120万円 |
| 医療過誤 | 約120万円~約200万円 |
| 消費者トラブル | 約60万円~約110万円 |
ただし、法律事務所によっても料金体系は異なりますので、あくまでも目安のひとつ程度に留めてください。
正確な金額を知りたい場合は、直接事務所に確認しましょう。
まとめ
法律トラブルについて弁護士に相談する際は、得意分野・レスポンスの早さ・相性・弁護士費用・懲戒処分の有無・アクセスの良さなどを見て選ぶことが大切です。
特に弁護士の人柄や雰囲気などは実際に話してみないとわからなかったりするため、無料相談なども活用しながら何人かの弁護士と相談してみて、信頼できる弁護士を選びましょう。
弁護士の探し方はいくつかありますが、なかでもお住まいの地域から分野ごとに弁護士検索できるベンナビがおすすめです。
ベンナビなら、初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、弁護士費用が不安な方も気軽にご利用ください。