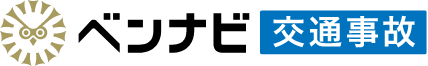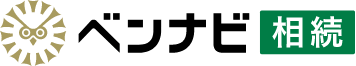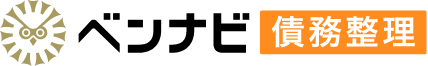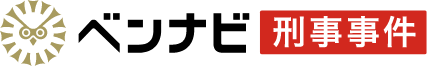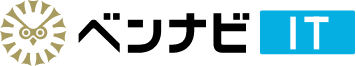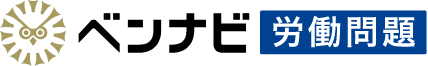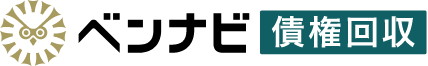【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説


内容証明郵便とは、郵便局が差出人・受取人・内容・差出日時を証明してくれるサービスのことです。
「誹謗中傷の書き込みを削除してほしい」「貸したお金を返してほしい」「不倫相手に慰謝料請求したい」など、法律トラブルで悩んでいる場合は内容証明郵便を利用するのが効果的です。
しかし、多くの方は内容証明郵便を送るのが初めてで「具体的にどのようなメリットがあるのか」「どのように書けばよいのか」など、わからないこともあるでしょう。
本記事では、内容証明郵便が必要なケースや効力、具体的な作成方法やケースごとの文例、内容証明郵便を受け取り拒否・無視された場合の対処法などを解説します。
内容証明郵便とは
まずは、内容証明郵便の特徴や、ほかの郵便方法との違いなどを解説します。
「いつ」「誰が誰に」「どのような内容」を送ったのかを郵便局が証明してくれる
内容証明郵便とは、いつ・誰が誰宛てに・どのような内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便を利用した場合、差出郵便局にて文書のコピー(謄本)が5年間保管され、その間は謄本の閲覧や再度証明の請求が可能です。
内容証明郵便で郵便局が証明できる事項
内容証明郵便を利用すれば、郵便局では以下のような事項を証明してくれます。
- 差出人の住所・氏名
- 受取人の住所・氏名
- 文書の記載内容
- 差し出した日付
なお、内容証明郵便では「郵便物を発送した」という事実は証明できるものの、「郵便物が相手に配達された」という事実まで証明するものではありません。
配達の事実まで証明できるようにしておきたい場合は、内容証明郵便を発送する際に配達証明も付けておく必要があります。
内容証明郵便とその他の郵便の違い
内容証明郵便以外の送り方としては、主に普通郵便・特定記録郵便・配達証明などがあります。
- 普通郵便:オプションなどが付いていない通常の郵便
- 特定記録郵便:郵便局が郵便物やゆうメールを引き受けた時間や、配達状況を記録してくれるサービス
- 配達証明:「郵便物を配達した」という事実を郵便局が証明してくれるサービス
内容証明郵便との主な違いをまとめると以下のとおりです。
| 内容の証明 | 配送状況の記録 | 賠償の有無 | 配達の証明 | |
|---|---|---|---|---|
| 内容証明郵便 | 〇 | 〇(書留扱い) | 〇(書留扱い) | × |
| 普通郵便 | × | × | × | × |
| 特定記録郵便 | × | 〇 | × | × |
| 配達証明 | × | 〇(書留扱い) | 〇(書留扱い) | 〇 |
内容証明郵便の効力
ここでは、内容証明郵便を利用することでどのようなメリットがあるのかを解説します。
裁判の際に有効な証拠となる
内容証明郵便は通常の郵便よりも証拠能力が高く、裁判などの法的手続きをおこなう際は証拠として採用されることもあります。
たとえば、裁判で相手が「訴訟内容について一切知らない」などと主張していても、訴訟前に内容証明郵便を送付していれば送付事実や内容を証明でき、相手の主張を覆せる可能性があります。
債権の時効完成が6ヵ月間猶予される
債権には消滅時効という制度が設けられており、時効期間を過ぎて時効が完成すると債権が消滅してしまい、債務者に対して請求できなくなります。
ただし、時効には「時効の完成猶予」という制度があり、内容証明郵便で債務者に請求書を送付すれば1度だけ時効の完成が6ヵ月間猶予されます(民法第150条1項、2項)。
時効が間近に迫っているような状態でも、内容証明郵便による催告をおこなうことで時間を稼ぐことができ、その間に訴訟の準備などを進めることができます。
相手に対して心理的なプレッシャーを与えることができる
内容証明郵便の書式は厳格に定められており、体裁の整った文章で損害賠償請求などの意思表示をすることで相手がプレッシャーを感じ、やり取りが有利に進む可能性があります。
内容証明郵便の場合、受取人は配達員から直接手渡しで受け取らなければならず、受け取る際は受領印やサインが必要という点でも通常の郵便とは異なります。
また、弁護士に依頼すれば弁護士名義で送付してもらうこともでき、その場合はより大きな心理的プレッシャーを与えられる可能性があります。
内容証明郵便を利用したほうがよいケース
特に以下のようなケースでは、内容証明郵便の送付が効果的です。
- 迷惑行為や違反行為に対して警告したい場合
- 借金の時効援用をおこないたい場合
- 未払いの債権を回収したい場合
- 慰謝料請求や損害賠償請求したい場合
ここでは、内容証明郵便の必要性やメリットを解説します。
迷惑行為や違反行為に対して警告したい場合
ストーカー行為やSNSでの誹謗中傷など、迷惑行為や違反行為をおこなう相手に対して警告したい場合には内容証明郵便の送付が効果的です。
内容証明郵便で迷惑行為や違反行為を止めるよう警告し、法的措置を検討していることなども伝えることで、こちらの本気度が相手に伝わって問題解決につながる可能性があります。
なお、問題が解決しなければ法的措置を検討することになりますが、その場合も被害状況などを訴える際に内容証明郵便が証拠として役に立ちます。
借金の時効援用をおこないたい場合
時効の援用とは、債務者が債権者に対して「時効期間を過ぎているので借金の返済義務はありません」と意思表示することです。
借金の返済義務は時効期間を過ぎただけでは消滅せず、この「時効の援用」という手続きをおこなわなければいけません。
時効の援用をおこなう際は、債務の内容や時効援用の意思などを記載した「時効援用通知書」を作成して内容証明郵便で送るのが一般的です。
内容証明郵便で送ることで時効援用通知書の送付事実が記録として残り、もし債権者から裁判を起こされたとしても時効の援用が有効であることを主張できます。
未払いの債権を回収したい場合
内容証明郵便は、債権回収をおこなう際にもよく用いられます。
「内容証明郵便の効力」で解説したとおり、内容証明郵便で債務の履行を催告すれば時効完成が6ヵ月間猶予され、その間に訴訟準備などを進めることができます。
内容証明郵便を送付しておくことで、裁判に発展した際は自分の主張や請求の事実などを証明することもでき、「言った言わない」のトラブルを回避できます。
慰謝料請求や損害賠償請求したい場合
「配偶者の不倫相手から慰謝料を受け取りたい」「交通事故の加害者から賠償金を受け取りたい」など、慰謝料請求や損害賠償請求する際も内容証明郵便の送付が効果的です。
このようなケースでは、相手によっては口頭や通常の郵便で連絡しても応じてくれないこともあります。
内容証明郵便を送付することで、相手に心理的プレッシャーを与えることができ、スムーズに慰謝料や賠償金を獲得できる可能性があります。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便の書式に関しては字数制限や行数制限が細かく定められており、使用できる文字にも制限があります。
ここでは、内容証明郵便の作成方法について解説します。
内容証明郵便の書式・用紙
内容証明郵便の用紙については特に定めはなく、材質・サイズ・枚数は自由です。
ただし、提出後5年間は差出郵便局で保管されるため、厚手のコピー用紙や品質の良い印刷用紙などの比較的劣化しにくい材質のものを利用したほうが安心です。
内容証明郵便の作成方法としては、手書きでもパソコン(Wordなど)でも作成可能ですが、注意点として以下のような字数制限・行数制限があります。
| 書き方 | 文字数・行数 |
|---|---|
| 縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
| 横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
※句読点や記号は1個1文字としてカウント、「」や『』は2つで1文字としてカウント
【参考元】内容証明 ご利用の条件等|郵便局
さらに、使用できる文字にも制限があり、ひらがな・カタカナ・漢字・数字・括弧・句読点・英語(固有名詞のみ)・その他一般的な記号のみ使用可能です。
内容証明郵便に記載すべき項目
内容証明郵便に記載すべき項目は以下のとおりです。
- 表題(通知書・請求書・催告書・警告書など)
- 日付
- 通知内容
- 差出人の住所・氏名
- 受取人の住所・氏名 など
注意点として、封筒にも差出人と受取人の住所・氏名の記載が必要です。
複数人で内容証明郵便を発送する場合は、差出人全員の住所・氏名を記載しましょう。
内容証明郵便を送る際に必要な部数
内容証明郵便を送る際は、同一の書面を3部用意する必要があります。
ひとつは相手に送る用、ひとつは郵便局での保管用、ひとつは自分の控え用となります。
なお、内容証明郵便を手書きで作成する場合、3通全て手書きで作成する必要はありません。
1通は手書きで作成し、残りの2通はコピーでも問題ありません。
e内容証明ならインターネット上で24時間発送できる
e内容証明(電子内容証明)とは、インターネット上で内容証明郵便を発送できるサービスのことです。
e内容証明なら郵便窓口での手続きは不要で、24時間いつでも利用可能です。
また、通常の内容証明郵便よりも料金が若干安く済むというメリットもあります。
【ケース別】内容証明郵便の文例・記載例
ここでは、以下のようなケースでの内容証明郵便の文例を紹介します。
- SNSやインターネット掲示板で誹謗中傷された場合の文例
- 退職した社員が退職時の取り決めに違反した場合の文例
- 未払金や売掛金の支払いを催促する場合の文例
- 慰謝料請求や損害賠償請求する場合の文例
ただし、個々の事情によっても記載すべき内容は異なります。
以下の文章をそのまま流用するのは避けて、もしわからないことがあれば弁護士に相談してください。
SNSやインターネット掲示板で誹謗中傷された場合の文例
「SNSで自分のお店を誹謗中傷する投稿を発見し、削除してほしい」というような場合、内容証明郵便の文例は以下のとおりです。
| 貴殿は2025年1月1日、X(旧Twitter)上の貴殿のアカウント(@xxx)において、当法人が運営する飲食店「〇〇」に関し、「賞味期限切れの食材を使用している」「食中毒事故を起こした」などと投稿されました。 しかし、これらの内容は事実に反するものであり、当法人の社会的信用や営業上の名誉を著しく損なうものです。 当該投稿は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為であり、名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当する可能性があります。また、民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象にもなり得ま す。 つきましては、当該投稿を速やかに削除いただきたく、本書面をもって通知いたします。 なお、対応がみられない場合は、刑事告訴や損害賠償請求訴訟など、必要な法的措置を検討いたしますので、あらかじめご承知おきください。 |
退職した社員が退職時の取り決めに違反した場合の文例
「退職した社員が会社の顧客に対して勧誘行為をしており、退職時の取り決めに違反している」というような場合、内容証明郵便の文例は以下のとおりです。
| 貴殿は2025年1月31日付で、当法人を退職されました。 退職にあたり締結した誓約書において、貴殿は当法人在籍中に知り得た一切の情報を退職後に使用しない旨に同意されています。 しかしながら、退職後、当法人の顧客に対し、電話により当法人との契約から貴殿が提供するプランへの変更を勧誘する行為が確認されました。 これらの行為は、誓約書に基づく義務に違反するとともに、競業避止義務違反や不正競争防止法違反等に該当する可能性があります。 つきましては、当該行為を直ちに中止し、現在保持している当法人の顧客情報を全て削除するよう強く要請します。 今後、当法人の顧客に対するいかなる接触・勧誘行為も行わないよう、あらためて厳重に警告いたします。 なお、本通知にもかかわらず、上記行為が継続する場合には、損害賠償請求や仮処分申立てなどの必要な法的措置をとることになりますので、あらかじめご承知おきください。 |
未払金や売掛金などの債権回収をおこなう場合の文例
「未回収の売掛金があり、相手先に支払いを求めても一向に応じてくれない」というような場合、内容証明郵便の文例は以下のとおりです。
| 拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、当方は下記のとおり、貴社に対し売掛金のお支払いを請求いたします。 下記売掛金については、これまでに口頭および書面にて再三ご連絡差し上げておりますが、現在に至るまでお支払いいただいておりません。 つきましては、本書面到達後◯日以内に、下記金額を当方指定口座へお振込みいただきますようお願い申し上げます。 なお、期日までにお支払いいただけない場合には、やむを得ず法的手続き(訴訟・支払督促)等に移行することになりますので、あらかじめご承知おきください。 【請求内容】 金額:金◯◯円(税込) 請求対象:◯月◯日納品の◯◯にかかる売掛金 支払期日:◯年◯月◯日 送金先口座:◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯ 口座名義人◯◯◯◯ 本件に関するご不明点等がございましたら、速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。 敬具 |
慰謝料請求や損害賠償請求する場合の文例
「配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に対して慰謝料請求したい」というような場合、内容証明郵便の文例は以下のとおりです。
| 貴殿は、私の配偶者である〇〇(氏名)が既婚者であることを知りながら、2025年◯月頃より、継続的に不貞行為を行っていたことを確認しています。 私は〇〇と、20◯◯年◯月◯日に婚姻し、現在も法律上の婚姻関係にあります。 このような行為は、私に対して著しい精神的苦痛を与えるものであり、不法行為に該当します(民法709条)。 つきましては、貴殿に対し、慰謝料として金◯◯万円を請求いたします。 下記の口座宛に、本書面到達後◯日以内にお振込みください。 振込先口座:◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯ 口座名義人◯◯◯◯ この件について、今後も誠意ある対応が見られない場合には、弁護士を通じて慰謝料請求訴訟などの法的手段に移行することも検討しております。その点、あらかじめご承知おきください。 |
内容証明郵便の送り方
内容証明郵便の送り方は、通常の内容証明郵便とe内容証明で異なります。
ここでは、それぞれの送り方について解説します。
通常の内容証明郵便の場合
通常の内容証明郵便の場合、郵便局窓口で手続きをおこなう必要があります。
郵便局によっては内容証明郵便に対応していないところもあるため、まずは「郵便局・ATMをさがす|日本郵政グループ」で郵便局を探して対応状況を確認しておきましょう。
郵便局窓口では、以下のものを提出すれば手続き完了となります。
- 書面3部(受取人用・郵便局の保管用・差出人の控え用)
- 封筒(差出人と受取人の住所・氏名を記載したもの)
- 郵便料金
なお、提出時に不備が見つかった場合は訂正印を押して訂正が必要になるため、念のため印鑑も持参しておくことをおすすめします。
e内容証明(電子内容証明)の場合
e内容証明の場合、発送までの流れは以下のとおりです。
- 専用Webサイトに無料利用登録をしてログインする
- Wordファイルで作成した文書をアップロードする
- 差出人や宛先を入力する
- 郵便料金を支払う(料金後納・クレジットカード払い)
- 内容証明郵便として発送され、後日差出人には謄本が郵送される
【参考元】e内容証明(電子内容証明)|日本郵便
e内容証明の差出方法は3種類ありますが、初めて利用する場合は手軽に発送できる「かんたん差出し」がおすすめです。
- かんたん差出し:一人の差出人が一人の受取人に、1通のe内容証明郵便を送る方法
- 差出し:複数のe内容証明文書を一人の受取人に一括で送ったり、同じ内容のe内容証明文書を複数の受取人に送ったりする方法
- 差込差出し:文書ファイルと差込データファイルを用意し、最大100通のe内容証明を一括で送る方法
内容証明郵便の料金・発送費用
内容証明郵便を送る場合、通常の内容証明郵便とe内容証明では料金が異なります。
ここでは、内容証明郵便の発送費用についてケースごとに解説します。
通常の内容証明郵便の場合
通常の内容証明郵便の場合、以下のような基本料金・内容証明の加算料金・一般書留の加算料金が発生します。
さらに、配達証明サービスを利用する場合は、配達証明の加算料金も発生します。
| ①基本料金 | 【定形郵便物】 ・50gまで:110円 【定形外郵便(規格内)】・50g以内:140円 ・100g以内:180円 ・150g以内:270円 ・250g以内:320円 ・500g以内:510円 ・1kg以内:750円 |
|---|---|
| ②内容証明の加算料金 | ・1枚目:480円 ・2枚目以降:1枚あたり+290円 |
| ③一般書留の加算料金 | ・損害要償額が10万円まで:480円 ・さらに5万円ごとに+23円(上限500万円) |
| ④配達証明の加算料金 | ・差出時に依頼する場合:350円 ・差出後に依頼する場合:480円 |
【参考元】手紙・はがき|郵便局、オプションサービスの加算料金一覧|郵便局
たとえば「内容文書1枚・定形郵便物(20g)・損害要償額10万円・配達証明あり(差出時に依頼)」という場合、料金は以下のとおりです。
| 基本料金(110円)+内容証明の加算料金(480円)+一般書留の加算料金(480円)+配達証明の加算料金(350円)=1,420円 |
e内容証明(電子内容証明)の場合
e内容証明の場合、以下のような郵便料金・電子郵便料金・内容証明料金・謄本送付料金・一般書留料金が発生します。
料金 郵便料金 (1)郵便料金 110円 内容証明関連料金 (2)電子郵便料金 ①電子内容証明文書1枚目 19円 ②電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) 6円 (3)内容証明料金 ①電子内容証明文書1枚目 382円 ②電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) 360円 ③同文内容証明(2通目以降1枚目) 210円 ④同文内容証明(2通目以降2枚目以降1枚ごとに(100通まで)) 210円 (4)謄本送付料金 ①通常送付 304円 ②一括送付(受取人数100人まで) 503円 (5)一般書留料金 480円
たとえば「e内容証明文書1枚・通常送付」という場合、料金は以下のとおりです。
| 郵便料金(110円)+電子郵便料金(19円)+内容証明料金(382円)+謄本送付料金(304円)+一般書留料金(480円)=1,295円 |
内容証明郵便を発送する場合の注意点
ここでは、内容証明郵便を利用する際に注意すべきポイントについて解説します。
内容証明郵便自体に法的拘束力はないため無視されることもある
内容証明郵便には、債権の時効完成を阻止する効果や法的手続きの際に証拠になるなどのメリットがありますが、内容証明郵便自体に法的拘束力はありません。
たとえば、配偶者の不倫相手に対して「慰謝料として400万円請求します」などと記載した内容証明郵便を送っても、不倫相手側は無視することも可能です。
内容証明郵便は意思表示の手段としては有効ですが、実際に問題が解決するかどうかは相手次第という部分もあり、思うような結果にならないおそれもあります。
内容文書以外の書類や物品を同封することはできない
内容証明郵便を送る際、封筒に入れられるのは内容文書のみです。
契約書の写しや写真などの内容文書に関連する資料も送りたい場合は、別の郵便で送る必要があります。
発送する際は配達証明サービスを利用したほうが安心
内容証明郵便を送る際は、配達証明を付けておくことをおすすめします。
内容証明郵便では「郵便物を発送した」という事実は証明できますが、「郵便物が配達された」という事実は証明できません。
配達証明を付けて内容証明郵便を送ることで、明確な配達日や郵便物が配達された事実を証明することができ、より確実な証拠を残すことが可能です。
内容証明郵便を受け取り拒否・無視された場合の対処法
内容証明郵便を送っても、なかには相手が無視して一切対応してくれなかったり、受け取りを拒否して返送されたりすることもあります。
内容証明郵便を送ってもうまくいかない場合は、以下のような対応を検討しましょう。
弁護士に依頼して弁護士名義で再送する
弁護士なら内容証明郵便の作成手続きを依頼でき、弁護士名義での送付が可能です。
弁護士名義で再送してもらうことで、こちら側の本気度が相手に伝わり、相手が「このまま無視していると本当に裁判になるかもしれない」などと考えたりして事態が進展する場合もあります。
もし弁護士名義で再送しても事態が進展しなかったとしても、弁護士ならその後の対応も引き続き依頼でき、問題解決のために尽力してくれます。
特定記録郵便を発送する
特定記録郵便の場合、内容証明郵便とは違って受取人のポストに投函され、受取人の受領印やサインは必要ありません。
内容証明郵便が受け取り拒否などで返送されてしまった場合でも、同じ内容の書面を特定記録郵便で送ることで受取人のもとに配達され、「意思表示が届いた」と判断されやすくなります。
内容証明郵便のメリット・デメリット
ここでは、内容証明郵便の主なメリット・デメリットについて解説します。
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便を利用することで、主に以下のようなメリットがあります。
- 裁判の際に有効な証拠となる
- 債権の時効完成が6ヵ月間猶予される
- 相手に対して心理的なプレッシャーを与えることができる など
「迷惑行為や違反行為に対して警告したい場合」や「未払いの債権を回収したい場合」など、さまざまな場面で内容証明郵便の送付が有効です。
内容証明郵便のデメリット
一方、内容証明郵便には以下のようなデメリットもあります。
- 発送費用がかかる
- 内容文書以外のものは同封できない
- 相手が受け取りを拒否した場合は返送される
- 内容証明郵便を送っても無視される可能性がある など
内容証明郵便自体に法的拘束力はないため、内容証明郵便を送ったからといって必ずしも問題解決につながるとはかぎりません。
場合によっては受け取りを拒否されたり無視されたりすることもあり、その場合は裁判などのほかの手段で解決を図ることになります。
さいごに|内容証明郵便を送るなら弁護士に依頼するのがおすすめ
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような内容の郵便物を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便は裁判で主張立証する際に証拠として活用でき、内容証明郵便を送るだけで相手がプレッシャーを感じて要求に応じてくれたりする場合もあります。
パソコンでの作成やインターネット上での発送も可能ですが、文字数や行数などの細かい決まりがあるうえ、個々の事情によって記載すべき内容は異なります。
弁護士なら以下のようなサポートが望めるため、内容証明郵便の作成が不安な方は相談してみることをおすすめします。
- 内容証明郵便の作成手続きを一任できる
- 弁護士名義で内容証明郵便を送ってくれる
- 不備なく効果的な内容文書を作成してくれる
当社が運営する「ベンナビ」では、各分野に強い全国の法律事務所を掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、まずは一度相談してみましょう。