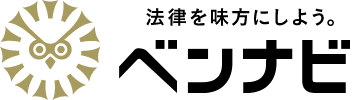保護責任者遺棄罪とは?構成要件や罰則・刑罰などを解説

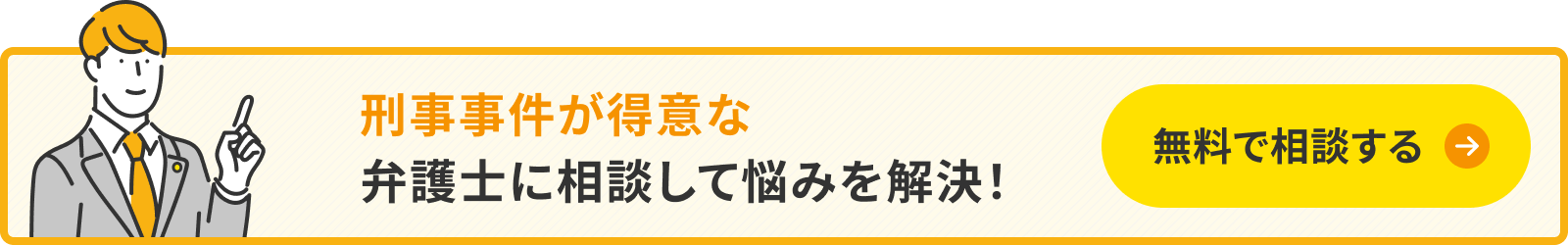

保護責任者遺棄罪は自身が保護すべきだった人物を遺棄、もしくは生存に必要な保護をしなかった場合に成立する犯罪であり、懲役刑の対象とされています。
具体例として、子どもにとって親の介護は放棄できるものではなく、介護が必要な状態の高齢者へのケアを放棄すると罪に問われる可能性が高いでしょう。
では、責任をもって介護をおこなった末に亡くなってしまった場合であっても、保護責任者遺棄罪に問われるのでしょうか。
本記事では、保護責任者遺棄罪はどのような場合に成立するのか、逮捕されるとどうなるかなどについて解説します。
保護責任者遺棄罪とは?
保護責任者遺棄罪とは、老年者・幼年者・身体障害者・病人など、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪です。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
つまり、保護を必要とする方が身近にいるにもかかわらず、何もせず生命や身体に危険を及ぼすことを罪と定めており、法定刑は3ヵ月以上5年以下の懲役とされています。
保護責任者遺棄罪と似たものに遺棄罪・過失致死傷罪・救護義務違反などがありますが、これらとどのような違いがあるのでしょうか。
遺棄罪との違い
遺棄罪は、物理的に助けを必要とする者を移動させた場合に成立します(刑法第217条)。
一方、保護責任者遺棄罪の場合は物理的に移動させるようなケースに限らず、どこかに置き去りにしてくるようなケースも含まれます。
ここでいう置き去りとは、たとえば母親が生活能力のない幼い子どもを自宅に放置しているケースなどが該当します。
量刑に関しても、保護責任者遺棄罪と比べて軽く、一年以下の懲役となっています。
過失致死傷罪との違い
過失致死傷罪は殺害の意思がない過失状態で相手を死亡・負傷させてしまうことです。
仮に故意がなくても、死亡させたという結果が出ている場合は逮捕されて刑事処分を下されるおそれがあります。
罰則については、過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金と、保護責任者遺棄罪と比べ軽くなっています。
なお、保護義務のある人物が要扶助者を死亡あるいは負傷させてしまった場合は、保護をした経緯があれば過失致死傷罪になるケースがあると理解しておきましょう。
救護義務違反との違い
自転車を含めた車両によって人身事故を起こした場合、加害者はただちに車両の運転を停止し、負傷者を救護して道路における危険を防止するなど、必要な措置を講じる「救護義務」が発生します。
そのため、たとえ相手方と直接接触していなかったとしても、相手方の直前を通過したり、接近して相手が急ブレーキをかけたりして転倒した場合、その場で停止せずに現場から立ち去る行為は救護義務違反が問われる可能性があります。
必要な措置をおこなわずに,その場を立ち去った場合は(いわゆるひき逃げ)、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
この場合、保護責任者遺棄罪も成立すると認識されますが、現場を確認せずにその場から立ち去るひき逃げは、保護責任者遺棄罪ではなく救護義務違反に該当するケースが少なくありません。
しかし、交通事故を起こして一度被害者に声をかけ、路肩に移すなどの救護処置をおこなってから警察に通報せず逃走した場合は、救護措置をした時点で保護義務が生じたとして、保護責任者遺棄罪が成立する可能性も考えられます。
保護責任者遺棄罪の構成要件
保護責任者遺棄罪の構成要件は次のとおりです。
- 老年者・幼年者・身体障害者・病者を遺棄、または保護しなかったこと
- 保護責任者であること
保護責任者に当たるかどうかは、法令の規定や契約、慣習などさまざまな根拠から決まります。
保護責任者遺棄罪の目的は「扶助を必要とする者」の保護
保護責任者遺棄罪の目的は、「扶助を必要とする者の保護」です。
ここでいう「扶助を必要とする者」には老年者や幼年者、身体障害者、病者といったが含まれます。
そして「扶助を必要とする」とは、他者の扶持助力がなければ日常生活を営むべき動作を自分自身でおこなうできない状態と解するのが古い判例の立場です(大審院大正4年5月21日判決)。
ただ、処罰範囲を限定する観点から、自らが生命に対する危険に対処できない状態であることを指す見解もあります。
いずれにしても扶助の必要性は、本人の知的能力や運動能力などを総合的に考慮して判断されます。
なお、病者とは身体的や精神的に健康状態が害されている状態にある者をいいます。
慢性的な疾病状態にある者だけでなく、高度の酩酊者や覚醒剤により錯乱状態にある者、衰弱状態にある若者、交通事故によって重傷を負い歩行不能になった者なども含まれます。
「遺棄」に当てはまる行為
遺棄に当てはまる行為は、被害者を安全な場所から危険な場所に移動させる、被害者が危険な場所にいるにもかかわらず、そのまま放置するなどがあります。
具体的には、次のような行為が「遺棄」とみなされ、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
- 交通事故を起こしたのちに被害者を自動車に乗せて事故現場を離れたが、被害者を薄暗い車道に放置した
- 病気により日常生活が困難な妻を残して夫が失踪した
- 幼い子どもを自宅に置き去りにした
ほかにも、物理的に移動させるだけでなく母親が生活能力のない子どもを自宅に置いているなど、どこかに置き去りにしてくることも遺棄に該当します。
「保護しなかったこと」に当てはまる行為
生存に必要な保護をしなかったこと(不保護)に当てはまる行為は、場所的隔離することなく保護すべき者を保護しないことをいいます。
一例として、次のようなケースでは、保護すべき者の生存に必要な保護をしなかったとして、保護責任者遺棄罪が成立する可能性が考えられます。
- 同居している重病人をまったく看病せずに放置した
- 同居している子どもへ適切に食事を与えなかった
なお、具体的に必要な保護が何かについては、保護者との関係や保護を必要とする理由など、具体的な状況と照らし合わせて総合的に判断されます。
保護責任者に含まれるのはどこまで?
保護責任者とは、法令や慣習、条理、契約などに基づいて要保護者を保護する責任のある人物をいいます。
具体的には、子どもを育てている親、高齢者の介護を請け負っている介護士やベビーシッター、自宅に病人を引き取った人などが該当します。
一方、要保護者とは幼い子どもや老人、身体障害や病気で身動きが自由にとれない人など、扶助を必要とする人物のことをいいます。
このように、特定人物の生命・身体を危険から守る必要がある場合には、保護責任に含まれると認識してよいでしょう。
保護責任者遺棄罪で逮捕されるとどうなる?罰則や刑罰は?
保護責任者遺棄罪で逮捕され有罪になると、どのような罰則や刑罰が定められているのでしょうか。
保護責任者遺棄致死罪|3年以上の有期懲役
保護責任を遺棄し相手を死亡させてしまった場合、保護責任者遺棄致死罪が問われます。
保護責任者遺棄致死罪は傷害致死罪(刑法第205条)と比較して重い刑に処断されるため、この場合は3年以上の有期懲役が科されます。
保護責任者遺棄致傷罪|15年以下の懲役
保護責任者が遺棄行為をして、さらに相手に傷害を負わせた場合は保護責任者遺棄致傷罪に問われます。
この場合、15年以下の懲役が科されます。
被害者が死亡する危険性を認識していた場合は殺人罪に問われる可能性も
被害者が死亡したケースにおいて、遺棄または不保護により被害者が死亡する可能性の具体的な危険を認識していたと判断された場合、保護責任遺棄罪に加えて殺人罪に問われる可能性があります(刑法第199条)。
仮に保護責任者遺棄致死罪の成立要件を満たさなかった場合でも、不注意によって死亡させてしまった、あるいは殺意をもって死亡させた場合は、過失致死や殺人罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の刑罰は50万円以下の罰金、そして殺人罪と保護責任者遺棄罪は観念的競合となるため、さらに重い殺人罪の法定刑として死刑または無期、もしくは5年以上の懲役により処断されることがあります。
保護責任者遺棄罪で逮捕された事例・判例
ここでは、実際に保護責任者遺棄罪で逮捕された事例や判例を紹介します。
幼児を置き去りにして死亡させた事例・判例
幼児を置き去りにして死亡させた事例として、令和3年に起きた事件があります。
この事例では、被告人である母親が当時3歳になる子どもを部屋の中に置き去りにして知人男性と旅行へ出かけました。
さらに、被告人は被害児がいる部屋の扉を閉めてその扉をソファで固定し、玄関ドアを外側から施錠して立ち去りました。
被害児を部屋内に放置して遺棄し、飲食物を適時与えることやおむつの着脱、医師の診察などの医療措置を受けさせず、必要な保護をしなかった結果、高度脱水症と飢餓によって死亡させました。
この保護責任遺棄致死の犯行は非常に悪質かつ身勝手な行動であること、ほかの方に世話を頼んだり子どもを一緒に連れて行ったりしなかったことから、東京高等裁判所は懲役8年の判決を下しました。
子どもに食事と与えずに餓死させた事例・判例
子どもに食事を与えずに餓死させた事例として、平成31年に起きた事件を紹介します。
被告人である母親は一人で3人の子どもを養育していたものの、ママ友である人物から指示を受け、子どもらの食事の量や回数を減らしたり、日中一人で留守番をするように言いつけたり、多数回にわたり連続で数日間子どもらに一切食事を与えないなどの行為をおこないました。
ママ友である人物は被告人と子どもらの生活全般を実質的に支配しており、その結果子どもたちは重度の低栄養状態になり、当時5歳になる三男を餓死させました。
母親は保護する責任を遺棄したため、保護責任者遺棄致死罪の罪などに問われました。
しかし、この犯行に至る経緯を見ると、被告人は子どもたちに十分な食事を与えないことが本意ではなく、ママ友である共犯者の嘘に騙され、手元の金を全て巻き上げられ、共犯者に依存しなければ食糧も手に入らない状況に陥っていたことが判明したのです。
被害者自身も食事や睡眠が相当不足している状況にあり、判断能力も低下していたなか、共犯者の指示に従わざるを得ないと考え、犯行に及んだことが認められました。
そして、令和4年6月に福岡地裁により被告人である母親は懲役5年、ママ友である共犯者は子どもを保護する責任はないものの、母親を支配して犯行に加担したため懲役15年が確定しました。
高齢者を放置して死亡させた事例
高齢者を放置して死亡させた事例として、平成27年に起きた事件を紹介します。
この事例では、同居する81歳の母親を放置して死亡させたとして、長男が保護責任遺棄致死罪に問われました。
息子は母親を介護する責任があるにもかかわらず、極度に衰弱した母親に食事を食べさせることもなく介護や救急車を呼ぶことを拒否したうえ、母親は入院中などの嘘をついて台所に放置するなど、母親の食事量が減少し極度に衰弱していることを知りながらも必要な医療措置を受けさせませんでした。
その結果、栄養失調で死亡させ、さらに遺体を放置したとしています。
母親が生命に関わる危険な状態と明確に認識していたこと、埋葬準備もおこなわずゴミが散乱する台所に放置したのは死体遺棄罪に当たるとして、奈良地裁より懲役3年が言い渡されました。
酔っぱらいを放置し、死亡させた事例
酔っ払いを放置し死亡させた事例として、平成29年に起きた事件を挙げます。
近畿大学2年(当時20歳)の男子大学生が、テニスサークルのメンバー約10人と共に居酒屋でおこなわれた飲み会に参加し、開始1時間ほどでビールのほか、ウォッカなどショットグラスで20杯ほどを次々と一気飲みして泥酔昏倒しました。
男子大学生は大きないびきをかきながら寝てしまい、反応を示さなくなったことから飲み会に参加していなかった当時大学2年の5名の学生が介抱役として呼び出されました。
急性アルコール中毒の疑いから上級生に処置を相談したが不要と判断されたため、誰も救急車を呼ばず病院にも連れて行かず、男子学生を近くに住む別の学生の家に運びその場は解散しました。
しかし、男子学生は明け方に気がついた時点ですでに呼吸をしておらず、すぐに病院に搬送されたものの死亡が確認されました。
死因は吐いたものが喉に詰まったことによる窒息死で、男子学生の両親は処置を不要と判断した上級生と介抱役の学生5名を保護責任遺棄致死罪の容疑で告訴しました。
そして、大阪地裁により救護隊の出動を要請するなど救護する義務があったものの、適切な救護をおこなわなかったこと、かつ学生宅に運び入れた学生に対しても放置すれば死亡する危険があると認識できたとして、元学生16人に賠償を命じました。
保護責任者遺棄罪で逮捕されたあとの流れ
ここでは、保護責任者遺棄罪で逮捕されたあとの刑事手続きの流れを説明します。
刑事手続きは刑事訴訟法により、ある程度決められた流れでおこなわれます。
①逮捕後に警察の取り調べを受ける
保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されると、まずは警察の取り調べを受けます。
この段階の取り調べ期間は48時間以内と決められており、逮捕後はすぐに当番弁護士制度を利用できます。
②検察に送致後、勾留請求をされる
検察からの捜査が終了すると検察に身柄が移されるのですが、これを送致といいます。
検察に送致後、被害者は検察からの捜査を受けますが、これは24時間以内と決められています。
また、警察を含め検察の捜査が終了するまでの最大72時間は家族でも面会できません。
捜査の結果、過失致死罪などに該当する場合は拘束期間は短くなることがあり、保護責任者遺棄罪であれば拘束期間が長引くことが予想されます。
検察官が加害者に罪証隠滅または逃亡のおそれがあるため身柄拘束を継続すべきと判断した場合は、裁判官に対して勾留請求をおこないます。
裁判官により勾留理由と必要性が認められると判断された場合、勾留状を発します。
逮捕72時間以内に勾留状が発せられなければ被害者は釈放されます。
③最大20日間、勾留される
裁判官により勾留状が発せられた場合、被害者の身柄拘束は逮捕から起訴前勾留に切り替わり、最長20日間勾留されます(刑事訴訟法第208条)。
なお、起訴前勾留の期間中は逮捕期間と同様に取り調べが実施されます。
④検察によって起訴・不起訴が判断される
勾留期間中を合わせ逮捕後23日以内の間に、捜査の結果を踏まえて検察官によって基礎や不起訴が判断されます。
この起訴と不起訴の分かれ目は非常に重要で、不起訴処分を獲得するにはいかに適切な弁護活動をおこなうかに重きが置かれています。
保護責任者遺棄罪の場合、保護責任者遺棄罪以外の罪でも起訴されてしまう可能性があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
不起訴処分、起訴猶予処分の場合は釈放される
検察官が犯罪事実の立証が困難である、もしくは社会における更生を促すべきと判断すると、不起訴処分や執行猶予処分になります。
保護責任者遺棄罪の決定刑は懲役刑のみであるため略式起訴の対象外であり、公判請求または不起訴処分のいずれかがおこなわれます。
⑤起訴された場合は公判手続がされる
起訴された場合は起訴前勾留から起訴後勾留に切り替わり、引き続き被告人の身柄が拘束されます。
ただし、被告人や弁護士、親族は裁判所に対して保釈請求ができます。
保釈が認められると、裁判所に保釈保証金を預けることを条件として、一時的に身柄が拘束されます。
検察官による正式起訴から1ヵ月ほど経過したあと、裁判官にて公判手続がおこなわれます。
公判手続は、検察官が犯罪事実を立証して被告人が反論する形で進行し、公判手続きの審理が熟した段階で裁判官から判決が言い渡されます。
その判決に対して、高等裁判所への控訴が認められます。
⑥有罪になると刑が執行される
公判手続において有罪判決が確定した場合、被告人に対して刑が執行されます。
ただし、保護責任者遺棄罪の場合は、科された懲役刑の期間が3年以下であれば執行猶予が付されることがあります。
保護責任者遺棄罪で逮捕されたら早急に弁護士に相談を
保護責任者遺棄罪で逮捕されたとき、もしくは容疑をかけられた段階ですぐに弁護士へ相談してください。
自分の行為が保護責任遺棄罪に該当するのか、それともほかの罪に該当するかは、細かい状況や経緯などがわからなければ判断できません。
また、取り調べでの供述内容は検察官による起訴や不起訴の判断、刑事裁判の判決における考慮要素になるため、被害者に黙秘権があることを踏まえたうえで供述する内容は慎重に考えなければなりません。
これらを弁護士に相談することで、取り調べに関する基本的な知識やルール、心構えなどに対して具体的なアドバイスを受けられます。
さらに、刑事手続きの流れについて説明が受けられるだけでなく、逮捕されている場合の家族との窓口にもなってもらえます。
警察や検察による取り調べを適切に対処して早期解放を目指すためにも、早急に弁護士に相談してください。
さいごに
保護責任者遺棄罪は重大な犯罪であるため、重い刑事罰が科される可能性があります。
また、保護責任者遺棄罪の刑罰が非常に重いだけでなく、殺人罪の成立が争われるケースもあり、不起訴処分や刑の減軽を得ることは決して容易ではありません。
なお、刑事事件は経験豊富な弁護士によるサポートが必要不可欠です。
早い段階での弁護活動が重要であるため、まずは初回相談無料などの法律事務所を活用して相談しましょう。