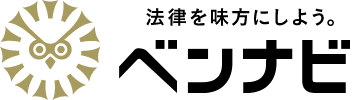遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点


遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄する(受け取らない・請求しない)こともできます。
ただし、遺留分は被相続人であっても奪うことができない権利なので、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ遺留分放棄が認められないようになっています。
今回は、遺留分放棄の具体的な流れと注意点について、被相続人の生前に行う場合と死後に行う場合の違いも交えてご紹介いたします。
遺留分の放棄とは|生前の手続きには家庭裁判所の許可が必要
遺留分の放棄とは、一定範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分である「遺留分」の権利を放棄することを言い、具体的には「遺留分を受け取らない」「遺留分を請求しない」ことを意味します(民法1043条)。
遺留分が問題になるのは、特定の相続人や第三者が遺産の大半を取得するような不公平な遺言が残されているケースが典型例で、こういった場合に遺産の最低限の取り分を侵害されている人が遺留分を請求して一定割合の遺産を確保するのが「遺留分減殺請求」ということになります。
まずは、遺留分放棄の基礎知識を整理してみましょう。
遺留分放棄が問題になるケース
遺留分放棄が問題になるのは、次のようなケースです。
- 相続に関わりたくないが、相続放棄をするのも面倒くさい
- 離婚した親について生前にできるだけ相続対策をしてトラブルを避けたい
- 事業承継にあたって特定の相続人に株式を集中させたい
遺留分放棄は、遺留分権利者が遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権)を放棄することを言います。
遺留分権利者は被相続人の配偶者・子およびその代襲者・直系尊属に限られ、実際にその相続において法定相続人に該当する人だけが請求権を有するので、例えば被相続人の死亡時に配偶者と子が相続人になる場合には、被相続人の直系尊属は遺留分権を持たないことになります。
なお、遺留分放棄はあくまで遺留分権利者が自主的に遺留分を辞退するための制度なので、被相続人や他の相続人がこれを強要したり、働きかけることは絶対に止めましょう。
相続放棄との違い
遺留分放棄も相続放棄も相続における一定の権利を拒絶する点では共通しますが、いくつか大きな違いがあります。
|
遺留分放棄 |
相続放棄 |
|
|
内容 |
遺留分減殺請求権の放棄 |
相続の拒絶 |
|
効果 |
遺留分が請求できなくなる |
最初から相続人でなかったものとして扱われる |
|
相続権 |
残る |
なし |
|
遺留分 |
なし |
なし |
|
他の相続人への影響 |
特になし (他の相続人の遺留分は増えない) |
同順位の相続人の相続分・遺留分が増加する 他に同順位の相続人がいなければ、次順位の相続人へ相続権が移る |
|
被相続人への影響 |
自由に処分できる財産が増加する |
特になし |
|
代襲相続との関係 |
遺留分放棄後に代襲相続が発生すると、代襲相続人の遺留分もなくなる |
特になし (相続放棄で代襲相続は発生しない) |
|
放棄できる期間 |
被相続人の生前~死後(遺留分権がある期間) ※生前の放棄には家庭裁判所の許可が必要 |
被相続人の死後、自己のための相続開始を知ってから3ヶ月間に限られる ※例外的に期間が延長できる場合もある |
簡単に言えば、遺留分を放棄しても相続権は残りますが、相続放棄をすると相続権・遺留分がなくなるということになります。
その結果、遺留分放棄によって他の相続人の遺留分が増えることはありませんが、相続放棄は相続人が最初から1人いなかったものと同じですから、他の相続人の相続分や遺留分が増える場合があります。
また、遺留分放棄をした相続人から代襲相続が発生する可能性はありますが、相続放棄は代襲原因に該当しないため、相続放棄者からの代襲相続は発生する余地がないという違いもあります。
要は、遺留分放棄をしても法定相続分や指定相続分を受け取れる可能性はありますが、相続放棄をしてしまうと一切の財産を受け取ることはできなくなるということです。
遺留分を放棄するとどうなるか
遺留分放棄は、放棄者自身への効果と、放棄者以外の相続人への効果の違いを理解することが大切です。
(遺留分の放棄)
第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
(引用元:民法1043条)
遺留分放棄者自身への効果
遺留分を放棄すると、放棄した遺留分権利者は遺留分の権利を失うことになります。
したがって、後日やっぱり遺留分が欲しいと思った場合には、生前の放棄の場合は家庭裁判所に審判の取消しを請求し、死後の放棄の場合で他の相続人に放棄する旨を伝えてしまった場合は撤回を打診することになるでしょう。(死後の放棄の場合で単に遺留分を請求しないでいただけの場合には、減殺請求のできる期間内であれば通常と同じように請求することもできるかと思います。)
なお、遺留分を放棄しても相続権は残りますし、その結果として債務も相続することになります。
相続自体を拒絶したい場合には、遺留分放棄ではなく相続放棄や限定承認の利用を検討することをおすすめしますが、こちらの方法は相続開始から3ヶ月の期間制限がありますので、速やかに準備に取り掛かることが大切です。
遺留分放棄者以外の相続人への効果
民法1043条2項の通り、遺留分の放棄は他の相続人の遺留分に影響を及ぼさないため、誰かが遺留分を放棄したからといって他の人の遺留分が増えることはありません。
そういう意味では遺留分放棄者以外の人にはあまり関係のない行為になるのですが、例外的に「被相続人の生前に遺留分を放棄した人に代襲相続が発生した場合」だけは、遺留分放棄の効果が代襲相続人へ承継されることになります。
代襲相続は、被相続人の生前に相続放棄以外の理由(相続欠格・相続廃除・死亡)によって被相続人の子(または兄弟姉妹)が相続権を失った際に、この子(または兄弟姉妹)の子が代わりに相続権を承継する制度をいい、遺留分の放棄が影響するのは「被相続人の子からの代襲相続」に限られます。
代襲相続人は、被代襲者が有していた以上の権利を取得することはありませんので、被代襲者が有効に遺留分を放棄していた場合には、代襲相続人となった子の子(被相続人の孫)にも遺留分権は承継されません。
被相続人への効果はある
また、遺留分放棄の結果として、被相続人が自由に処分できる財産が増えることになります。
例えば相続人が配偶者と子1人だとして、被相続人が全財産を愛人に譲るという遺言を残していたとします。
このとき、財産の1/2は配偶者と子の遺留分(それぞれ1/4ずつ)として確保されることになり、被相続人が自由に処分できる財産は1/2に留まります。
しかし、配偶者が遺留分を放棄していた場合、財産の1/4だけが子の遺留分となりますから、残りの3/4については遺言通り愛人に譲ることができるようになります。
遺留分放棄を選択する理由の具体例
遺留分放棄は、被相続人の生前・死後どちらでも行うことができるため、気にする方もそれなりに多いかと思います。
遺留分放棄を選択するに至った具体的な理由としては、冒頭で述べた事例が典型例になりますが、共通して言えるのは「遺留分を請求したくない」という強い事情があるという点です。
遺留分は、遺留分権利者が潜在的に有する遺産の取り分なので、理論上は遺留分権利者に原始的に帰属する財産ということになりますが、実際は侵害された限度で権利者が請求して取り返さなければ手元に戻ってくるわけではありません。
そのため、よほどの事情がなければわざわざ遺留分放棄を選択する必要はないのです。
遺留分放棄を選択する理由としては、「相続自体にあまり関わりたくない」、「相続での面倒を減らしたい」、「他の相続人と揉めたくない」、「他の相続人のためにできることをしたい」といった事情が根本にある場合が多いです。
例えば、離婚した父の相続で前婚の子が相続人になる場合に再婚後の子と顔を会わせたくないから遺留分を請求しないというケースや、親の介護に関われなかった子が献身的に介護に関わっていた兄弟に気兼ねなく遺産を受け取ってもらいたいというケース、親不孝をしていた自覚があるため積極的に遺産を受け取る気がなく遺言の際に遺留分を気にしてほしくないケースなどが挙げられるでしょう。
このように、遺留分の放棄を選択する事情は様々で、相続人間の仲が悪くない場合でも行われることがありますが、被相続人の生前の遺留分放棄は、放棄に至った事情の正当性や被相続人からの対価などを充分に審査して許可されることになりますので、なんとなく放棄したいと思っているに留まる場合には、被相続人の死後の遺留分放棄を検討するのが良いでしょう。
生前に遺留分放棄をする場合の手順
被相続人が生きている間に遺留分放棄をしたい場合には、家庭裁判所に申立てをし、許可を得ることになります。
というのも、遺留分は被相続人であっても簡単には奪えない権利なので、遺留分権利者の真意による放棄なのか、それとも何らかの強要や働きかけがなされた結果による放棄なのかを吟味する必要があるからです。
生前に遺留分放棄をする場合には厳しい条件が課せられるので、ここで詳しく見ていきましょう。
手順
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に「遺留分放棄の許可を求める審判」を申し立てます。
その際、申立書に被相続人の戸籍謄本と申立人の戸籍謄本を添付し、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手を予納します。
申立書には財産目録も記載する必要があるので、被相続人と協力して財産調査を済ませたほうが簡単かもしれません。
申立書が受理されると、当事者からヒアリングをするため審問期日が通知され、その日に裁判所で面談が行われます。
遺留分放棄が許可されると、後からこれを撤回するのは非常に難しくなるので(原則として撤回できないと考えておくほうが無難です)、迷っている場合は審問の際に放棄をやめたほうが良いでしょう。
審問が終わると、家庭裁判所が遺留分放棄の許可または不許可を決定し、その旨の通知がきます。
遺留分放棄が許可された場合には、速やかに遺留分放棄の許可証明書を発行しておくと、相続が発生した際にスムーズかと思います。
注意点
被相続人の生前の遺留分放棄が許可されるか否かは、主に以下の3点から審査されることになります。
本人の真意に基づく希望なのか
被相続人や他の推定相続人、親族等から強要されての遺留分放棄でないか、充分に確認されることになります。
未成年者の場合は特にこの点に配慮がなされることが予想されますので、申立ての前によく話し合って考えを理解することが大切です。
放棄の理由の合理性と必要性
遺留分放棄の理由が「相続が面倒くさいからなんとなく放棄しておきたい」というような、漠然としたものだと不許可になる可能性が高いといえます。
「自分は疎遠で絶対に関わりたくない」といった強い希望や、「介護に関わった○○に気兼ねなく遺産を受け取って欲しい」、「障害のある△△のために使ってほしい」といった合理的な理由を踏まえて、説得力のある主張を行うことが大切です。
被相続人から放棄する遺留分権利者へ何らかの代償が支払われているか
特別受益としてある程度の贈与がなされている場合や、遺留分放棄と引き換えに贈与がなされることになっている場合には、代償性の観点からも遺留分放棄の許可が下りる可能性が高くなります。
遺産の前渡しといえるような贈与があれば、遺留分を放棄するに至った合理的な理由があると判断できますし、当然と言えば当然でしょうか。
なお、遺留分権利者が経済的に裕福であって遺産が必要ないといった事情では遺留分放棄の理由としては弱いと言えますし、結婚や縁談など何かの代償に遺留分放棄を希望するのも避けたほうが良いです。
こういった理由で遺留分放棄の許可を申し立てると被相続人等の介入があったとして①②について疑いがあると判断されるおそれがありますから、代償性についてもある程度は考慮が必要です。
死後に遺留分放棄をする場合の手順
被相続人の死後に遺留分放棄をしたい場合には、特に法によって規制されているわけではなく、決められた方式なしに自由に放棄を選択することができます。
死後の遺留分放棄は言い換えれば「私は遺留分は要らないですよ」「私は遺留分を請求しませんよ」という意思表示に他ならないので、相続人間で遺留分放棄の意思が伝われば充分かと思います。
ただし、安易に遺留分を放棄して、後からやっぱり欲しいとなってしまうと大きなトラブルになりますから、よく考えた上で選択することと、放棄する際にはきちんと文書などを作成したほうが無難でしょう。
手順
被相続人の死後に遺留分放棄をする場合には、①他の相続人に遺留分を放棄する旨を伝えるか、②遺留分減殺請求権の時効まで権利を行使しないでおくかの2つの方法が考えられます。
他の相続人に遺留分放棄を伝える
手っ取り早く遺留分放棄をしたいのであれば、他の相続人に対して遺留分を放棄する旨をきちんと伝えましょう。
後日の紛争を防止する意味でも遺留分放棄通知書などを作成して送付しておくのがおすすめですが、単に「私は遺留分を請求しない」と伝えるだけでも放棄としては成立すると思います。
遺留分減殺請求権が消滅するのを待つ
遺留分には元々1年の消滅時効と10年の除斥期間が設けられていますから(民法1042条)、この期限を超えれば自動的に遺留分の権利は消滅します。
要は、遺留分が請求できる期間中に一切この権利に手をつけないでおくことで、遺留分放棄の効果を生じさせる方法です。
遺留分減殺請求権は、一度消滅すると復活することはほぼありえませんので、急いで放棄する必要がないのであれば、相続内容が発覚してから1年間何もせずに黙っていれば良いかと思います。
注意点
死後の遺留分放棄の注意点としては、①安易な遺留分放棄がトラブルを拡大する危険があること、②生前の放棄と異なり決められた方式がないため、混乱を招きやすいことが挙げられます。
安易な遺留分放棄はトラブルの元
死後の遺留分放棄は家庭裁判所の許可も不要で、遺留分権利者が比較的自由に放棄を実行することができるため、安易に放棄を選択して後日それを翻すなど紛争を拡大するケースも少なからずあります。
また、口頭のみで遺留分放棄を伝えてしまうと、言った言ってないで余計なトラブルを招く可能性もありますので、被相続人の死後に遺留分放棄をする場合には、相続に関わる人全員にきちんと書面などで遺留分放棄をする旨を伝えたほうが良いでしょう。
なお、遺留分を放棄しても相続分を受け取る権利は残りますので、遺産分割協議の参加は必須となります。
生前の遺留分放棄と違って方式の規制がない
被相続人の生前の遺留分放棄と異なり、死後の遺留分放棄は方式の規制がありません。
そのため、遺留分権利者の自由な意思により、自由な方式で遺留分放棄を選択することができるわけですが、言い換えれば、適当に遺留分放棄を伝えてしまったり、遺留分を放棄するからと相続に関する他の相続人の言葉を無視し続けるなどしてしまうと、本人のあずかり知らぬところでトラブルが発生する危険もあるのです。
①とも関連しますが、被相続人の死後の遺留分放棄は、慎重によく検討してから選択することと、放棄の意思を伝える際には書面を利用すること、遺留分を請求しない=相続に一切かかわらなくて良いというわけではないことを、きちんと理解しておきましょう。
未成年の遺留分放棄の注意点
相続において、未成年者は単独で有効な行為をすることができないため、生前の遺留分放棄や相続放棄・限定承認、遺産分割協議といった手続きをする場合には、未成年者のために代理人を選任する必要があります。
このとき、法定代理人である親権者が代理人になれるケースもありますが、親権者も相続人になる場合や子が複数いる場合には、子と親権者、子と子の利害が対立することになるので、子1人ずつに特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人は、子の住所地の家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行って選任してもらうことになります。
申立ての際には申立書(書式|記載例)と未成年者の戸籍謄本、親権者または未成年後見人の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票、子と親権者の利害が衝突することの分かる資料(遺留分放棄の場合、相続人の内訳の分かる資料や遺留分放棄をしたい理由の分かる資料などになると思われます)などに加え、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
子と親権者の利害が衝突することの分かる資料については、具体的な事案によって異なる可能性がありますので、申立ての前に家庭裁判所に遺留分放棄のための特別代理人選任に必要な書類は何かを尋ねることをおすすめします。
なお、未成年者の遺留分放棄は選任された特別代理人が代わりに手続きすることになりますが、特別代理人は遺留分放棄についての代理権しか付与されませんから、生前に遺留分放棄をする場合には、死後の遺産分割協議等については再度特別代理人の選任が必要です。
まとめ
相続放棄とは異なり、遺留分の放棄は被相続人の生前から死後までいつでも選択することができますが、遺留分権利者の真意に基づく選択か否かが重視されるため、被相続人の生前の遺留分放棄はある程度の制約が課されることになります。
また、相続放棄はそもそも相続人としての権利を失うわけですが、遺留分の放棄は遺留分減殺請求権を失うにすぎないので、相続人としての他の権利や義務は残りますので、遺産分割協議などの相続手続きはきちんと関わる必要があることにも注意しましょう。