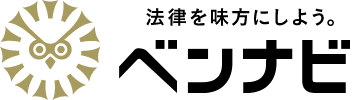遺留分の計算方法を徹底解説|遺留分計算の基礎知識まとめ


一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言いますが、遺留分は法律によって割合や計算方法が決まっています。
遺留分の計算は、基礎財産(相続財産)と総体的遺留分(相続財産に占める遺留分全体の割合)を元に、遺留分権利者である法定相続人の個別的な取り分を求めるという方法でなされますが、基礎財産の算定がやや難しいため注意が必要です。
今回は、遺留分の計算方法を徹底的に解説するとともに、相続の場でしばしば問題になる寄与分についても基本的な知識をご紹介いたします。
遺留分の計算方法とは
遺留分は、一定の法定相続人について認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度のことですが、その具体的な額の計算は民法に則って行われます(民法1028条以下)。
基本的には「相続開始時に被相続人が有していた財産」が算定の基礎になりますが、相続開始前の1年間にした贈与や期限を問わず特別受益と呼ばれる贈与についても算入されることから、遺留分算定の基礎財産を把握する際には注意が必要とされています(民法1029条・1030条)。
遺留分の基本的な計算式
遺留分の基本的な計算式は、
(【相続開始時の財産】+【贈与財産の価格】-【相続債務】)×総体的遺留分×各権利者の法定相続分割合
となっています。アンダーラインの部分がいわゆる「みなし相続財産」というもので、ここまでの説明では基礎財産というものに該当します。
総体的遺留分とは、基礎財産全体に占める遺留分の割合のことをいい、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています(民法1028条)。
総体的遺留分×各権利者の法定相続分割合によって実際の遺留分額が分かるため、この部分を「個別的遺留分」と呼ぶこともあります。
では次に、遺留分の計算必要な基礎財産に関する知識や遺留分に関する疑問について解説します。
遺留分の割合
遺留分の分配割合に関しては以下の表の通りになります。
| 相続人の組合わせ | 総体的遺留分 | 法定相続分割合 | |
|
配偶者のみ
|
1/2 | 配偶者のみなので、遺留分については100% | |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/4ずつ | ||
| 子2人 | 1/2 | 子 | 1/2ずつ |
| 配偶者+父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 |
| 父母 | 1/6ずつ | ||
| 父母のみ | 1/3 | 父母のみなので1/2ずつ | |
| 配偶者+兄 | 1/2 | 配偶者 | 遺留分について100%(相続分は3/4) |
| 兄 | 遺留分なし(相続分は1/4) | ||
そもそも遺留分が兄弟姉妹にないのはなぜ?
遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹を除く法定相続人すなわち「配偶者」「子など直系卑属」「父母など直系尊属」の3種類の人たちです。

遺留分制度は残された遺族の生活保障の側面を持つことから、「血が遠い」相続人である被相続人の兄弟姉妹には保障されていません。
相続において、兄弟姉妹は血族相続人の第三順位として法定相続人に数えられてはいるものの、旧民法下ではこれら被相続人と縁の薄い相続人が自己の権利を主張し泥沼の争いが起こることがしばしばあったため、現民法では兄弟姉妹の相続権をある程度制限しています。
したがって、遺留分を考える上でまず気をつけなければならないことは、遺留分を請求しようとしている人が遺留分権利者であるのかどうかということと、実際に遺留分が侵害されているかどうかということの2点になります。
なお、直系尊属については代襲相続はありませんが、直系卑属の代襲相続の際は遺留分の権利も代襲相続人へと承継されることになっています。
その際、代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の遺留分権を頭割りして承継することになります
例:孫2人が子の代襲者となる場合、遺留分権は1/2ずつ承継
遺留分を計算する際に基礎財産となるもの
遺留分算定の基礎財産には、「被相続人が相続開始時に有していた財産」に加え、「相続開始前1年間になされた贈与」および「遺留分権利者に損害を加えることを知っていながら行われた贈与」ならびに「特別受益」が含まれることになります(民法1030条・1044条・903条)。
言い換えれば、
- 相続開始前1年以内になされた生前贈与
- 遺留分権利者を害することを知っていながら行われた贈与
- 死因贈与
- 特別受益に該当する贈与
この4種類の贈与を考慮して遺留分を計算することになるということです。
①相続開始前1年以内になされた生前贈与
被相続人が死亡する前1年以内に契約が締結された贈与については、相手方が誰であるかを問わず、すべて基礎財産の算定に含まれます。
例えば被相続人が平成29年2月20日に死亡した場合、基礎財産に含まれる贈与は下記のようになります。
| 贈与契約の締結日時 | 相手方と金額 | 基礎財産に含まれるか否か |
| 平成27年1月1日 | 孫へ30万円 | × |
| 平成27年9月30日 | 弟へ20万円 | × |
| 平成28年2月18日 | 子へ30万円 | ×※特別受益に該当する場合は含まれる可能性あり |
| 平成28年4月15日 | 親友へ50万円 | ○ |
| 平成28年7月1日 | 配偶者へ100万円 | ○ |
| 平成28年12月31日 | 子へ100万円 | ○ |
②遺留分権利者を害することを知っていながら行われた贈与
当事者双方に客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき認識(加害の認識)があってなされた贈与については、相続開始前1年間のものでなくとも、すべて基礎財産の算定に含まれます。
このとき、加害の認識というのは「贈与財産の価格が残存財産の価格を超えることを知っていた事実のみならず、将来において、被相続人の財産に何らの変動がないこと、少なくともその増加のないことの予見」が必要とされており(大判昭和11年6月17日)、加害の認識については遺留分権利者に立証責任があります(大判大正10年11月29日)。
例えば、被相続人が死亡の5年前に愛人にめぼしい財産をすべて贈与した場合、配偶者や嫡出子に財産が残らないという認識が双方にあったとすれば、それらは遺留分権利者を害することを知っていながら行われた贈与ということになります。
③死因贈与
死因贈与とは、「私が死んだら妻に預金全額を与える」というような、死亡を条件として効果が発生する、生前に交わした贈与契約のことをいいます。
遺贈と似ていますが、遺贈は遺言によって遺贈者が一方的に行う単独行為であり、受遺者はその財産を受け取るか否かの選択が出来るのに対し、死因贈与の場合は当事者双方の同意があって初めて成立する諾成契約です(なお、贈与という名前ですが、相続税が加算されます)。
死因贈与の場合も、生前贈与と同様に、相続開始前1年間に契約が締結された死因贈与が基礎財産に含まれ、②についても双方に加害の意思がある場合は期限を問わず基礎財産に含まれると考えられています。
④特別受益に該当する贈与
共同相続人に対する贈与で特別受益に該当するものは、1年以上前の贈与であっても基礎財産にすべて算入されることになります(民法1044条・903条)。
相続分算定の場合は、持戻し免除の意思表示があればそれは遺産分割の際に考慮しないという運用がなされていますが、遺留分算定の際には持戻し免除の意思表示の有無にかかわらず、すべて遺留分算定の基礎財産に含まれることになります(大阪高判平成11年6月8日)。
なお、多額の特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされるため(民法939条)、相続開始前の1年間になされた贈与に限って遺留分算定の基礎財産に含まれると考えられています。
それでは、特別受益になりうる贈与とはどのようなものなのでしょうか?
遺留分と特別受益の関係
特別受益が遺留分算定の基礎財産に含まれるというのは前述のとおりですが、特別受益とはどのようなものを言うのか整理してみましょう。
大前提として、特別受益というのは「被相続人の生前の資産および生活状況に照らし合わせてそれが扶養の一部であると認められる場合は(特別受益に)該当しない」と考えられています。
例えば、年収3,000万円の被相続人が子に100万円の贈与を行うことは、扶養の一部として認められる可能性があり、そうなった場合には特別受益でなく通常の贈与として考えられることになります。
逆に、年収300万円の被相続人が配偶者に100万円の贈与を行うことは、扶養の範囲を超えると考えられそうですよね。
このように、特別受益は被相続人の経済状況によって判断が分かれることになるので、まずはその点を理解しましょう。
さて、実際に特別受益になり得る贈与としては、以下のものが考えられます。
①婚資等
結婚や養子縁組のために被相続人が負担した費用は、典型的な特別受益とされています。
ごく少額であった場合などは婚資であっても特別受益にならないとされることもあります。
②不動産の贈与
不動産はそれ自体が高額な財産なので、原則として特別受益に該当します。
③金銭・有価証券・金銭債権等の贈与
これらが相当額の贈与である場合には、原則として特別受益に該当します。
相当額というのは、小遣いや慰労金・礼金といった範囲を超えて、明らかに相続分の前渡しであると認められる金額のことをいい、例えば相続財産が1,000万円で子どもに800万円の贈与を行っていた場合などがこれに該当します。
④借地権の承継
借家権は原則として特別受益になりませんが、借地権に関しては、特定の相続人名義に変更することで借地権相当額の贈与とみなされ特別受益と判断される可能性が高いと言えます。
⑤高等教育のための学資等
義務教育でない高等教育(一般的には大学教育以上)に関しては、特別受益と判断される可能性があります。
ただし、被相続人の経済状況等に照らし、その程度の教育をするのが普通である場合には特別受益にはなりません。
留学等の費用負担も同様の判断が行われます。
具体例で考える遺留分の計算
それでは、実際に遺留分の計算をしてみましょう。
今回は、被相続人の財産が5,000万円あり、債務(ローン)が1,000万円残っているという例で、実際の計算を行ってみたいと思います。
遺留分の割合と計算
今回の例で、被相続人が愛人に全財産を譲るという遺言を遺している場合は、遺留分はそれぞれ下記のようになります。
| 相続人の組合わせ | 総体的遺留分 | 法定相続分割合 | 具体的な遺留分額 | |
|
配偶者のみ
|
1/2 | 配偶者のみなので、遺留分については100% | (5,000万円-1,000万円)×1/2=2,000万円 | |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円 |
| 子 | 1/4ずつ | 4,000万円×1/2×1/4=500万円ずつ | ||
| 子2人 | 1/2 | 子 | 1/2ずつ | 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円ずつ |
| 配偶者+父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 4,000万円×1/2×2/3=約1,333万円 |
| 父母 | 1/6ずつ | 4,000万円×1/2×1/6=約333万円ずつ | ||
| 父母のみ | 1/3 | 父母のみなので1/2ずつ | 4,000万円×1/3×1/2=約666万円ずつ | |
| 配偶者+兄 | 1/2 | 配偶者 | 遺留分について100%(相続分は3/4) | 4,000万円×1/2=2,000万円 |
| 兄 | 遺留分なし(相続分は1/4) | 遺留分なし | ||
なお、実際にあなたが遺留分額を計算する際には、「遺留分計算シート」というような遺留分概算ツールが使える場合があります。
弁護士事務所や司法書士事務所、税理士事務所等のホームページでこのようなツールを配布していることがありますので、興味がある方は探してみてはいかがでしょうか。
ただし、あくまで概算であることから、正確な数字でない可能性もあり得ます。
心配な場合は必ず専門家に相談し、場合によっては計算をしてもらうのがおすすめです。
生前贈与や特別受益に関する計算
今回の例で、相続人が配偶者・子2人であり、生前贈与や特別受益があった場合の基礎財産は下記のように計算します。
| 相続人 | 贈与等の有無 | 基礎財産へ算入されるか否か |
| 配偶者 | 死亡前1年以内に500万円の贈与あり | ○ |
| 子A | 住宅購入資金として1,000万円の贈与あり | ○ |
| 子B | 特になし | - |
⇒基礎財産は、(5,000万円+500万円+1,000万円)-1,000万円=5,500万円となります。
なお、特別受益には持戻し免除という制度がありますが、遺留分算定の際には適用されませんのでご注意ください。
遺留分に不動産が含まれる場合の計算方法
めぼしい財産が不動産だけの場合、通常はその不動産を相続した人に遺留分減殺請求を行うことが考えられます。
不動産の評価については「固定資産税評価額」「路線価」「地価公示価格」「地価調査標準価格」などの方法がありますが、遺留分減殺請求訴訟の場合は「相続開始時の取引価額」によるのが原則となっています(東京地裁平成24年10月12日)。
固定資産税評価額や路線価をそのまま使用してしまうと不動産評価額が時価よりも低くなることが多いので、不動産業者による査定を行って時価額を決定することもあります。
なお、相続財産が不動産だけの場合は、相続した人に対する遺留分減殺請求の結果、不動産の一部の返還を求めたり、遺留分を金銭で請求する(価額弁償)といった方法が考えられます。
遺留分と寄与分の関係
相続時の遺産の取り分について、相続分・遺留分と並んでしばしば問題になるのが寄与分(民法904条の2)です。
寄与分とは、共同相続人の中の特定の相続人の相続分を増やす制度で、認められるためには遺産分割協議で主張をし、話がつかなければ家庭裁判所での調停が必要になります。
ここでは、遺留分と寄与分の関係について簡単にご説明いたします。
遺留分と寄与分の違い
遺留分と寄与分の大きな違いは、遺留分が特定の相続人に必ず認められている最低限の遺産の取り分であることに対し、寄与分は相続分増加の考慮要素に過ぎないという点です。
つまり、遺留分は適正な主張であればもらえる可能性が非常に高いのに対し、寄与分は主張してももらえるとは限らないという違いがあります。
遺留分減殺請求は一方的な意思表示で効果を発生しますが(ただし、実際に遺留分が返還されるためには別途手続きが必要な場合もあります)、寄与分は遺産分割協議で主張し、認められない場合は調停等で主張しなければならないという制度でもあります。
そして、遺留分減殺請求には時効がありますが、寄与分については原則として時効という概念はありません。
被相続人の生前に特定の相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献(特別の寄与)をした場合に発生するのが寄与分です。
その事実があればいつでも主張はできるのですが、かといってあまりに昔の寄与である場合は、その後の財産の減少がある場合には寄与として扱われないという欠点もあります。
この点、遺留分は所定の期間内であれば行使できるので、このような側面からも両者の違いが窺えます。
寄与分の計算方法
寄与分が認められる要件としては、
- 共同相続人による寄与行為
- 寄与行為が特別の寄与に該当すること
- 被相続人の財産の維持または増加があり、寄与行為との間に因果関係があること
この3つの要素が必要です。そして、特別の寄与にあたるかどうかの判断基準は「無償性」「継続性」「専従性」「被相続人との身分関係」によって判断されます。
| 寄与パターン | 具体例 | 計算方法(参考) |
| 家事従事型 | 30年間家業に従事した子の場合の寄与分など | 寄与分額=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給付額 × (1-生活費控除割合) ×寄与年数 |
| 金銭等出資型 | 不動産の贈与 | 寄与分額=相続開始時の不動産額×裁量的割合 |
| 相続人の被相続人に対する不動産取得のための金銭贈与 | 寄与分額=相続開始時の不動産額×(出資金額/取得当時の不動産額) | |
| 不動産の使用貸権 | 寄与分額=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合 | |
| 相続人の被相続人に対する金銭贈与 | 寄与分=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合 | |
| 療養看護型 | 実際の療養看護 | 寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合 |
| 費用負担 | 寄与分額=負担費用額 | |
| 扶養型 | 現実の引き取り扶養 | 寄与分額=(現実に負担した額又は生活保護基準による額) ×期間× (1-寄与相続人の法定相続分割合) |
| 扶養料の負担 | 寄与分額=負担扶養料×期間 × (1―寄与相続人の法定相続分割合) | |
| 財産管理型 | 不動産の賃貸管理、占有者の排除、売買契約締結についての関与など | 寄与分額=(第三者に委任した場合の報酬額) × (裁量的割合) |
| 火災保険料、修繕費、不動産の公租公課の負担 | 寄与分額=現実に負担した額 |
なお、寄与分が認められた寄与者の相続分については、以下の算定式によって計算することになります。
| 寄与者の相続額= (相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格 |
分かりにくい遺留分の計算ポイントまとめ
以上が遺留分の計算についての基礎知識の全てですが、ここで最後にポイントを整理してみましょう。
遺留分の計算方法
遺留分の計算式は、
(【相続開始時の財産】+【贈与財産の価格】-【相続債務】)×総体的遺留分×各権利者の法定相続分割合
となっています。もっと簡単に言えば、「みなし相続財産×遺留分割合」ということになります。
<ポイント> 民法1028条、1029条ほか
- 相続開始時の財産=被相続人の死亡時点での財産
- 相続開始前1年間になされた贈与はみなし相続財産に含まれる(当然、遺贈も含まれる)
- 特別受益がある場合は、期間を問わずみなし相続財産に含まれる
- 被相続人に借金等がある場合は必ずこれを控除(マイナス)する
- 総体的遺留分=遺留分権利者全員の遺留分を足したもの(相続財産に占める遺留分全体の割合)
- 個別的遺留分=各遺留分権利者の具体的な遺留分
遺留分の請求方法と時効
①遺留分の請求方法
遺留分の請求は、遺留分を侵害している相続人等に個別に「遺留分減殺の意思表示」を行うことで効果を発揮します。
すなわち、「あなたが私の遺留分をこれだけ侵害しているので、その分を請求します(私の遺留分を侵害する○○円分を返してください)」という内容を相手に伝えることになります。
この際の手段は口頭や電話・メール等でも問題ありません。
ただし、後々調停や裁判になった際に証拠としても役に立つ内容証明郵便で行うのが一般的です。
②時効
遺留分には請求できる期限があり、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から1年間(消滅時効)、相続開始の時から10年間(除斥期間)で権利が消滅します(民法1042条)。
1年間の消滅時効に関しては期間内に一度でも遺留分減殺の意思表示を行っていれば問題ありませんが、10年間の除斥期間については時効を止める方法は一切ありません。
先延ばしにせず、遺留分侵害に気がついたらすぐに請求を開始するのがおすすめです。
<ポイント> 民法1042条
- ・遺留分請求先は「遺留分を侵害している相続人等」
- ・全員にまとめて請求はできず、侵害している人それぞれに個別に請求しなければならない(効果が相対的)
- ・請求の際には遺留分侵害額を明記する
- ・内容証明郵便で行うのが一般的
- ・1年間の消滅時効と10年間の除斥期間に注意
遺留分の放棄
遺留分は放棄することができますが、遺留分を放棄しても相続放棄と違い相続への権利は失いません。
①生前の放棄
被相続人の生前に遺留分を放棄したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
というのも、遺留分はそれなりの割合になることから、年長者等から遺留分放棄の圧力を掛けられる危険性があるため、このような運用になっています。
なお、生前・死後問わず遺留分放棄をした相続人がいても、他の相続人の相続分や遺留分割合には何の影響も及ぼしません。
また、遺留分放棄をしても相続権は失わないため、遺留分以上の相続分を獲得する場合も当然ありえます。
②相続開始後の放棄
被相続人の死後に遺留分を放棄したい場合は、特に何の手続きも必要ありません。
相続開始から1年間、遺留分の権利を行使しないだけで、消滅時効によって遺留分減殺請求権はなくなることになります。
他の相続人等を安心させたいのであれば、内容証明郵便等で遺留分放棄の意思表示を行っておくのが良いかと思いますが、基本的には何もしないでいるのが一番簡単な遺留分放棄方法です。
<ポイント> 民法1043条
- 生前の遺留分放棄は家庭裁判所へ
- 死後の遺留分放棄は特に何もしなくてよい
- 遺留分を放棄しても相続の権利は残るため、相続放棄をしたい場合は別途手続きが必要
- 遺留分放棄の結果、遺留分はなくても相続分はあるので要注意
- 遺留分放棄した相続人がいても、他の相続人の遺留分割合に影響はない
まとめ
遺留分の計算は相続分の計算と混同しがちになりますが、大きな違いは「特別受益が必ず考慮される」点にあります。
また、相続放棄と違って、相続開始後の遺留分放棄は特に何の手続きも必要ありませんし、生前の遺留分放棄の方法も定められています。
相続財産に不動産が含まれる場合は、遺留分の計算も複雑になるので、このような場合は専門家への相談も視野に入れると良いかと思います。