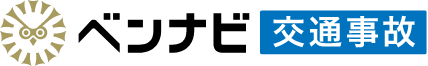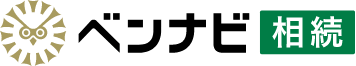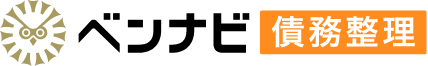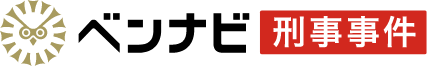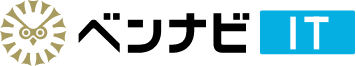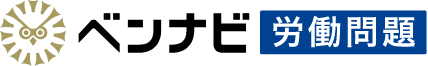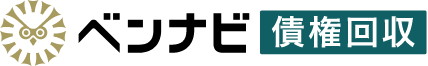お金がない人が頼める弁護士を紹介!利用できる制度や弁護士費用の相場も解説


法律トラブルに巻き込まれた方の中には、弁護士費用は高額というイメージがあって、以下のような悩みや疑問を持っている方も多いでしょう。
- 訴えられたけどお金がない
- 弁護士に頼まなくても解決できる?
- 弁護士費用の相場っていくら?
- お金がない人が頼める弁護士っている?
- 弁護士費用の節約方法ってある?
弁護士は裕福な依頼者だけを相手にしているわけではなく、お金がない人でも問題解決を依頼できるケースもあります。
たとえば、法テラスでは「弁護士費用の一時立替え」などのサポートも提供しており、弁護士費用が支払えないからといってすぐに諦めずに、どのような選択肢があるのか確認しておきましょう。
本記事では、お金がない人が頼める弁護士・利用可能な制度や、弁護士費用を安く抑える方法、弁護士費用の内訳・相場などを解説します。
お金がない人が頼める弁護士・利用可能な制度
自分では解決できないような法律問題が発生した場合、まとまったお金がなくても弁護士に依頼できるケースもあります。
「就職したばかりで収入が低い」「高額な買いものなどをして一時的に預金が減っている」など、まとまった資金がない方は以下の方法で弁護士を探しましょう。
法テラスの民事法律扶助制度|法テラスが定める要件を満たしている場合に利用可能
法テラスとは、法律問題の解決をサポートしてくれる公的機関です。
法テラスでは民事法律扶助業務として、弁護士との無料法律相談(約30分×3回)や弁護士費用の立替払いなどのサポートを提供しています。
弁護士費用の立替払いを利用したあとは、法テラスへ毎月5,000円~1万円程度分割で支払う必要があるものの、現在手元にまとまった資金がない方でも速やかに弁護士に依頼することができます。
ただし、法テラスの民事法律扶助制度を利用するためには、法テラスが定める以下のような要件を満たさなければなりません。
- 資力が一定額以下であること
- 1. 月収が一定額以下であること:「単身者は18万2,000円以下」など
- 2. 保有資産が一定額以下であること:「単身者は180万円以下」など
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(権利濫用的な訴訟や報復目的の依頼などではない)
【参考元】民事法律扶助業務|法テラス
なお、原則として法テラスから紹介される弁護士は自由に選択できないため、解決したい問題について対応経験の浅い弁護士が担当する可能性もあるほか、刑事事件に関する相談は受け付けていません。
収入や資産に関しては、給与明細の写し・源泉徴収票・課税証明書・確定申告書などで証明する必要があり、不動産を所有している場合には固定資産評価証明書が必要になるケースもあります。
法テラスでの無料相談については以下の関連記事でも解説しているので、詳しくはそちらをご確認ください。
【関連記事】法テラスで無料相談できる内容はどこまで?利用するための条件や注意点も解説
日本弁護士連合会の法律援助事業|経済的に余裕がなく弁護士が必要と認められた場合に利用可能
日本弁護士連合会とは、日本全国の弁護士が所属している団体です。
日本弁護士連合会では以下のような委託援助業務をおこなっており、弁護士を通じて委託先の法テラスに申し込むと、原則無料で弁護士に依頼できます。
- 刑事被疑者弁護援助
- 少年保護事件付添援助
- 犯罪被害者法律援助
- 難民認定に関する法律援助
- 外国人に対する法律援助
- 子どもに対する法律援助
- 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
- 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助
【参考元】法律援助事業のご案内|日本弁護士連合会
注意点として、親族から資金援助を受けられる場合や、委託援助業務を申し込んだあとに収入が増加した場合などは、弁護士費用を請求される可能性があります。
なお、法テラスへの申込みは相談者本人からはできず、委託援助契約弁護士を通じておこなう必要があります。
まずは各都道府県の弁護士会に相談するなどして、委託援助業務を引き受けてくれる弁護士を探しましょう。
また、弁護士が見つかったとしても、自分が解決してほしい法律問題には注力していないケースもあるため、必ずしも納得のいく形で問題解決できるとはかぎりません。
当番弁護士|刑事事件の被疑者として逮捕された場合に利用可能
当番弁護士とは、刑事事件で逮捕された場合に1度のみ無料で呼ぶことができる弁護士のことです。
逮捕後に接見して、今後の刑事手続や取り調べの受け方などについて無料でアドバイスを受けることができますが、以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
- 1度しか呼ぶことができない
- どの弁護士にするか指定できない
- 身柄拘束されていない在宅事件の場合は利用できない など
当番弁護士の場合、弁護士会の管理名簿からランダムで弁護士が選ばれるため、場合によっては相性の悪い弁護士が担当することもあります。
また、当番弁護士は1度しか呼ぶことができないため、継続的な弁護活動を依頼したい場合は国選弁護人や私選弁護人に切り替える必要があります。
国選弁護人|刑事事件の被疑者・被告人となって経済的に困窮している場合に利用可能
刑事事件の被疑者として勾留または起訴された場合、資産(現金・預金などの流動資産)が50万円未満であれば国選弁護人に弁護活動を依頼できる可能性があります。
国選弁護人の費用は国が負担するため、原則として被疑者・被告人本人に請求されることはありませんが、以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
- 勾留前は呼べない
- どの弁護士にするか指定できない
- 原則として弁護人を自由に交代・解任できない
- 納得のいく弁護活動をしてくれない可能性がある など
国選弁護人を呼べるタイミングは勾留後・起訴後になるため、逮捕直後の取り調べなどのアドバイスを受けることはできません。
また、国が弁護人を指名するため相性の悪い弁護士が担当するケースもあるほか、私選弁護人と比べて報酬が低く設定されているため熱心な弁護活動をしてくれない可能性もあります。
弁護士費用特約|保険加入している場合に利用可能
自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約を付けている場合、弁護士との法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円を限度に保険会社が負担してくれます。
具体的な適用範囲は保険会社や契約内容によっても異なりますが、主に以下のような法律トラブルで利用できます。
- 交通事故
- 暴行などによる被害
- 業務妨害
- 労働問題
- 遺産相続 など
ただし、一口に交通事故といっても「自分に100%の過失がある交通事故」や「自動車が関係していない事故」などでは適用対象外となったりするため、詳しくは契約内容をよく確認しましょう。
弁護士費用を安く抑えるための対処法
「弁護士への依頼を考えているものの、できるだけ弁護士費用を安く抑えたい」という場合は、以下のような対応が有効です。
初回無料相談を活用する
多くの法律事務所では、初回の法律相談を無料に設定しています。
初回無料相談に対応している法律事務所に絞ることで、数千円~数万円程度の節約につながります。
また、弁護士費用は法律事務所によってもバラつきがあるため、無料法律相談を活用して複数の法律事務所で見積もりを出してもらって比較することで、安いところが見つかる可能性があります。
なお、市区町村役場によっては定期的に無料法律相談会を実施しているところもあり、「とりあえず一度相談だけしたい」という方は利用してみるのもよいでしょう。
【関連記事】弁護士の無料電話相談窓口4選|24時間法律相談受付のおすすめ窓口はどこ?
後払い・分割払い可能な弁護士を探す
弁護士に依頼する場合は一括で弁護士費用を支払うのが原則ですが、以下のようなケースでは後払いや分割払いに応じてもらえることもあります。
- 信頼できる人から紹介された場合
- 依頼者に安定的な収入がある場合
- 相手方から確実に金銭を回収できる場合 など
たとえば、残業代未払い・B型肝炎訴訟・遺留分侵害額請求などの依頼では金銭の回収が望めるため、後払いや分割払いでも事件に着手してくれる可能性があります。
弁護士に後払いや分割払いの相談をする際は、経済的な事情を正直に伝えて、無理のない支払い期日や分割回数を設定してください。
着手金無料・完全成功報酬制の弁護士を探す
弁護士費用のうち「着手金」は依頼時に支払わなければいけませんが、なかには着手金を0円に設定しているところもあります。
ただし、着手金無料の法律事務所では成功報酬を高めに設定しているところが多いため、トータルコストとしては着手金ありの場合とほとんど変わらないこともあります。
また、案件対応で必要な実費については、その都度請求されることもあります。
着手金無料の弁護士に依頼する際は、各費用の請求時期や報酬体系をよく確認しておきましょう。
法律トラブルでかかる弁護士費用の内訳
法律トラブルを弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金(成功報酬)
- 日当
- 実費 など
ここでは、各費用項目について解説します。
相談料|30分あたり5,000円程度
相談料とは、弁護士に法律相談する際にかかる費用のことです。
多くの法律事務所ではタイムチャージ制となっていて、30分あたり5,000円程度が一般的な相場です。
ただし、初回相談に関しては無料で対応してくれる法律事務所も多くあります。
着手金|依頼内容や請求金額によって変わる
着手金とは、弁護士に問題解決を依頼する際にかかる費用のことです。
着手金は問題解決の成否を問わず発生するため、たとえ思うような結果にならなかったとしても返金されないのが原則です。
法律事務所によっても料金体系は異なりますが、基本的には「依頼者が得ようとする経済的利益」に応じて金額が決まります。
基本的には弁護士が回収した金銭、または弁護活動により獲得した権利や地位などが経済的利益となるため、依頼内容や相手方への請求金額によって金額は大きく変わります。
弁護士は着手金を受け取ってから業務をスタートするため、委任契約するときは不足がないように準備しましょう。
報酬金・成功報酬|依頼後の経済的利益の額によって変わる
報酬金とは、弁護士に依頼して問題解決できた場合にかかる費用のことです。
基本的に報酬金も経済的利益を基に算出されますが、支払うタイミングは問題が解決したあとで、依頼が失敗に終わった場合は発生しません。
報酬金が発生する場合、経済的利益の考え方が重要になるため、支払いトラブルが発生しないように注意しましょう。
たとえば、弁護士の介入によって離婚時の財産分与額を増額できた場合、増額分だけが経済的利益となるのか、それとも全額が経済的利益となるのかを事前に弁護士とすり合わせておかないと、認識違いでトラブルになってしまうおそれがあります。
また、損害賠償請求などを依頼する場合、獲得見込み額が少ないと弁護士費用のほうが高くなって費用倒れとなることもあるため、獲得見込み額と費用総額についても十分に話し合っておく必要があります。
日当|半日3万円~5万円程度、1日5万円~10万円程度
日当とは、弁護士が案件対応のために事務所から離れて活動する場合にかかる費用のことです。
基本的には拘束時間によって金額が変わり、半日の場合は3万円~5万円程度、1日の場合は5万円~10万円程度が一般的な相場です。
たとえば、刑事事件の弁護・離婚裁判・インターネットトラブルの開示請求などのような裁判所や警察署での対応が必要なケースでは、日当が発生する可能性があります。
できるだけ日当を節約したい場合は、裁判所や警察署などから近いところにある法律事務所を選ぶのが有効です。
実費|弁護士の業務内容によって変わる
実費とは、弁護士が案件対応する際にかかった費用のことです。
弁護士が業務をおこなう場合、必要書類の収集・証拠保全・示談書や離婚協議書の作成など、さまざまな場面で実費が発生します。
ほかにも、通信費・コピー代・交通費なども実費に含まれ、どのような対応を依頼するのかによっても金額は変わるため、詳しくは依頼先に直接確認しましょう。
【分野別】弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場
弁護士は幅広い分野の法律問題に対応しており、問題解決のための的確なアドバイス・サポートが受けられます。
ここでは、分野ごとの弁護士費用の相場やサポート内容について解説します。
なお、弁護士費用は依頼内容や依頼先事務所によっても変わるため、あくまでも以下で解説している金額は参考程度に留めてください。
交通事故の弁護士費用
交通事故の被害者になった場合、弁護士なら以下のようなトラブル解決を依頼できます。
- 不当な過失割合を提示された
- 相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られた
- 後遺障害等級の認定結果に納得いかない
- 慰謝料を減額された
- 逸失利益の請求を認めてもらえない など
交通事故トラブルの場合、弁護士費用は着手金が10万円~20万円程度、報酬金は慰謝料や逸失利益などの獲得できた賠償金額によって変わります。
なお、弁護士が代理人として示談交渉することで賠償金が増額されるケースが多いため、示談交渉が難航している方や、後遺障害などで悩んでいる方は一度相談してみることをおすすめします。
【関連記事】交通事故の無料相談窓口9選!電話相談・休日相談に対応している窓口も紹介
刑事事件の弁護士費用
刑事事件の加害者が弁護士に依頼した場合、以下のような減刑・早期釈放の獲得を目指した弁護活動をおこなってもらえます。
- 逮捕後の早期釈放に向けた働きかけ
- 取り調べの受け方のアドバイス
- 被害者との示談交渉の代行
- 勾留・勾留延長の阻止活動
- 不起訴処分・無罪判決の獲得に向けたサポート など
刑事事件でかかる弁護士費用は、着手金が30万円~50万円程度、報酬金も30万円~50万円程度が一般的な相場です。
また、逮捕・勾留されている場合、弁護士と面会する際は1回あたり2万円~5万円程度の接見費用もかかります。
刑事事件を起こして逮捕されても、不起訴処分となれば前科は付かずに済みます。
ただし、刑事手続にはタイムリミットがあってスピーディに進行し、時間の経過とともに弁護士ができることも限られてくるため、できるだけ速やかに弁護活動を受けることが大切です。
遺産相続の弁護士費用
遺産相続で起きやすいトラブルとしては主に以下があり、相続人同士で解決できない場合は弁護士に依頼しましょう。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 想定外の相続人の存在が判明した
- 被相続人に多額の借金がある
- 遺留分の侵害が発生している
- 特別受益や寄与分の主張がある
- 相続財産の評価額がわからない など
相続トラブルの場合、弁護士費用は遺産総額に応じて決まり、着手金の相場としては20万円~200万円程度です。
報酬金に関しては、遺留分の回収額や取得財産の増額分などをベースに計算するのが一般的です。
相続トラブルは子孫に引き継がれるケースも多く、相続財産の有効活用もできなくなるため、弁護士に依頼して早期解決を目指すことをおすすめします。
離婚問題の弁護士費用
離婚問題の当事者になった場合、弁護士なら以下のようなトラブル解決を依頼できます。
- 財産分与で揉めている
- 親権がどちらにあるのか揉めている
- 元パートナーの財産隠しやストーカー行為が発覚した
- 慰謝料や養育費の未払いが発生している
- 面会交流のルール違反が起きている など
離婚問題でかかる弁護士費用は、どのような対応を依頼するのかによって変わります。
離婚手続きとしては協議離婚・調停離婚・裁判離婚などがあり、協議離婚の場合は20万円~60万円程度、調停離婚の場合は40万円~70万円、裁判離婚の場合は70万円~110万円程度が一般的な相場です。
たとえば、離婚原因が夫のDVやモラハラというようなケースでは、離婚後もトラブルを引きずってしまうと精神的にも消耗するため、弁護士のサポートを受けて早期解決を目指すことをおすすめします。
また、夫婦間での約束は簡単に破られてしまうことも多く、弁護士に離婚協議書を作成してもらったり、強制執行を可能にするために公正証書を作成してもらったりすることでトラブル防止が望めます。
【関連記事】離婚問題を弁護士に電話で無料相談できる窓口|24時間相談受付も
インターネットトラブルの弁護士費用
主なインターネットトラブルとしては以下のようなものがあり、個人では解決が難しく泣き寝入りとなってしまうケースも多くあるため、弁護士に解決を依頼することをおすすめします。
- SNSやインターネット掲示板での誹謗中傷・名誉毀損
- リベンジポルノ
- 個人情報の流出
- 著作権・肖像権・商標権の侵害 など
インターネットトラブルでかかる弁護士費用は依頼内容によって異なり、たとえば投稿者の身元特定を依頼した場合は着手金として20万円~30万円程度、報酬金として15万円~20万円程度かかるのが一般的です。
インターネットトラブルでは被害の拡散スピードが早く、なかには投稿を削除しても別アカウントで誹謗中傷が繰り返されたりすることもあり、迅速かつ的確に対応しなければなりません。
ただし、個人で開示請求などをおこなっても簡単には応じてもらえないこともあるため、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
労働問題の弁護士費用
主な労働問題としては以下があり、なかには労働基準監督署や労働組合に相談しても解決が難しいケースもありますが、そのようなケースでも弁護士に依頼することで解決につながることもあります。
- 賃金・残業代の未払い
- 不当解雇
- 労災問題
- パワハラやセクハラなどのハラスメント
- ブラック企業問題
- 雇い止め など
労働問題でかかる弁護士費用は依頼内容によって異なり、たとえば残業代請求を依頼した場合は着手金が20万円~30万円程度、報酬金は獲得金額の20%程度になるのが一般的です。
たとえば、賃金や残業代の未払いが起きているようなケースでは、労使の力関係から会社側に強く言えず、成果主義を理由にサービス残業を強いられている労働者も少なくありません。
セクハラ被害に関しては相談相手すらいないケースもあり、一人で悩まずに早めに弁護士に相談して、今後の対応についてアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。
【関連記事】労働問題の24時間無料相談窓口|その他の窓口も受付時間別に紹介
債権回収の弁護士費用
債権回収で以下のようなトラブルが発生した場合、自力で対応しようとすると回収が先延ばしになってしまったり、未回収のまま終わってしまったりするおそれがあるため、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。
- 相手方が「借りた証拠がない」と主張している
- 下請代金・業務委託料の未払いが起きている
- 商品代金・サービス利用料の支払いを滞納されている
- 家賃を支払ってもらえない
- 取引先が倒産した
- 敷金・保証金が返還されない など
債権回収でかかる弁護士費用は、どのような方法での回収を依頼するのかによって変わります。
たとえば、内容証明郵便での債権回収を依頼する場合は着手金が1万円~5万円程度、訴訟での債権回収を依頼する場合は10万円~30万円程度かかるのが一般的です。
報酬金に関しては、回収額の10%~20%程度となるのが一般的です。
債権回収の場合、時効の問題もあるため、できるだけ速やかに適切な方法で時効完成を阻止しなければなりません。
特に時効が迫っている場合は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。
債務整理の弁護士費用
借金問題で悩んでいる場合、以下のような任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理をおこなうことで解決が望めます。
- 任意整理:債権者と直接交渉して、返済期限の延長や将来利息のカットなどをしてもらう方法
- 個人再生:裁判所を介して、借金を最大80%減額してもらう方法
- 自己破産:裁判所を介して、借金の返済を全額免除してもらう方法
弁護士なら上記の手続きを一任でき、どれを依頼するのかによって弁護士費用は変わります。
たとえば、任意整理を依頼して100万円減額できた場合はトータルとして20万円程度、個人再生を依頼した場合は40万円~60万円程度、自己破産を依頼した場合は30万円~60万円程度かかるのが一般的です。
弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの督促は停止するため、常に債権者からの連絡を気にする必要がなくなり、精神的負担も軽くなります。
借金問題を解消して人生の再スタートを切るためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
【関連記事】【土日・夜間対応】自己破産の無料相談窓口|相談の流れや有効活用するポイントを解説
弁護士への依頼後に弁護士費用を支払えなくなった場合のリスク
弁護士への依頼後に弁護士費用を支払うことができなくなった場合、以下のようなリスクがあります。
問題解決の途中で弁護士に辞任される
弁護士費用の支払いが滞ってしまうと、問題解決の途中でも弁護士が辞任してしまう可能性があります。
その場合、たとえば債権回収を依頼していた場合は時効が成立して回収できなくなったり、債務整理を依頼していた場合は債権者からの督促が始まったりなど、さまざまな不利益が生じます。
特に証拠収集などに時間がかかるような案件の場合、着手に向けた準備段階で辞任されることもあります。
法律事務所から訴訟を起こされる
弁護士費用が発生しているにもかかわらず滞納している場合、法律事務所から督促を受けたり訴訟を起こされたりする可能性もあります。
弁護士と争ったところで基本的に勝ち目はないため、親族や友人などに立替払いをしてもらうなど、何らかの方法でお金を準備しましょう。
お金がない人が弁護士に依頼する際の注意点
金銭的に厳しい状況ではあるものの、弁護士への依頼を検討している場合は、以下のような点に注意しましょう。
費用対効果を考えておく
お金がない人の中には「そもそも本当に弁護士が必要かどうか」「自力でも解決できないか」などと考えている方もいるでしょう。
そのような方は、弁護士に依頼することで得られる金銭や、失わずに済む権利・地位などについて一度考えてみましょう。
たとえば、遺産相続トラブルで1,000万円の遺留分侵害額請求を依頼する場合、着手金と報酬金の合計額としては150万円~200万円程度になる可能性があります。
これは決して安い金額ではありませんが、素人が自力で対応すると相手方と揉めて1円も回収できずに終わってしまう可能性もあるため、状況次第では何とか弁護士費用を準備してでも依頼する価値はあるでしょう。
また、刑事事件の場合は、速やかに弁護士のサポートを受けることで不起訴処分・無罪判決を獲得でき、会社を解雇されることなく無事に社会復帰できることもあります。
たしかに弁護士費用は高額になることもありますが、そのぶん得られるメリットもあるため、法律トラブルで悩んでいるのであれば弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士には予算の事情を正直に伝える
弁護士費用の支払いについては柔軟に対応してもらえるケースもあるため、弁護士に依頼する際は予算の事情を正直に伝えましょう。
弁護士に予算を伝えないまま依頼してしまうと、のちのち予算を超える金額を請求されたりして支払いが困難になるおそれがあります。
「弁護士費用を安く抑えるための対処法」でも解説したとおり、法律事務所によっては後払いや分割払いに応じてもらえることもありますし、予算の範囲内でできる限りのサポートをしてくれる可能性があります。
もし分割払いにする場合は、毎月の給与支給日を支払い期日に設定し、賞与や一時金があるときは増額するなど、無理のない支払い方法を弁護士と話し合ってください。
以下の記事では、弁護士費用の相場や計算方法について解説しているので、費用面について詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
【関連記事】【分野別】弁護士費用の相場はいくら?安く抑える方法・払えない場合の対処法を解説
質問事項や相談内容に関する資料をまとめておく
依頼前に弁護士との無料相談を利用する場合、相談時間は30分~1時間程度に設定されているのが一般的です。
限られた相談時間を無駄にしないためにも、事前に以下のような情報をまとめておきましょう。
- 相談状況・トラブルの経緯
- 相談内容に関する資料・証拠
- どのような形での解決を望んでいるのか など
弁護士は何も知らない状態で相談を受けるため、事実経過を時系列にまとめ、トラブル相手との関係性なども整理しておきましょう。
トラブル相手から内容証明郵便などで請求を受けている場合や、裁判所から調停などの書類が届いている場合は、それらの書類も忘れずに持参してください。
さいごに|お金がなくても諦めずに、まずはベンナビで無料相談を
法テラスの民事法律扶助制度や日弁連の法律援助事業など、お金がない方でも場合によっては弁護士のサポートが受けられることもあります。
法律事務所の中には初回相談無料のところもあるため、法律トラブルで悩んでいるのであればまずは相談してみることをおすすめします。
当サイト「ベンナビ」では、各分野に強い全国の弁護士を掲載しています。
初回相談無料・着手金0円・分割払い対応・後払い対応などの法律事務所も多数掲載しているので、お金がなくて悩んでいる方も一度利用してみましょう。
依頼はせずに相談だけの利用も可能ですので、気軽にご相談ください。