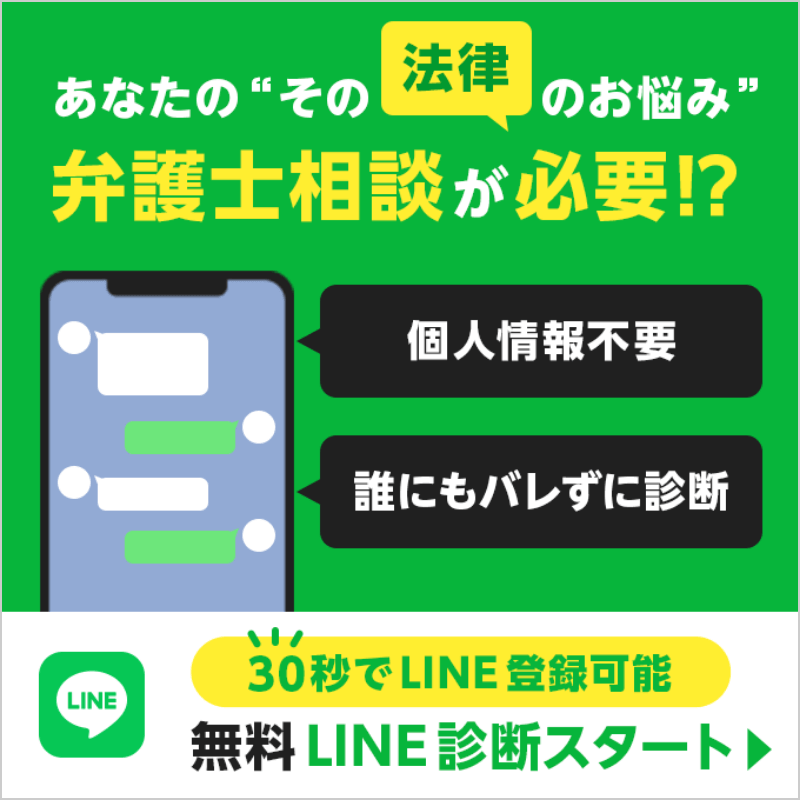弁護士の回答一覧
回答日:2025年09月16日
【弁護士歴20年以上|書き込み削除・犯人特定に実績豊富!】あきつゆ国際特許法律事務所

外国での判決を日本で執行する場合、外国判決の確認手続を日本の裁判所で行う必要があります。具体的には、民事訴訟法118条に基づき申立を行うことになりますが、同条には以下のような要件があります。
①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
③判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
④相互の保証があること。
弊所は、外国判決の日本国内の執行に関する経験値は多い方だと思いますが、上記のうち、②の送達、④の相互保証については、案件によっては立証に苦労する場合があります。
上記により裁判所が外国の判決を日本で適用できると認定すると、次に強制執行の手続きに進むことになります。
強制執行は日本の法律に基づいて執行します。これには、収入の差し押さえも含まれます。収入の差し押さえについては、法律上、債務者の生活費等を確保するための差し押さえ禁止額が設けられており、それを超えた部分が差し押さえの対象となります。その範囲等も日本の法律に従うことになりますが、ご参考までに、以下に該当する債権、動産等は、法律上、差押えが禁止されております。
差押禁止債権:
・手取り給与(給与額面額から税金等を控除した額。賞与、退職金、退職年金を含む)の4分の3、又は、33万円を超えない金額
・国民年金、厚生年金、生活保護給付金、児童手当などの受給債権 など
差押禁止動産:
・債務者の生活に不可欠な物資や道具
・債務者に思い入れがあり、売値がつかないと判断されるもの
・宗教的な信仰対象 など
以上の通り、外国判決の日本での執行は一定の手続きを経なければならず、強制執行も日本の法律の枠内で行われます。相談者様の具体的な事情により、手続きや結果は異なる場合がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
②敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
③判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
④相互の保証があること。
弊所は、外国判決の日本国内の執行に関する経験値は多い方だと思いますが、上記のうち、②の送達、④の相互保証については、案件によっては立証に苦労する場合があります。
上記により裁判所が外国の判決を日本で適用できると認定すると、次に強制執行の手続きに進むことになります。
強制執行は日本の法律に基づいて執行します。これには、収入の差し押さえも含まれます。収入の差し押さえについては、法律上、債務者の生活費等を確保するための差し押さえ禁止額が設けられており、それを超えた部分が差し押さえの対象となります。その範囲等も日本の法律に従うことになりますが、ご参考までに、以下に該当する債権、動産等は、法律上、差押えが禁止されております。
差押禁止債権:
・手取り給与(給与額面額から税金等を控除した額。賞与、退職金、退職年金を含む)の4分の3、又は、33万円を超えない金額
・国民年金、厚生年金、生活保護給付金、児童手当などの受給債権 など
差押禁止動産:
・債務者の生活に不可欠な物資や道具
・債務者に思い入れがあり、売値がつかないと判断されるもの
・宗教的な信仰対象 など
以上の通り、外国判決の日本での執行は一定の手続きを経なければならず、強制執行も日本の法律の枠内で行われます。相談者様の具体的な事情により、手続きや結果は異なる場合がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
回答した事務所の紹介
【弁護士歴20年以上|書き込み削除・犯人特定に実績豊富!】あきつゆ国際特許法律事務所
愛知県名古屋市東区武平町5丁目1番地名古屋栄ビル4階
オンライン面談可能
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
お住いの都道府県を選ぶ
北海道・東北
関東
中部
関西
中国・四国
九州・沖縄
法律相談Q&Aランキング
副業助成金は詐欺ですか?
2024年12月23日
1
30
貞操権侵害、、、、?
2026年01月15日
2
3
父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか
2024年10月21日
1
20
SNSでの児童ポルノについて
2025年05月29日
1
7
離婚するといったら死ぬと言われた場合
2025年03月26日
1
21
フリーワードで探す
この質問に関連する法律相談
投稿順
役立った順
関連順
投稿日:2026年02月03日
回答日:2026年02月03日
同棲相手が既婚者でした
昨年10月から結婚を前提に同棲を始めました。
住民票も移してます。
しかし、相手が既婚者でした。
今月その事実が発覚しました。
問い詰めても「いまは結婚してない、子どももいる、ただ2人の将来には支障がないから言わなかった、独身証明書はすぐに出せる、なんなら婚姻届持って来てもいい
すぐにハンコ押してやる」とも言われましたが全く信じてません。
2
0
投稿日:2026年01月30日
回答日:2026年01月30日
不貞行為に対する慰謝料請求について
約2週間不倫をしていました。
相手の奥さんにバレ、慰謝料180万円の請求と旦那さんとの接触禁止が和解条件として提示されています。
奥さんと旦那さんは10月また頃に離婚をしています。
1
0
投稿日:2026年01月29日
回答日:2026年01月30日
賃貸仲介における重要事項不説明(エアコン設置可否)に関する相談
不動産仲介業者の仲介により、2025年12月6日に賃貸契約を締結しました。内見時(11月16日)、担当者から「エアコンは業者確認が必要だが、縦積みやマルチエアコン等で寝室2部屋とも設置できると思われる」との説明を受け、設置可能であることを前提に契約に進みました。
しかし契約前の11月23日、管理会社から仲介業者に対し「エアコン増設工事は難しいかもしれない」との情報が共有されていたにもかかわらず、私には伝えられないまま契約が締結されました。契約後にエアコン業者確認を行った結果、一方の寝室には設置できないことが判明し、現在も居住上の不便が生じています。
私が説明義務違反として仲介手数料全額22万円の返還を内容証明で請求したところ、仲介業者は業者確認が必要だとは伝えたとして、説明義務違反を否定し、エアコン工事費の一部として2万円のみ提案していますが、納得できず、少額訴訟を検討しています。加えて、重要事項説明書や口頭説明がないまま、仲介手数料1.1か月分を契約前に支払っている点にも問題意識があります。
1
0
投稿日:2026年01月25日
回答日:2026年01月25日
夫側の浮気が原因で離婚する場合、慰謝料はいくらかかるか知りたいです。
知り合いの話なのですが、10年前の結婚前から浮気相手がいて奥さんが妊娠中にバレ、認めてはないものの信用を失い、10年間レスにもなり、最近は夫婦関係が破綻し、会話もなければ洗濯物なども別、朝と夕飯は作ってくれているそうです。
それでも旦那さん側から離婚を切り出した場合、慰謝料と養育費はどのくらいかかるのか知りたいです。子供は小4の息子のみです。
よろしくお願いいたします。
1
0
投稿日:2026年01月21日
回答日:2026年01月21日
参考人として出頭要請がありました
以前付き合いがあった取引先企業が外為法違反の被疑者となっています。当時、私が被疑者の担当として付き合いがあったので、警察から電話がありました。参考人として、調書を取り、チャット履歴も確認したいと言われています。話しぶりでは、多少共犯として疑われている印象もうけました。任意ではありますが、出頭しないとデメリットでしょうか。
1
0
投稿日:2026年01月19日
回答日:2026年01月19日
母が母名義の不動産を知人に無償で貸していた不動産を取り返したい。
母名義の不動産に関し、今後の対応について匿名で初期相談をさせていただきます。
物件は東京都内の区分所有マンション一室(事業用可)で、所有者は私の母、相手方は知人男性およびその関係法人です。
当該物件は、母が税理士事務所として長年使用していた事業用物件で、当時から相手方より「法人登記上の本店所在地として住所を使わせてほしい」との依頼がありました。母は「本店所在地表示目的に限り、実際の使用や占有は一切認めない」前提で、書面契約なく無償・一時的に許諾しました。
その後、母は高齢となり数年前に実質廃業しましたが、管理能力が低下していた時期に、相手方が無断で法人名の表札・室内に自身の法人の掲示物等(宅地建物取引業者票等)を設置しました。現在、室内は居住実態・事業実態ともになく空室状態で、登記変更・鍵返却・掲示物撤去も未了です。
昨年末に普通郵便、今年1月に内容証明で上記許諾解除通知を発送しましたが、不在持戻りとなり反応はありません。
現在、防犯上の理由から鍵交換を検討していますが、自力救済と評価されるリスクについて初期的なご見解を伺いたく存じます。
2
0
投稿日:2026年01月17日
回答日:2026年01月19日
有料副業コミュニティで退会できずに困っている
有料副業コミュニティに先月加入しましたが、案件先の会社からクレームが会社にクレームが来ていて裁判を起こすかもしれないと言われました。
案件が全て終わったと思い退会申請をし、ラインの内容も全て消してしまいましたが、その後にカード決済が何回か走りましたが残高不足のため無視していました。
その後にその副業コミュニティの代表から個人ラインが来て、案件が途中なので月額費を払えと言われ払わない場合は、提携弁護士から督促すると言われました。
案件を再開し、案件をやりたい旨をLINEのアカウントに連絡したところブロックしたためお断りと連絡をもらいました。
それだけなら良かったのですが、その案件元の企業から有料コミュニティの会社にクレームで裁判起こすかもしれないと言われています。
契約違反だと言われたのですが、契約が手元にないのでわからないのですが、裁判になった所で私が何か費用を払わないといけないのでしょうか?
有料副業コミュニティの名前はあり、どうやら法人企業らしいですが連絡先がラインのみのため、企業の連絡先も不明です。
1
0
投稿日:2026年01月16日
回答日:2026年01月16日
公園での過度なスキンシップについて
当時は全く犯罪かもしれないなどとは考えていなかったが、急に不安になりました。既に4ヶ月ほど経過しています。後日逮捕されたらどうしようかと心配です。
1
0
投稿日:2026年01月16日
回答日:2026年01月16日
マッチングアプリでの出会い、不同意性交等の訴えについて
マッチングアプリにて女性と出会い、飲食後、宿泊しているホテルへ行く許可を得て、出会ったその日にホテルで避妊をした上で関係を持ちました。ホテルに行く前には、コンビニで飲み物を買って友好的に入室しております。
乱暴なことも一切しませんでしたが、行為途中からお互いにやや盛り上がりにかける雰囲気になり、そのまま女性を部屋から見送りました。(着替えもしていないことから、そこはやや不満そうでした。)
ただ、その日にごちそうさまでした、また機会があれば会いましょうというメッセージがマッチングアプリでおくられてきたのですが、翌日にブロックされました。(ブロックされると相手とのメッセージは全て削除され現在は残っておりません。)
自分自身、着替えもせずに部屋から見送ったことは良くなかったと反省しておりますが、この場合、不同意性交等の被害届が出された場合は事件化する可能性はございますでしょうか。
1
0
投稿日:2026年01月07日
回答日:2026年01月07日
暴行罪の慰謝料を支払わせたい
駅のホームで歩きスマホをしていた加害者と肩がぶつかった後に、突然背後から突き飛ばされました。
駅員が仲裁に入り、その場は加害者が謝罪して別れたのですが、その後どうしても許せずに
後日、警察へ被害届を出して、最終的に暴行罪で略式命令で罰金を支払ったようです。
その後も加害者は誠意のない対応だったので、内容証明郵便で慰謝料を請求したのですが、この段階で相手側の弁護士がでてきて
「事件当日に謝罪して別れているので、和解が成立している」と言ってきました。
2
0
投稿日:2024年12月23日
回答日:2024年12月23日
副業助成金は詐欺ですか?
今LINEグループで副業助成金7億円に当選したみたいで受け取る手続きをした際IDが間違えてると指摘されてしまい、2千円のアップルギフトカードを買って送ってほしいというのですがこれは詐欺でしょうか?
もし24時間以内に受け取らないと不正行為となり差し押さえや逮捕されるというのですがどうすればいいのでしょうか?
ちなみにキャリアアップと言う会社です。
副業助成金を受け取らずに逮捕されたという2人の動画も添付されていて、とても怖いです。
今はまだギフトカードは購入していないので実害はありませんが、警察に行ったら相談に乗ってくれますか?
私は、逮捕されてしまうのでしょうか?
また、どんな対応をすればいいのでしょうか?
1
30
投稿日:2024年08月21日
回答日:2024年08月21日
性病を移されたことにたいしての治療費請求について
友達の紹介である日本人男性に出会いました。何度か遊んでいく中で相手から告白され関係をもちました。
その後体調不良となり、病院を受診したところ性器ヘルペスに感染していると診断を受けました。
病院の先生には、間違いなくその相手から感染したと診断されました。
その旨を相手に伝えたところ、俺のせいじゃない、俺は関係ないの一点張りで、検査もせず最終的には連絡先までブロックされてしまいました。
お互いに責任があることかとは思いますが、その後の対応で体調を心配することもせず逆ギレをされブロックされた事に非常に怒りを覚えます。
1
5
投稿日:2024年02月04日
回答日:2024年02月05日
騒ぎを起こさず、お金を返して欲しい
約9年間ダブル不倫をしてました。
彼に何回かお金を貸して欲しい、すぐ返すからと言われ、お金を貸してからなかなか返してくれず、お金の話をすると、逆ギれされたり機嫌が悪くなるので、催促がなかなかできない状態でした。私の方が彼に気持ちが強かったので、怒らせないように、嫌な事をいわれても我慢してました。
でも、今年に入り地震もあり、お金が必要だから返して欲しいと言うと、逆ギレされ、会話も出来ず、連絡も無視状態になりました。
お金の金額は合計190万近くになります。
借用書はありません。
LINEとのやりとりに、彼からお金を返しますとのメッセージはあります。
ダブル不倫ということもあって、逆に彼の奥さんから、慰謝料を請求書されたら?との不安があります。
1
5
投稿日:2024年06月25日
回答日:2024年06月25日
ハラスメントについて
同僚の異性との不倫の噂を流された。
そんな事実はなく、業務にも支障をきたし家族も傷ついている。
また、業務を行っているのに相手の方と仕事をせず遊んでいると言いふらされ人間関係が悪化している。
そもそも、その方とは友人関係であり家族との面識もある。
それにより、働く仲間へ疑心暗鬼になり職場にある事が苦痛。
2
4
投稿日:2023年07月26日
回答日:2023年07月27日
社用車の修理費用を請求されています
以前働いていた会社から、社用車の修理費用10万円を請求されました。社用車を塀に擦ってしまい、その時は「1回目はお金を請求しないけれど、2回目からは修理費用を出してもらう」と言われました。ですが、その会社を退職した所「これから頑張ってもらうために修理費用を免除した。辞めたのだから請求する」と言われました。塀の角と車が接触し、動かなくなってしまったため他の職員が車を動かせるようにした事もあり、どこまでが私のやった傷なのかもはっきりしていません。それに免許を取りたての初心者だということも知っていたはずなのに大きい車を運転させられ、擦ったら修理費用を請求、と言うのは悔しいです。
1
4
投稿日:2024年06月10日
回答日:2024年06月11日
現在の収入が少なく損害賠償が払えれない。
スーパーの商品(タバコ)を約2年に渡り窃盗し昨年の11月で解雇になり警察に被害届けを出されましたが検察は不起訴処分になりました。
最近になり電話があり損害賠償の電話があり会社(スーパー)に来いとの事でした。
2
4
投稿日:2024年08月28日
回答日:2024年09月04日
居候が家に居座っていて困っているので追い出したいです。
私: 26歳の男性です。
状況: 3年前から友人が私の家に住んでいます。当初、彼はお金がなくて困っていると言うので一緒に住むことを許しました。しかし、彼は怒ると床や壁に物を叩きつけたり、夜中に大声で怒鳴ったりするようになりました。
一度、私も怒ってしまい、棚を蹴ったことがあります。棚の上にあった彼のパソコンが壊れたらしく、修理代を払えと要求されています。さらに、もし払わなければ私の物を壊すと脅されてしまい、どう対応すれば良いか悩んでいます。
考えている対策:
・家の鍵を変え、彼の荷物をレンタル倉庫に預ける。契約が切れたら処分してもらう。
・自分が引っ越して、彼の荷物をそのまま残していく。
・警察や弁護士、管理会社に相談して、彼を追い出してもらう。
問題点: 鍵を変えて荷物を処分するのが最も早い方法だとは思いますが、法的に問題がないかが心配です。
また、パソコンに関しても修理代は、出さなければいけないのでしょうか。
どうかアドバイスをお願いいたします。
1
4
投稿日:2024年06月23日
回答日:2024年06月24日
離婚の切り出し方、夫に家から出て行ってもらう方法
結婚15年目で正社員フルタイムで働いています。子どもは中2と小5息子2人です。夫は自分を優先にして行動し、子どものことにはまったく無頓着で、家事も洗濯物を干す以外しません。家計は私が管理しています。はっきり言って父親らしいことは何もしていません。生活費は一応渡されますが少ないし、この先一緒にいることのメリットを息子も私も感じていません。離婚したいのですが、持ち家の名義は私ですし、まだローンは1500万くらいのこっていますし、私や息子はでていきたくありません。夫に出て行ってほしいのですが、まだ離婚をしたい旨も切り出していないのですが、離婚したいと申し出てからスムーズに出て行ってくれるのか?出て行ってくれない場合どうしたらいいのか?そもそも、離婚したいと言ってからは一緒にもう住みたくないという気持ちでいる(何をしでかすかわからない)のですが、離婚を切り出すときには一時的にマンションなど借りて別居していた方がいいのか、どのように進めていくのがいいのか悩んでいます。
1
4
投稿日:2023年05月23日
回答日:2023年05月24日
女性の胸のチラ見は犯罪になるのか?
帰宅の際、駅のホームを動画を見ながら歩いていると改札に続く曲がり角で女性が歩いてきて、
ぶつからないように女性に近い方の肩をずらして半身になりながらすれ違いました。
その際、ぶつからないように女性の肩から肘にかけて目線をずらして自分との距離を測っていましたが、女性のシャツのボタンが第2か3ボタンくらいまで外れており胸の谷間が見えてしまいました。
すれ違った後、女性が胸元のシャツを閉じるように手で掴みながら振り向いたような気がします。すれ違った後すぐに動画に目線を移していたので視界の端に見えていた程度です。
何か問い詰められるのが怖くてそのまま人の流れにそって歩いて帰宅しました。
1
3
投稿日:2024年07月17日
回答日:2024年07月17日
精神疾患と傷害罪について
何度も何度も弁護士・警察に相談してきました
私はある人から受けた過度なストレス(証拠あり)でうつ病になり、当たり前の生活ができなくなって今年で3年目になります。
発作・動けない・無気力・好きなことができない・仕事が普通にできない・お風呂になかなか入れない・希死念慮・リストカット、自殺など、症状は調べていただければ分かるかと思います。
障害罪は精神疾患にさせた場合も当てはまるとありました。でも誰に相談しても訴えられないと言われます。一人の弁護士の方だけできますと言われました(お忙しいとのことでお願いできませんでしたが)
警察に関しては因果関係にのみ固執してまともに相手されず、障害者相手に可哀想とまで言われ
今はいつ自殺するか分からない精神状態です。
精神疾患は見えない病気です。いつ何が起こるか分からない病気です。医者でさえ因果関係は勿論、はっきりとした決断が話せません。
でもストレスの元凶からは絶対離れてくださいとは言われます。
1
3
投稿日:2026年02月03日
回答日:2026年02月03日
同棲相手が既婚者でした
昨年10月から結婚を前提に同棲を始めました。
住民票も移してます。
しかし、相手が既婚者でした。
今月その事実が発覚しました。
問い詰めても「いまは結婚してない、子どももいる、ただ2人の将来には支障がないから言わなかった、独身証明書はすぐに出せる、なんなら婚姻届持って来てもいい
すぐにハンコ押してやる」とも言われましたが全く信じてません。
2
0
投稿日:2026年01月30日
回答日:2026年01月30日
不貞行為に対する慰謝料請求について
約2週間不倫をしていました。
相手の奥さんにバレ、慰謝料180万円の請求と旦那さんとの接触禁止が和解条件として提示されています。
奥さんと旦那さんは10月また頃に離婚をしています。
1
0
投稿日:2026年01月29日
回答日:2026年01月30日
賃貸仲介における重要事項不説明(エアコン設置可否)に関する相談
不動産仲介業者の仲介により、2025年12月6日に賃貸契約を締結しました。内見時(11月16日)、担当者から「エアコンは業者確認が必要だが、縦積みやマルチエアコン等で寝室2部屋とも設置できると思われる」との説明を受け、設置可能であることを前提に契約に進みました。
しかし契約前の11月23日、管理会社から仲介業者に対し「エアコン増設工事は難しいかもしれない」との情報が共有されていたにもかかわらず、私には伝えられないまま契約が締結されました。契約後にエアコン業者確認を行った結果、一方の寝室には設置できないことが判明し、現在も居住上の不便が生じています。
私が説明義務違反として仲介手数料全額22万円の返還を内容証明で請求したところ、仲介業者は業者確認が必要だとは伝えたとして、説明義務違反を否定し、エアコン工事費の一部として2万円のみ提案していますが、納得できず、少額訴訟を検討しています。加えて、重要事項説明書や口頭説明がないまま、仲介手数料1.1か月分を契約前に支払っている点にも問題意識があります。
1
0
投稿日:2026年01月25日
回答日:2026年01月25日
夫側の浮気が原因で離婚する場合、慰謝料はいくらかかるか知りたいです。
知り合いの話なのですが、10年前の結婚前から浮気相手がいて奥さんが妊娠中にバレ、認めてはないものの信用を失い、10年間レスにもなり、最近は夫婦関係が破綻し、会話もなければ洗濯物なども別、朝と夕飯は作ってくれているそうです。
それでも旦那さん側から離婚を切り出した場合、慰謝料と養育費はどのくらいかかるのか知りたいです。子供は小4の息子のみです。
よろしくお願いいたします。
1
0
投稿日:2026年01月21日
回答日:2026年01月21日
参考人として出頭要請がありました
以前付き合いがあった取引先企業が外為法違反の被疑者となっています。当時、私が被疑者の担当として付き合いがあったので、警察から電話がありました。参考人として、調書を取り、チャット履歴も確認したいと言われています。話しぶりでは、多少共犯として疑われている印象もうけました。任意ではありますが、出頭しないとデメリットでしょうか。
1
0
投稿日:2026年01月19日
回答日:2026年01月19日
母が母名義の不動産を知人に無償で貸していた不動産を取り返したい。
母名義の不動産に関し、今後の対応について匿名で初期相談をさせていただきます。
物件は東京都内の区分所有マンション一室(事業用可)で、所有者は私の母、相手方は知人男性およびその関係法人です。
当該物件は、母が税理士事務所として長年使用していた事業用物件で、当時から相手方より「法人登記上の本店所在地として住所を使わせてほしい」との依頼がありました。母は「本店所在地表示目的に限り、実際の使用や占有は一切認めない」前提で、書面契約なく無償・一時的に許諾しました。
その後、母は高齢となり数年前に実質廃業しましたが、管理能力が低下していた時期に、相手方が無断で法人名の表札・室内に自身の法人の掲示物等(宅地建物取引業者票等)を設置しました。現在、室内は居住実態・事業実態ともになく空室状態で、登記変更・鍵返却・掲示物撤去も未了です。
昨年末に普通郵便、今年1月に内容証明で上記許諾解除通知を発送しましたが、不在持戻りとなり反応はありません。
現在、防犯上の理由から鍵交換を検討していますが、自力救済と評価されるリスクについて初期的なご見解を伺いたく存じます。
2
0
投稿日:2026年01月17日
回答日:2026年01月19日
有料副業コミュニティで退会できずに困っている
有料副業コミュニティに先月加入しましたが、案件先の会社からクレームが会社にクレームが来ていて裁判を起こすかもしれないと言われました。
案件が全て終わったと思い退会申請をし、ラインの内容も全て消してしまいましたが、その後にカード決済が何回か走りましたが残高不足のため無視していました。
その後にその副業コミュニティの代表から個人ラインが来て、案件が途中なので月額費を払えと言われ払わない場合は、提携弁護士から督促すると言われました。
案件を再開し、案件をやりたい旨をLINEのアカウントに連絡したところブロックしたためお断りと連絡をもらいました。
それだけなら良かったのですが、その案件元の企業から有料コミュニティの会社にクレームで裁判起こすかもしれないと言われています。
契約違反だと言われたのですが、契約が手元にないのでわからないのですが、裁判になった所で私が何か費用を払わないといけないのでしょうか?
有料副業コミュニティの名前はあり、どうやら法人企業らしいですが連絡先がラインのみのため、企業の連絡先も不明です。
1
0
投稿日:2026年01月16日
回答日:2026年01月16日
公園での過度なスキンシップについて
当時は全く犯罪かもしれないなどとは考えていなかったが、急に不安になりました。既に4ヶ月ほど経過しています。後日逮捕されたらどうしようかと心配です。
1
0
投稿日:2026年01月16日
回答日:2026年01月16日
マッチングアプリでの出会い、不同意性交等の訴えについて
マッチングアプリにて女性と出会い、飲食後、宿泊しているホテルへ行く許可を得て、出会ったその日にホテルで避妊をした上で関係を持ちました。ホテルに行く前には、コンビニで飲み物を買って友好的に入室しております。
乱暴なことも一切しませんでしたが、行為途中からお互いにやや盛り上がりにかける雰囲気になり、そのまま女性を部屋から見送りました。(着替えもしていないことから、そこはやや不満そうでした。)
ただ、その日にごちそうさまでした、また機会があれば会いましょうというメッセージがマッチングアプリでおくられてきたのですが、翌日にブロックされました。(ブロックされると相手とのメッセージは全て削除され現在は残っておりません。)
自分自身、着替えもせずに部屋から見送ったことは良くなかったと反省しておりますが、この場合、不同意性交等の被害届が出された場合は事件化する可能性はございますでしょうか。
1
0
投稿日:2026年01月07日
回答日:2026年01月07日
暴行罪の慰謝料を支払わせたい
駅のホームで歩きスマホをしていた加害者と肩がぶつかった後に、突然背後から突き飛ばされました。
駅員が仲裁に入り、その場は加害者が謝罪して別れたのですが、その後どうしても許せずに
後日、警察へ被害届を出して、最終的に暴行罪で略式命令で罰金を支払ったようです。
その後も加害者は誠意のない対応だったので、内容証明郵便で慰謝料を請求したのですが、この段階で相手側の弁護士がでてきて
「事件当日に謝罪して別れているので、和解が成立している」と言ってきました。
2
0
都道府県ごとのその他弁護士から探す
お住まいの地域を選択してください
関東
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
関西
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
東海
愛知
岐阜
静岡
三重
北海道・東北
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
北陸・甲信越
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
中国・四国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
九州・沖縄
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
その他弁護士に相談する
- 東京
- 大阪
- 愛知
- 神奈川
- 福岡
- その他
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかどうか
・弊社サイト経由の問合せ量の多寡
・サイト掲載中の事務所解決事例の豊富さ
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかどうか
・弊社サイト経由の問合せ量の多寡
・サイト掲載中の事務所解決事例の豊富さ