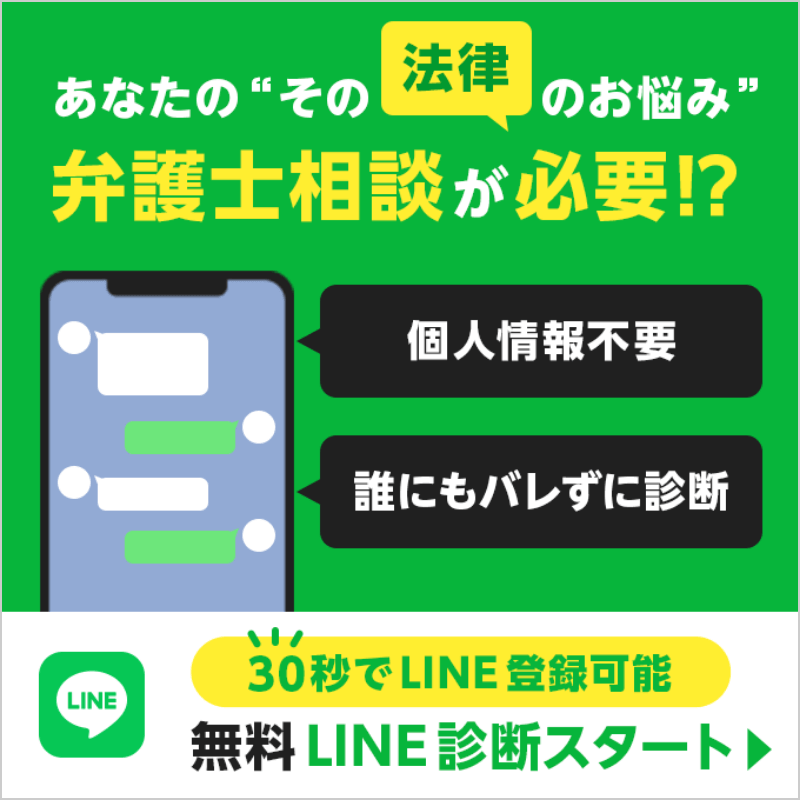弁護士の回答一覧
回答日:2025年09月08日
弁護士法人染矢修孝法律事務所

このたびはご相談いただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下のとおりご回答いたします。
1. 遺言書の撤回について
被相続人(ご主人)がすでに亡くなられている場合、遺言書を「撤回」することはできません。遺言は死亡の時点で効力が生じ、原則としてその内容に従って相続が進められることになります。
2. 遺言書の有効性について
ただし、遺言書に法的な不備がある場合や、作成時に判断能力が欠けていた場合などは、「無効」を主張できる可能性があります。この点は、遺言書の形式や作成経緯を確認する必要があります。
3. 長男の遺留分について
仮に遺言が有効で長男が排除されていた場合でも、長男には「遺留分」という最低限の取り分を主張する権利があります。子が3人の場合、長男の遺留分は遺産全体の6分の1となります。長男が請求すれば、二男・三男にはその分を金銭で支払う義務が生じます。
4. 今後の対応について
自筆証書遺言の場合、遺言書を家庭裁判所で「検認」し、有効性を確認する必要があります。
遺言が有効であっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。
現状、長男に相続開始を知らせていないとのことですが、これは重大な法的リスクを伴います。後日の争訟を避けるためにも、必ず長男に相続開始を通知し、相続人全員で協議を行う必要があります。
5. まとめ
遺言を撤回することはできません。
無効の可能性がある場合には、検討が可能です。
遺言が有効であっても、全員の合意により法定相続分に近い分割が可能です。
長男を外したまま手続きを進めると、後に紛争となる危険が非常に高いため、必ず通知して協議に参加させるべきです。
ご希望が「法律に沿った遺産相続」である以上、まずは遺言の有効性を確認しつつ、長男を含めた話し合いを整えることが最善と考えます。
今後の具体的な進め方等に関して、ご相談がある場合には、弊所での相談やWEb相談等をご利用いただくことも可能ですので、ご希望があればお知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人染矢修孝法律事務所
弁護士 染矢修孝
回答した事務所の紹介
弁護士法人染矢修孝法律事務所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松No.41-301
初回の面談相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応
お住いの都道府県を選ぶ
北海道・東北
関東
中部
関西
中国・四国
九州・沖縄
法律相談Q&Aランキング
父親はどこまで頑張れば親権を取れるのか
2024年10月21日
1
20
SNSでの児童ポルノについて
2025年05月29日
1
7
副業助成金は詐欺ですか?
2024年12月23日
1
28
別れたら死ぬと言っている彼女について
2024年03月13日
1
57
離婚するといったら死ぬと言われた場合
2025年03月26日
1
21
相続問題に関するその他の質問を見る
フリーワードで探す
この質問に関連する法律相談
投稿順
役立った順
関連順
投稿日:2026年01月15日
回答日:2026年01月16日
契約後の報酬額の交渉は可能か
[民事訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件]というくくりで、遺産分割協議の代理人をお願いすべく弁護士に依頼し、委任契約書を交わしました。
我の強い相続人が1人いたせいで難航するであろうと予想されておりましたが、こちらが代理人を立てたことで焦ったとみえ、相手も早々に (優秀な) 弁護士を投入してきたお陰で早目に終結を迎えるに至りました。
結果、こちらの代理人であった弁護士は問題の相続人と一度も直接交渉をすることはなく (何なら、逆にこちらの代理人のせいで揉めそうになった)、行政書士でも可能な書類の取り寄せや事務処理のみに終始した挙句、手続きが最も猥雑であったはずの代理人を立てなかった相続人がいち早く完了している… という体たらくだったのですが、それでも最初に交わした契約書に記載通りの報酬額をお支払いしなければならないでしょうか?
因みに、この弁護士が所属する法律事務所のHPには[円満遺産分割サポート]という項目もあり、そちらだと報酬額はかなり抑えられているようなのですが。
1
0
投稿日:2025年12月21日
回答日:2025年12月23日
生命保険の受取に関して
父親の生命保険金が受取人が弟と自分になっているのですが(保険会社にも確認したら2分割と言われました。)代表者が弟で叔父さんが管理するといって、弟の通帳を預かり
全部貰えると思うなよと言われ、半分以下しか貰っていません。弟もおじさんのいいなりで連絡も連絡先もわからないです。
何度も連絡していますが、
無視され、貰えません。
どうすれば宜しいでしょうか?
ちなみに相続放棄しています。
1
0
投稿日:2025年09月20日
回答日:2025年09月20日
生命保険が遺産分け対象となるか
母が亡くなりました。
父は既に亡くなっており、
法定相続人は兄と私の2人です。
母は生命保険に入っており、
保険金は990万円で、
母死亡時の受取人は私と保険契約に設定されています。
1
0
投稿日:2025年09月08日
回答日:2025年09月08日
遺言書を撤回して、法律に基づいた遺産相続がしたい。
3人の息子がいます。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。
1
0
投稿日:2025年08月28日
回答日:2025年08月28日
相続における遺留分請求の可能性と費用について
父方の祖父が今年2月12日に亡くなりました。祖母、父は既に故人で、相続人は祖父の娘(父の妹)、私、妹です。
祖父は遺言書を残しており、内容は私と妹に各150万円、叔母にそれ以外の全財産となっていました。総資産は財産目録上で約7,000万円ですが、不動産は時価換算されておらず、実勢価格では1億円近くになる可能性があります。
叔母から「遺言分与後にさらに350万円ずつ送る。相続税や税理士費用は負担する」と申し出がありましたが、遺留分が全く満たされていないため、私は争う方向で検討しています。
2
0
投稿日:2025年08月10日
回答日:2025年08月13日
弟との相続手続きのトラブルについて
母の遺産、郵便貯金と土地と家。
相続人は私と弟の2人だけです。
弟が印鑑証明書など必要書類を送って来ません。
亡くなって1年経ちますが何度催促しても協力せず困っています。
2
0
投稿日:2025年07月16日
回答日:2025年07月17日
1人に財産が集中している不公平相続の場合、どのようにしたら好転できるでしょうか。
約20年前に父が亡くなり、相続人は母と長女、次女《自分)、長男、の4人でしたが、なんの相続も行わないまま、2024年2月に母が亡くなりました。
遺産は、おおまかなところで、
実家の土地と家 時価9000万円
貯金現金4000万円
母の死亡保険金約4880万円
遺言書があり、実家の土地と家は、長男に、と書いてあり、死亡保険金の受け取り人は長男です。当初、死亡保険金があることは長男は内緒にしており、そのことを知ったのは、相続税 納入期限が迫った 2024年の11月でした。分割について何も決まらす、時間がなかったので 相続税は とりあえず全てを1/3に分けるという方法で納税しました。死亡保険金があったことで相続税がかかりました。
最近になり、1人に多くの財産がかたよっている相続の場合、裁判では違った 判決が出る例があることや、死亡保険金を含めた財産の遺留分が認められる場合があることを知りました。
母が死亡してから1年以上経っておりますが 生命保険金があったことを知った時からは1年は経っていません。
1
0
投稿日:2025年05月03日
回答日:2025年05月06日
遺産がはっきりせず、実家とも話し合いにならないので助けてほしい。
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。
相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。
5/1に母親から
『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、
戸籍謄本
印鑑証明書
が必要です。取り寄せて送って下さい。』
とLINEが入り不信感を覚えたので『大事な書類なので託せない」と返したところ
長女から電話が来たので拒否したところLINEにて私を除いたところで遺産分割しようとしていることがわかりました。
特に余分にもらいたいなどとは思っていませんが遺産の内容をはっきりとしてから協議して結論を出したいと思っていますが
話し合いがしたいなら葬儀代を出せとか分家とか論点をずらされて話し合いになりそうにありません。
どうか、弁護士の方に間に入っていただこうと考えています。
1
0
投稿日:2025年04月30日
回答日:2025年04月30日
遺産分割協議の特別受益について
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
2
0
投稿日:2025年04月15日
回答日:2025年04月15日
不動産の売却を伴う遺産分割方法について
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。
2
1
投稿日:2024年06月29日
回答日:2024年06月29日
後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?
3
10
投稿日:2024年07月06日
回答日:2024年07月08日
代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています
2
4
投稿日:2022年03月10日
回答日:2022年03月10日
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。
4
4
投稿日:2022年03月11日
回答日:2022年03月12日
2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人
母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし
母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。
家に住みたいなら代償金を出せと云われています。
長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。
自宅を売りに出すしかないのでしょうか?
母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。
1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。
同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
2
3
投稿日:2021年11月26日
回答日:2021年11月26日
遺産相続での苗字について
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?
3
3
投稿日:2023年04月28日
回答日:2023年05月01日
亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。
不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1
3
投稿日:2024年05月27日
回答日:2024年05月27日
介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません
3
3
投稿日:2024年08月30日
回答日:2024年09月01日
遺産分割協議ができない
母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。
私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。
遺産分割協議に進めない状態です。
銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。
最近では連絡にも応じてくれないのですが、どのように進めたらよいでしょうか。
2
2
投稿日:2024年11月27日
回答日:2024年11月27日
特別受益の精算をしたい
私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。
1
2
投稿日:2024年12月04日
回答日:2024年12月04日
遺産分割協議を二転三転される。
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。
相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。
相続は
土地 査定額2700万
マンション 800万
預貯金 500万
土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。
遺言書(一部不備と指摘)の内容
マンション 私
土地 私と弟 二分の一
預貯金 私と弟 二分の一
遺産分割協議書
マンション 私
土地 弟 1000万私に支払後登記
預貯金 私 弟 二分の一
私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局
これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。
1
2
投稿日:2025年12月21日
回答日:2025年12月23日
生命保険の受取に関して
父親の生命保険金が受取人が弟と自分になっているのですが(保険会社にも確認したら2分割と言われました。)代表者が弟で叔父さんが管理するといって、弟の通帳を預かり
全部貰えると思うなよと言われ、半分以下しか貰っていません。弟もおじさんのいいなりで連絡も連絡先もわからないです。
何度も連絡していますが、
無視され、貰えません。
どうすれば宜しいでしょうか?
ちなみに相続放棄しています。
1
0
投稿日:2025年09月20日
回答日:2025年09月20日
生命保険が遺産分け対象となるか
母が亡くなりました。
父は既に亡くなっており、
法定相続人は兄と私の2人です。
母は生命保険に入っており、
保険金は990万円で、
母死亡時の受取人は私と保険契約に設定されています。
1
0
投稿日:2025年09月08日
回答日:2025年09月08日
遺言書を撤回して、法律に基づいた遺産相続がしたい。
3人の息子がいます。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。
1
0
投稿日:2025年04月30日
回答日:2025年04月30日
遺産分割協議の特別受益について
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人です。
遺産は実家と預金僅か。
実家は弟が引き継ぎ代償分割をすると主張しています。
弟は20年ほど前県外で一人暮らしをしており無職になった際、仕事が決まるまでと母に仕送りを頼み毎月11万程度、約6〜7年も送ってもらっていました。
この仕送りは特別受益に該当するでしょうか。
該当する場合、仮に家の評価額500万、預金100万の場合弟の遺留分を考えると私が受け取れる金額はいくらほどでしょうか。
仕送り分の口座の利用明細書は手に入りそうです。
2
0
投稿日:2025年04月15日
回答日:2025年04月15日
不動産の売却を伴う遺産分割方法について
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。
2
1
投稿日:2024年12月04日
回答日:2024年12月04日
遺産分割協議を二転三転される。
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。
相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。
相続は
土地 査定額2700万
マンション 800万
預貯金 500万
土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。
遺言書(一部不備と指摘)の内容
マンション 私
土地 私と弟 二分の一
預貯金 私と弟 二分の一
遺産分割協議書
マンション 私
土地 弟 1000万私に支払後登記
預貯金 私 弟 二分の一
私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局
これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。
1
2
投稿日:2024年10月25日
回答日:2024年11月17日
二世帯住宅の遺産の分け方について
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。
兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。
兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。
二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。
兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。
1
0
投稿日:2024年10月01日
回答日:2024年10月01日
共有分の解消と分割協議書について
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?
1
0
投稿日:2024年07月30日
回答日:2024年07月30日
遺産の中からの支払いの仕方について。
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。
2
0
投稿日:2024年07月27日
回答日:2024年07月29日
納得できる遺産分与をしてほしい。
遺産分与に関して
姉は出生後、父と数回しか会っていないのに
父とずっと一緒に住んでいた私は同じ割合で
分けることに納得いきません。
意見が合わず話し合いができないので
弁護士を通してやり取りをしていきたいです。
1
0
都道府県ごとの相続弁護士から探す
お住まいの地域を選択してください
関東
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
関西
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
東海
愛知
岐阜
静岡
三重
北海道・東北
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
北陸・甲信越
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
中国・四国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
九州・沖縄
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
相続弁護士に相談する
- 東京
- 大阪
- 愛知
- 神奈川
- 福岡
- その他
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかどうか
・弊社サイト経由の問合せ量の多寡
・サイト掲載中の事務所解決事例の豊富さ
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかどうか
・弊社サイト経由の問合せ量の多寡
・サイト掲載中の事務所解決事例の豊富さ